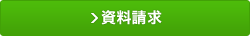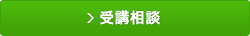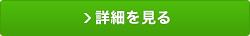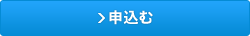コース・料金(税法実務:スキルアップ)
ご自身の必要なスキルに合わせて
最適なコースが選択できます!
-
法人税
(地方税など含む)
-
所得税
-
消費税
-
相続税
開講コース一覧
| NEW |
税制改正のポイントをわかりやすく解説! 物価上昇局面における税負担の調整等の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得 |
|---|
| NEW |
2027年4月から適用される新リース会計基準。税法上の 処理と乖離する点を税務申告において調整することが必要です。 新リース会計基準適用後は、リースか非リースかの識別を行い、重要性のあるリースに該当する場合は、原則として「使用権資産」および「リース負債」のオンバランス計上が求められます。また、不動産賃貸借取引もリースに該当する可能性があり、大きな影響が見込まれます。一方、税制上は旧来のリース取引、リース以外の賃貸借取引の取扱いに大きな変更がないため、会計と税務での不一致を税務申告において調整しなければなりません。本講座では、新リース会計基準の実務上のポイントを解説するとともに、設例を上げながら、税務との異同点とその調整について解説します。 |
|---|
|
重要度の高いケーススタディにより、別表5の記載方法を網羅的に完全マスター! 別表4および5(一)(二)は、については、作成方法だけでなく、申告書・別表がどのように関連しているかを把握することが、実務上必要なスキルとなります。 |
|
「修正申告書」「翌年度の確定申告書」の作成ポイントと留意点を解説! 「当年の確定申告書」、「修正申告書」との関係、「修正申告書」「翌年度申告書」との関係、過年度遡及会計基準の適用などの留意点の把握は、実務上必要なスキルとなります。 |
|
重要テーマ「繰延資産」「リース取引」「役員給与」の税務処理を学習 「繰延資産」「リース取引(借り手)」「役員給与」は、一般の会計処理と異なる法人税法上の取扱いや別表の記載方法を把握することが、実務上必要なスキルとなります。 当講座では、繰延資産、リース取引、役員給与の税務処理と別表の記載方法を学習します。 |
|
重要テーマ「益金配当等の損金不算入」「みなし配当」の税務処理を学習 「受取配当等の益金不算入」および「増減資等の場合のみなし配当」各制度の課税関係、別表の記載方法を把握することが、実務上必要なスキルとなります。 当講座では、受取配当等(みなし配当含む)の税務処理と別表の記載方法を学習します。 |
|
重要テーマ「設立第一期」「外貨建資産等」「控除対象外消費税」等の税務処理を学習 「棚卸資産」「有価証券」「外貨建資産の換算等」「控除対象外消費税等」「保険料、入会金など」「債務確定基準」「設立第一期」の概要を把握することが、実務上必要なスキルとなります。 当講座では、これらの実務上重要なテーマについての税務処理を学習します。 |
| Renewal |
海外進出の形態や資本形態の多様化に伴い重要となる国際税務の概要をマスター! 海外進出をしている企業が増えており、国際税務の知識の重要性が高まってきています。 |
|---|
|
収益認識基準の会計と税務のポイントをマスター! 収益認識会計基準は、収益認識を5つのステップを踏んで行います。この収益認識の考え方をマスターし、企業への影響を把握しておく必要があります。当講座では、既に強制適用となっている、収益認識会計基準の基本的な考え方および法人税の取扱いについて解説していきます。 |
| Renewal |
固定資産に関する会計や税務の実務を詳細に解説! 固定資産に関する実務は、取得価額・減価償却費の計算・資本的支出と修繕費・リース取引など様々あります。 |
|---|
|
圧縮記帳制度の効果と、それぞれの規定の具体的な要件や計算方法を学習! 圧縮記帳は、本来は課税所得として発生している利益について、一定の場合に将来に課税を繰り延べるのが圧縮記帳ですが、各規定により要件や計算方法が異ります。 |
|
資本的支出と修繕費を判断する際の留意事項を、具体例と合わせて確認する! 資本的支出と修繕費のいずれに該当するかの判定は、納税額へ大きな影響を及ぼすことがありますが、実際には、その区分が非常に難しい場合も少なくありません。 |
| Renewal |
はじめてグループ通算制度を学習する方のために制度の基礎解説! グループ通算制度を導入するにあたって、そもそもどのような制度なのかを理解しなければ活用できません。 |
|---|
|
「グループ法人税制」の制度と税務処理を学習し、予想外の課税を回避する! 事業を行っていく上では、複数の企業によるグループ経営が行われるケースが多くあります。法人税では、グループ通算制度を採用していない企業でも、完全支配関係にあるグループ会社間の取引について「グループ法人税制」が適用されます。グループ法人税制を知らないと予想外の課税が生じたり、税務上の不利益を受ける可能性があります。逆に、グループ法人税制を上手く利用すれば、グループ会社間での資産の移転や資金の移動を税負担なく行うことが可能となって、グループ経営をスムーズに行うことができると言えます。当講座では、グループ法人税制の基礎を解説するとともに,実務上留意すべき点について解説していきます。 |
|
連結納税制度→グループ通算制度への移行で何がどう変わるかを解説! 連結納税制度が見直され、令和4年4月1日以後に開始する事業年度からグループ通算制度が施行されますいます。当講座では、連結納税制度の見直しのポイント、グループ通算制度の概要、連結納税制度からグループ通算制度に移行する場合の判断ポイント、単体納税制度からグループ通算制度を開始する場合の判断ポイントについて解説していきます。 |
|
経営戦略としての組織再編をめぐる税務上の取扱いについて解説! 法人税においては、組織再編特有の取扱いがあり、実務での重要性は高く、組織再編にあたっ |
| Renewal |
租税特別措置法の法人税額の特別控除制度の要件・計算方法等について解説! 税額控除制度は納税額に直接影響を及ぼすため非常に重要な論点ですが、租税特別措置法に規定する特別控除制度の中には、その適用要件や計算方法が複雑な制度もあり、適用にあたっては慎重に検討を行う必要があります。当講座では、賃上げ促進税制(給与等支給額が増加した場合等)をはじめとする租税特別措置法に規定する各種の法人税の特別控除制度について、適用要件から控除額の算定まで解説していきます。 |
|---|
|
税効果会計の基本的な仕組みと「法人税申告書」との関係について解説! 上場企業やその連結子会社などは、四半期ごとに税効果会計の処理が必要です。会計基準の理解と法人税申告書との関連性を把握することが、実務上必要なスキルとなります。 当講座では、税効果会計の基本的な仕組みのほか法人税申告書との関係について解説します。 |
| Renewal |
事業税の「外形標準課税」・「分割基準」について体系的な学習と申告業務のポイントを解説! 外形標準課税制度は、法人税の計算とは一線を画していることもあり、要所において法令等の |
|---|
| Renewal |
「個人住民税」の計算方法、「法人住民税」の申告書作成について学習! 個人住民税は、所得税の申告書に基づいて課税する賦課課税方式です。法人住民税は事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に申告書を提出する申告納付方式です。当講座では、個人住民税がどのようなプロセスで計算されるか確認し、基本的な法人住民税の申告書の様式とその作成手法を解説していきます。 |
|---|
| Renewal |
さまざまな給与、報酬の源泉徴収について、その可否と計算上の留意点を解説! 源泉徴収実務は、日次・月次に発生する重要な業務であり、課税対象の判断を誤れば源泉徴収 |
|---|
| Renewal |
譲渡所得の申告書の作成をマスター! 土地・建物等の譲渡には様々な特例が存在するため、どの特例の適用を受けられるかを判断し、それに基づく税額の算定が重要です。当講座では、土地・建物等の譲渡所得の基本から、各種特例の要件、所得税の申告書の作成までを具体例を用いて解説していきます。 |
|---|
|
金融商品課税を体系的にマスター! 当講座では、金融商品課税のまとめとして、利子所得、配当所得、譲渡所得の所得区分、課税方法を整理し、確定申告の有利不利の判断の仕方までを体系的に学習します。 |
| Renewal |
法人成りのメリット、デメリットを理解し、有効活用法をマスター! 法人成りを検討する際には、個人事業を法人化することのメリット・デメリットを確認し、法人成りの税務、法人成り後の注意点を含めて考えることが必要です。当講座では、法人成りを取り扱う際に、どのような点に注意しなければならないか、また、設立した法人に対する資産の移転や賃貸する場合の取扱いなどを網羅的に解説していきます。 |
|---|
|
住宅の取得、改修などを促進するための住宅関連税制。代表的な住宅借入金等特別控除制度を中心に実務上のポイントを解説 住宅関連税制は持家政策の促進と住宅投資を通じての内需拡大を図ることを目的として創設さ |
| Renewal |
医業特有の計算、付表の書き方についても徹底解説! 医業(個人)の計算は、通常の事業所得とは異なり、社会保険診療に係る必要経費を概算経費 |
|---|
|
国際税務に実務に関わる各国の「租税条約」・「租税協定」を体系的に解説! 近年は海外進出をしている企業が増えてきています。海外に支店を設置したり現地法人として子会社を設立するようなケースが増えています。逆に、海外法人が日本に子会社を設立する場合もあります。このような場合、実務において国際税務の知識が必要となります。税制の詳細な内容は必要に応じてマスターする必要がありますが、どのような制度があり,またどのような点に留意すべきなのかについて把握をしておきたいところです。当講座では,国際税務の概要について、米国・中国・シンガポール&香港・英国・台湾の5ヵ国について解説していきます。 |
| Renewal |
「海外勤務者」と「在日外国人」に関する税務を形態別に解説! 企業のグローバル化に伴い、国内法人から海外支店・子会社への出向・転籍等により「海外勤務者」となる方が増加し、各人の課税関係は複雑な処理が必要となってきています。当講座では、このような実務を正しく行えるように海外勤務者の「出国」「海外滞在期間」「帰国」それぞれの時点での取扱いおよび国外に転出する際の注意点を解説していきます。 |
|---|
| Renewal |
「国際取引に係る源泉徴収」と「租税条約の取扱い」について体系的に解説! 企業活動のグローバル化に伴い国際取引が増加し、外国法人への報酬・配当・利息の支払い、非居住者に対する給与の支払等について、正しい源泉徴収実務が必要となります。当講座では、国際税務のうち、国際取引に係る源泉徴収事務を正しく行うために国内法及び租税条約の取扱いについて体系的に解説していきます。 |
|---|
| Renewal |
申告漏れに注意したい「国外転出時」に係る取扱いの要点を解説! 国外転出時課税制度とは、国外転出をする一定の居住者が、1億円以上の有価証券等を所有等 |
|---|
| Renewal |
インボイス制度の施行に伴う消費税実務の留意点について令和7年度の税制改正も踏まえて徹底解説! 消費税インボイス制度が令和5年10月から導入されました。この制度により、従来の区分記載請求書に代えて適格請求書等(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となりました。この適格請求書を発行するためには、事前に申請して適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。事業者としては、事前申請や請求書等の記載事項の変更などが必要となり、制度導入後において、適格請求書か否かを判断しなければならず、従来と異なる経理処理が求められることとなりました。当講座では、インボイス制度の概要を判りやすく解説し、さらに導入後の仕入税額控除の適用要件、消費税の経理処理など消費税の実務で特に留意すべきポイントやインボイス制度施行後の様々な見直しについても取り上げます。また、事例を挙げながら消費税の税額計算、申告書記載方法についても解説しています。 |
|---|
| Renewal |
消費税の還付を受けるための条件と手続きについて、法律内容を理解しながらマスター! 消費税の還付を受けるためには、課税事業者に該当していることや簡易課税制度の適用を受けていない事業者であることなど、いくつかの条件が備わっていなければなりません。当講座では、法律的な内容を交えながら消費税の還付を受けるための条件や手続きについて解説していきます。 |
|---|
| Renewal |
軽減税率の制度内容、対象品目や留意点を具体的に解説! 軽減税率の制度の導入により、商品等の価格表示や請求書等の記載方法が変更となり、複数税率により経理処理を行う必要があるため、消費税の計算が従来より複雑になっています。 |
|---|
| Renewal |
リバースチャージの内容や実務上の留意点を徹底解説! リバースチャージ方式は、国内の事業者が受けた事業者向け電気通信利用役務の提供については、国内の事業者側が消費税の申告納付を行う制度です。 |
|---|
|
「生命保険・損害保険」に加入した場合の税務の取扱いを体系的に解説! 個人で「生命保険・損害保険」に加入した場合の保険料の取扱い、法人で「生命保険・損害保険」に加入した場合の保険料の取扱い、実際に保険事故が発生した場合の保険金の取扱いの税務処理は非常に重要です。 当講座では、それぞれの取扱いを所得税、法人税、相続税、贈与税の観点から確認し、具体例を用いて解説していきます。 |
| RenewalFP継続教育研修対象講座! |
土地・建物・有価証券等の財産評価をマスター! 相続税と贈与税では、共に無償で取得した財産の価額を基礎に税金計算を行います。申告書を作成する際には財産の価額がいくらになるかが最も重要な要素となります。 |
|---|
| RenewalFP継続教育研修対象講座! |
財産評価時の重要度の高い、「取引相場のない株式」の評価をマスター! 難解で難しく感じられる、「取引相場のない株式」の評価。相続時の財産評価で重要度の非常に高いテーマです。当講座では、財産評価のうち「取引相場のない株式評価」に特化し、その評価と税務上の取り扱いを解説します。 |
|---|
| Renewal |
相続税対策に欠くことができない生前贈与対策、 そして難解な事業承継税制を基礎から確認し、お客様のニーズに応じた選択肢を解説 平成27年に施行した相続税法の改正より相続税は増税路線に舵を切りました。相続税対策を検討する場合に生前贈与の実施は引き続き有効な対策になりますが、お客様のニーズに合う提案をするには、令和5年度税制改正はもちろん、民法改正その他さまざまな規定を理解しておく必要があります。当講座では、基本知識となる相続税や贈与税の計算の仕組み、民法の改正点、令和5年度税制改正、そして事業承継税制に関する基本内容の確認、スキームに応じた活用方法について検討していきます。 |
|---|
|
小規模宅地等の特例の適用要件の判定をマスター! 相続税においては、宅地等の評価額を80%又は50%減額してもらえる小規模宅地等の特例の適用を受けられるか否かにより納税額に大きな差が生まれます。本講座では、相続税実務を行う上で確実に理解しておきたい小規模宅地等の特例について税制改正も踏まえて詳しく解説します。 |
|
みなし相続財産・みなし贈与財産を態様別に解説! 税法における「みなし規定」は法的拘束力が強いため処理を誤ると思わぬ課税を受ける可能性があります。そのため、みなし相続財産、贈与財産について正しい知識を身に付けておくことが必要です。本講座では、相続税や贈与税におけるみなし課税の規定および、関連する所得税法の一部を解説します。 |
|
配偶者の特別な規定について解説! 民法及び相続税や贈与税の規定の中でも正式な婚姻関係にある配偶者には特別な規定があります。本講座では、相続税や贈与税の制度の中で設けられている配偶者関連の規定についてその要件や手続きおよび、民法改正により新設される配偶者居住権について解説します。 |