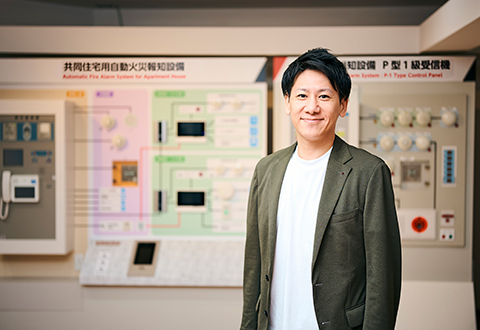日本のプロフェッショナル 日本の社会保険労務士

宇梶 純江(うかじ すみえ)氏
すみえ社会保険労務士事務所 代表
社会保険労務士
1978年、栃木県真岡市生まれ。電気メーカーにて、人事・労務業務に13年間従事。2010年、社会保険労務士試験合格。2011年4月、すみえ社会保険労務士事務所を開設。
開業して、やりたいことができて、会いたい人に会える。
思いの丈、仕事ができて幸せです。
電気メーカーに13年間勤務し、人事・労務業務に携わったキャリアを活かして社会保険労務士資格を取得した宇梶純江氏。メーカー勤務も資格取得も順風満帆とはいかなかった。そんな宇梶氏に、開業に至るまでの経緯と現在の活躍についてうかがった。
高卒で人事労務のエキスパートに
現在、社会保険労務士(以下、社労士)として活躍する宇梶純江氏の社会人としての第一歩は、電気メーカーの工場製造ラインの組立オペレーターだった。栃木県の女子高校を卒業して入社した宇梶氏は、工場の製造ラインでは目立ち過ぎる存在だった。
「私はエネルギーがありあまっていました。Windows95が出てパソコンが1人1台になりつつあった当時、これからはパソコンの時代だと思い、製造員なのにExcelの本を買って事務所のパソコンで習い始めたんです。先輩たちはこれがおもしろくない。生意気だと仲間はずれにされました」
そんな状況を見かねた総務部長は、人事課に欠員が出たとたん宇梶氏を異動させた。入社2年目で人事課に移ったことが、社労士への第一歩になった。人事課では、人事労務の仕事の中で新卒採用と社員教育以外のすべてを経験。約500名の勤怠集計から勤怠管理、給与計算、出張精算、グループ24社約1,450名の請負派遣先責任者まで務めた。
「とにかくおもしろかったんです。在籍中、会社が2回統合して、最終的に2,000名規模の会社になったとき、統合プロジェクトメンバーもやりました。システムを導入したり、管理職教育をしたり。普通は高卒社員がやらせてもらえないような仕事を、どんどん任せてもらいました」

5年かけて社労士試験に合格
もっとキラキラ輝きたい。もっと任せてほしい。人事の仕事を極めたい。そう思ったときに出会ったのが社労士資格だった。社労士は実務経験2年以上で高卒でも受験資格が得られる。しかも、グループ内に社労士はいない。資格を取得すれば東京本社勤務も夢じゃないかも、と夢見て宇梶氏はTAC大宮校に通い始めた。
「講座のある土日は朝8時45分、自習室が開く前に誰よりも早く行って、誰よりも遅く帰りました。ずっと机にかじりついて、スタッフに声をかけられるまで自習室で勉強です。27歳から31歳の5年間を、社労士受験に捧げました。彼氏も欲しかったけど、受験仲間と『合格するまでは勉強をがんばろう』と誓い合いました(笑)」
すべてを社労士合格に捧げて5年。2010年、宇梶氏は社労士試験に合格した。これでグループ唯一の社労士、向かうところ敵なしと思ったときには、合併プロジェクトも落ち着いていた。
「人事係長の男性7人、主任は私1人。30代で既婚、学歴なし。まずいな、一番にリストラされると思っていたら、合格してわずか2週間で製造現場に戻されました」
すでに、通勤に1時間かかるさいたま市に住んでいた宇梶氏に、朝5時からの工場勤務は不可能。実質的なリストラだった。
「会社としては仕方ないのかもしれない。でも、屈辱的でした」
転職を考え人材紹介会社に行くと「30代、学歴なし。ご紹介できる人事の仕事はパート社員。それも100倍以上の倍率。あなたに市場価値はありません」とバッサリ切られた。
「700名の年末調整をサクサクこなして、グループ統合にも関わって……。それを意味がないと言われたようでショックでした。大宮周辺の社労士法人の求人も大卒以上。悔しいですね。実務はできるのに、自分は必要とされていないのだと感じました」
どん底まで落ち込んだとき、不思議と気持ちが軽くなり、視界が開けたように感じた。「それなら自分自身で価値を創り出そう」と宇梶氏は独立開業を決めた。「だから、消去法での開業だったんです」と、宇梶氏は付け加える。
ゼロからの独立開業
2011年4月、宇梶氏はさいたま新都心にあるインキュベーションオフィスで開業第一歩を踏み出した。社労士実務経験ゼロ、顧客ゼロでのスタートだ。
まず、東京都主催の女性開業セミナーを皮切りに異業種交流会7つに参加。そのうち弁護士、税理士、行政書士、中小企業診断士、ファイナンシャル・プランナーと、士業の知り合いが増えていった。初めての顧客も、SNSの創業家コミュニティで同じ埼玉県在住の行政書士から紹介された。
「初めてって怖いんです。何を聞かれるかわからない。社労士資格の業務範囲の10分の1も実務をやっていないので、知らないことばかり。でも、お客様の前ではできるふりをしなければならない。
――労働保険の年度更新はできますか。『はい、お任せください。』
――建設業大丈夫ですか。『大丈夫です。』
もう俳優ですよ。家に帰ってから猛勉強。まだ、インターネット上のコンテンツが充実していなかったので、労働基準監督署に足しげく通って教えてもらいました」
新規の依頼に対応できる組織へ
ネットワークを徐々に広げていくと、2年目から顧客数は緩やかに増えていった。そして2014年、3年目に現在のJR宇都宮線土呂駅から徒歩3分の店舗型オフィスに移転。移転を機にスタッフ採用を開始。開業5年目には売上1,000万円に到達した。
スタートから今年で15年目。現在は顧問数40社、顧客数50〜60社に上る。山あり谷ありの事務所経営でもっともおそろしかったのが、2016年、売上の約3割を1社に依存していた開業6年目のことだ。100名規模の会社が組織改編でいきなり4名に、月22万5000円の顧問料が一気に3万円に。「これはまずい」と肝を冷やした。
「ところが、たった1ヵ月半で13社と契約しました。それまで1年に1〜2社増ペースだったので、神がかり的でしたね。捨てる神あれば拾う神あり。何か目に見えない力を感じて。それからは、どんなことがあっても『大丈夫』が口癖。何とかなると思うようになりました」
顧客数は順調に増え、14年目、2024年9月からはキャパオーバーで新規の依頼を断る事態に陥った。
「需要に対して供給不足のもどかしさに、この3年間苦しんでいます。それは会社としてあるべき姿ではないんです」
課題解決のため、2023年からは事業計画、経営方針発表会を開き、目標に向けて担当者一人ひとりが事業課題を掲げ、達成をめざしている。さらに、2025年はスタッフ2名を採用。新規顧客の受け入れ体制を整える計画だ。

2026年、法人化を計画
現在事務所は、宇梶氏含め社労士有資格者3名、総勢7名の体制になった。今年のスローガンは『器を広げて法人化』。みんなで力を合わせ、2026年1月1日に法人化するのが目標。法人化のきっかけは、社労士有資格者を採用したことだった。
「個人事務所ではいつまでたっても私のお客様。みんなに担当先は自分のお客様だと思ってもらえる組織を作りたいので、法人にします」
法人化に際しては事務所名に自分の名前をはずし、みんなで名前を決めたいという。
「自己実現の場で、私だけが気持ちよかったらダメ。今度はスタッフみんなが輝く番。そのステージに移らなければ、組織化はできません。
目標の規模は大宮で3番目ぐらい。働きやすさはNo.1をめざします。職員がキラキラ働ける職場ならどこにも負けない事務所を作りたいですね」
「豊かで自由で幸せに働ける事務所」にしよう!
宇梶氏が作りたいと願っている組織のあるべき姿が、もうひとつある。「豊かで自由で幸せに働ける」組織だ。
「豊かって何か。社労士事務所の中で一番給与が高くなること。自由はスーパーフレックス。いつ来てもいいし、いつ帰ってもいいし、在宅勤務もOK。会社に来ようが来まいが、それもおまかせ。シフトは一応決まっていますが、みんなママさんスタッフだから家族が第一でいい。子どもたちが1番、家事が2番、旦那さんが3番、何かが4番。事務所は5番か6番でいいから、みんなの生活の延長で働いてもらいたいんです。
人間関係がギスギスしてもダメ。なんかあの人機嫌悪いね、口聞いてくれない。そういうのは一切禁止。お客様にも、一緒に働く仲間にも、所長の私にも、お互いに、みんなに愛情を持つこと。それが実現できているから、みんなよくしゃべります。まるで家族のような雰囲気です」
「豊かで自由で幸せに働ける事務所」をテーマにしたきっかけは、自身の経験から来ている。
「前職は朝8時に工場に入って、窓もない職場で夕方5時まで働いて。外に出るともう真っ暗。もぐらみたいな生活でした。
それが開業して自転車でレンタルオフィスまで行く間、当たり前だけど空が青いんです。空が青くて、雲が白くてきれいだなぁ。なんて自由なんだろう。好きな時間、好きなお客様に対して、好きな仕事が提供できる。なんて幸せな働き方なんだろうって思ったんですね。
私がスタッフを雇ったら、同じように好きな時間に入って、ごたごたした人間関係がなくて、時間に追われないような働き方をしてもらおう。そう心に誓ったんです。
この電車に乗らなきゃ間に合わない。階段をダダダっと駆け上がって、みたいなことにエネルギーを使ってほしくないし、『電車が遅れているので今日5分遅れます』なんていちいち連絡もいりません。時間じゃなくて成果だから、細かいことは気にしません」
思いが伝わって、スタッフは積極的に事務所をよりよくしようと動いてくれる。「だからみんな幸せだよね」と、近くのスタッフに呼びかける宇梶氏。「幸せですよ」とスタッフから返ってくる。気持ちよい職場は、何も言わなくてもわかるものだ。
子育てママには最高の環境
人柄重視の宇梶氏の事務所も、たくさんの人が入ってはやめていった。
「奪い取る『ぎらこちゃん』と、人に対して思いやりがあり『あなたのためにができる人』。経験上、この2パターンあるとわかって。『あなたのために』ができる人を雇っています。かくいう私は『ぎらこちゃん』。ギラギラしてて、やるぞっていうタイプ(笑)。でもスタッフは心穏やかで優しい人ばかり。そういう人なら、未経験でも全然OK。パソコンなんかできなくても大丈夫です」
事務所は子連れ出勤OK。年度末の3月31日、1年で一番忙しい日も、子どもたちが事務所で遊び回っている。
「バンバンバタバタ、こっちのスポーツカーが勝ち!みたいなことをずっとやっています。賑やかすぎたらシー!と言えばわかってくれます。学校帰りに事務所に来ることも。学童代わりですね。夏休みも楽しみで、今年は6人くらい来る予定です。
中には仕事の手伝いをしてくれる子どももいます。給与明細を折って封筒に入れたり、ダブルチェックしてくれたり。社会に触れるよい機会ですね」

社労士が支援できることは無限大
「独立っておもしろい。常に挑戦。毎日ジェットコースターです。普通に生活していたら、こんなにいろいろな人、いろいろな経験に出会えませんでした」
中でも一番やりがいを感じるのは、やはりお客様から「ありがとう、助かりました」と言われたときだ。
「ああ、お役に立ててよかったとつくづく思います。手続きや労働法がわからなくて不安な気持ちでいる社長さんに、私たちが支えるから安心してねという気持ちで関われる。すごくうれしいです」
AIの進化の中で社労士の手続き業務が取って代わられても、開業社労士には「やることも打ち手も、無限大にある」と、宇梶氏は太鼓判を押す。
「人事制度然り。制度は作って終わりではなくて、そのあとの伴走が大事。就業規則しかり。うちでは社内を巻き込んだ就業規則の作り方をしていて、そこに幹部候補にも入ってもらい進めます。経営者の視点や考え方、社員の立場や考え方、どちらも考えながら落とし所を見つけることができる。社員教育の絶好の場にもなります。
また、中小企業は大企業に比べてIT化がとても遅れています。未だにタイムカードもガッチャン方式が多いぐらいなので、IT推進支援もクラウド導入も喫緊の課題です」
単純な入退社や給与計算だけでなく、就業規則からIT化支援まで。さらに、事務所で導入しているBCPも後押しする。BCPとは、自然災害やトップの急逝といった緊急事態に遭遇しても事業を中断させない、中断しても早期復旧させるための「事業継続計画」のことをいう。
「BCPは、2024年から福祉事業所で義務化されました。でも、まだまだ策定されていない会社はたくさんあります。専門機関にBCP支援を依頼すると数百万から1,000万円と高額です。でもそうでなくて、もっと簡単で実務に則した、スタッフを巻き込んだBCPが作れるんです。今地震が起きたらどうする、電気が止まったらどうする、データの保管はどうする。それらをパッケージ化して、地に足のついたBCP支援ができる。社労士が支援できることはいくらでもあるんです」

合格で新しい人生の扉をたたこう
労働基準法や労働者災害補償保険法、雇用保険法……。社労士は、さまざまな内容を勉強する。その中でもっとも使うのは「一般常識」だと、宇梶氏は指摘する。
「『一般常識』で学ぶ法律を、自分なりにどうお客様の実務に落とし込むか。そこが一番の支援になる。一般常識にきちんとフラグを立てて、お客様にご支援できるかどうかで非常に変わってきます。手続きだけをやっている事務所ではなく、いかにお客様のところにぐいぐい入り込めるか。入り込めば入り込むほど、やることはいくらでも出てきます」
「社労士になっていなかったら、思うような職に就けずに、未だに自分探しをしていただろう」と宇梶氏は話す。
「5回の受験は本当に苦しかった。そのうち2回は足切りです。得点は取れていたのに、足切りで切られました。そうするとあきらめたくなる。苦しいんですよ。1年間ものすごく勉強してきたから。でも、自分はあきらめないでよかったと思っています。自分の新しい人生のステージ、絶対出会えなかったであろう、絶対経験できなかったであろうステージの扉をたたくことができたから。
だから、苦しくてもあきらめないで。もう1年チャレンジしてみて。自分の行くべき場所は必ず待っていてくれるから」
そうアドバイスする宇梶氏に、苦しかった当時の面影はない。キラキラ輝く笑顔が印象的だった。
[『TACNEWS』日本のプロフェッショナル|2025年9月 ]