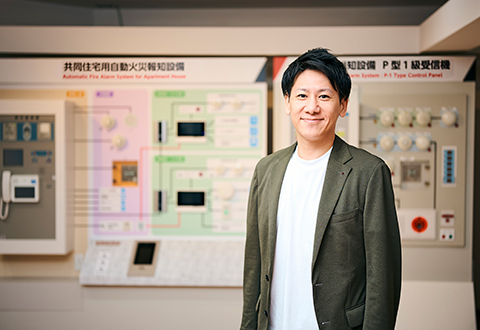人事担当者に聞く「今、欲しい人財」 第81回 オイシックス・ラ・大地株式会社

竜沢 華林(たつざわ かりん)氏
HR本部人材企画室 人材スカウトセクション
新卒でSaaS業界の企業に入社。サブスクリプション型のカートシステムを扱う会社で営業を担当。2022年秋、現在の会社へ第二新卒枠で転職。約2年半にわたり、「らでぃっしゅぼーや」の新規顧客向けプロモーションや新サービス立ち上げを担当。その後、社内異動で人事へ。現在は主に新卒(一部中途)採用を担当。
非連続な挑戦を成し遂げ、
社会にイノベーションを起こしたい。
そんな情熱とWillを持って
成長したい方を求めています。
2000年6月、10数名の20代独身男性が「このチームで本気で世界を変えたい、社会をよくしたい」という想いで、安心安全な食品をインターネットで販売する「オイシックス」を創業した。以来、「食の社会課題をビジネスの手法で解決する」ことで事業拡大をしながら、持続可能な社会の実現に挑戦し続けている。オイシックス・ラ・大地株式会社では、どのような人材観を持って採用・人材育成を行っているのだろうか。HR本部人材企画室・人材スカウトセクションの竜沢華林氏にうかがった。
食の社会課題解決を標榜
──最初にオイシックス・ラ・大地をご紹介いただけますか。
竜沢 当社は「これからの食卓、これからの畑」を企業理念に掲げ、食に関する社会課題をビジネスの手法で解決することにより、持続可能な社会の実現を目指す企業です。主力の食品宅配事業「Oisix」「らでぃっしゅぼーや」「大地を守る会」をはじめ、米国でプラントベースのミールキット宅配を行う「Purple Carrot」、買い物難民の方々を支援する移動スーパー「とくし丸」など、多角的な事業を手掛けています。
近年ではBtoB事業にも注力しており、同じく社会課題解決を志向する企業とのM&Aを通じて、事業領域の拡大を加速させています。
20代をメインに採用
──オイシックス・ラ・大地の「求める人物像」とはどのような人材ですか。
竜沢 当社が求める人物像の根幹には、「非連続な成長への意欲」があります。メンバーの一人ひとりが自身の強みを最大限に発揮し、成長を続けることこそが、社会課題解決の原動力になると考えているからです。
この成長意欲を体現するための行動規範として、当社は7つの項目からなる『ORDism(オーディズム)』を定めています。この『ORDism』を深く理解し実践する姿勢、そして、それを支える論理的思考力と実行力を兼ね備えた方を、私たちは求めています。
▼7つの行動規範『ORDism』
1.ベストを尽くすな、Missionを成し遂げろ
2.早いもの勝ち、速いもの価値
3.お客様を裏切れ
4.サッカーチームのように
5.当事者意識、当事者行動
6.強さの源泉は成長力
7.前例はない。だからやる
──オイシックス・ラ・大地の採用方針について教えていただけますか。
竜沢 採用は新卒とキャリアの両軸で展開しています。当社の採用の特徴は、年間のキャリア採用90〜100名のうち、約半数が第二新卒を含む20代である点です。新卒採用の10名前後と合わせ、若手層の採用に力を入れています。ここでは即戦力としてだけでなく、将来の事業を牽引しうる、ポテンシャルの高いリーダー候補を広く求めています。

新卒は細かく丁寧な対応に配慮
──新卒採用の選考フローとミスマッチを防ぐための配慮についてお聞かせください。
竜沢 選考は書類選考と2回のオンライン面接、1回の対面面接が基本フローです。採用人数が10名前後と少数であるため、画一的な選考に留まらず、候補者一人ひとりに合わせたアプローチを重視しています。例えば、先輩社員との座談会や商品体験会などを個別に設定し、入社後のキャリアイメージを具体化できるようサポートしています。
これは入社後のミスマッチを最小化する目的はもちろん、候補者自身が当社で最大限に成長できるかを判断するための重要なプロセスと位置づけています。過去には、「生産者が報われる社会を作りたい」という学生に対し、農産部門と販売部門の社員双方と対話する機会を設け、生産から販売までのバリューチェーンを深く理解した上で、自らのキャリアを構想してもらいました。こうしたパーソナライズされたコミュニケーションを通じて、相互理解を深めることを大切にしています。
──内定式後の内定者フォローはどのように行っていますか。
竜沢 入社後、いち早く活躍していただくために内定者向けの事前研修を計画しています。特に、食の社会課題をビジネスの力を用いて解決するには課題を正しく捉え、解決に導くことのできる「問題解決力」が必要不可欠であるため、事前のロジカルシンキング研修の導入を検討中です。研修とテストを通じて、入社前に問題解決の基礎能力を習得してもらいます。また、スキル面の強化に加え、同期としての連帯感を醸成するための施策を予定しており、入社前の不安を払拭し、スムーズなスタートを支援します。
──入社前にある程度教育の基盤を固めるのですね。
竜沢 これまでは入社後に行っていましたが、入社後の研修は多岐にわたるため、事前に論理的思考の基盤を構築しておくことで、その吸収率が飛躍的に高まると考えて計画をしています。これは、早期の戦力化に不可欠な投資だと捉えています。
1泊2日の入社式でサプライチェーン全体を体感
──2025年4月入社の新入社員研修は、どのように実施しましたか。
竜沢 新入社員研修は、1泊2日の入社式と、そのあとに続く約1ヵ月の研修で構成されています。
入社式は、当社の一員としての自覚と気概を育むことを目的としています。これからサプライチェーン全体を扱う事業に携わる者として、その原点を体感してもらうためのプログラムです。具体的には、生産者の方にご協力いただき、飼料作りや石積みといった様々な農作業を行います。さらに、自ら収穫した野菜を味わうことで、食のありがたみを実感してもらいます。こうした一連の体験を通じて、生産者の想いを一次情報として肌で感じ、その価値をお客様にどう届けていくべきか、深く考える機会としています。
この体験を土台として、続く約1ヵ月の研修では、ビジネスマナーや当社の事業戦略、各種スキルを学んでもらいました。
──5月の配属後、新卒同期が一堂に会する機会はありますか。
竜沢 はい、配属後も同期との繋がりや成長を継続的に支援する体制を整えています。具体的には、企業理念の浸透やミッション達成への意識を再確認するフォローアップ研修を定期的に実施します。並行して、人事担当者による1on1を年間を通じて行い、それぞれの成長をサポートしています。
──新卒の配属後のキャリアパスはどのような流れになりますか。
竜沢 当社では、あらかじめ決まったキャリアパスはありません。個人の成長と活躍を最大化することを目的に、「本人のWill」「本人の強み」「配属環境」、この3つの観点で配属先を決めています。1年目は全員営業部配属といった固定観念がないのが、ひとつの特徴です。1年目から挑戦できる環境に身を置き、裁量を持って働くことができるため、圧倒的なスピードで成長することが可能です。これは当社の大きな特徴のひとつと言えるかと思います。
キャリア入社も食の体感研修を実施
──キャリア採用の選考フローは新卒より短めですか。
竜沢 基本的な選考フローは新卒採用と同一ですが、面接の担当者が異なります。キャリア採用では、HR本部メンバーに加えて、配属予定の事業部メンバーが面接に加わります。HR本部はカルチャーフィットや組織全体とのマッチングを、事業部は専門スキルやチームとのシナジーをそれぞれ見極める、という役割分担になっています。
──キャリア採用でも入社研修を実施していますか。
竜沢 はい、キャリア入社者にも当社の理念やビジネスへの理解を深めていただくための研修プログラムを用意しています。3日間の基礎研修に加え、新卒と同様に生産者の現場を体験する研修や、お客様を深く理解するための研修を実施します。後者では、お客様へのインタビュー映像などを通じて、サービスが提供される「食卓」のリアルな状況をインプットしてもらいます。こうしたインプットは、お客様目線でサービスを作り、提供していくためには必要不可欠であると考えており、全社的に実践しています。また、人事による定期的な1on1やフォローアップ研修も新卒同様に実施します。
個人の成長を支援する評価制度
──社内制度でユニークなものがあればご紹介いただけますか。
竜沢 ユニークなものに、社員一人ひとりの成長支援制度「ORDit」があります。「ORDit」は、「ORD(Oisix ra Daichi) Incubation of Talent」の略で、当社では、個人の成長が会社の成長につながるという考え方のもと、「Will・Skill・Syuraba」という3つの要素を持ったフレームワークを取り入れています。
具体的には、本人の「Will(意志)」を起点に、ミッション達成に必要な「Skill(能力)」を定義し、現時点の実力より一段高い挑戦環境である「Syuraba(修羅場)」を提供することで、非連続な成長を促します。 評価は半期ごとに実施し、年次に関わらず個人の成長と貢献度を絶対評価します。これにより、入社3年目でマネージャーへ、あるいは半年で室長クラスへ昇格する事例も生まれており、成長意欲の高い人材が正当に評価され、活躍できるしくみを構築しています。
──成長意欲をより活かしてもらうための制度なのですね。
竜沢 その通りです。当社のDNAには、創業当時からのベンチャースピリットが色濃く受け継がれています。「食の社会課題をビジネスの手法を用いて解決する」という前例のない挑戦から始まった企業だからこそ、組織が拡大した現在も、現状維持を良しとせず、常に高みを目指す挑戦的なカルチャーが根付いています。

会社側推奨と公募でポジティブな異動が可能
──ジョブローテーション的な制度はありますか。
竜沢 ジョブローテーション自体はありませんが、個人のWill(意志)と成長を起点とした、戦略的な人材配置を積極的に行っています。
私自身を例に挙げますと、もともとは地元に還元できるような事業をしたいというWillが自分の中にありました。そのために、当社で身につけたいスキルは、経営的視点とモノを売る力だったので、最初の2年間は事業部でプロモーションや新サービスの立ち上げを経験させてもらいました。そのあと、「経営部分も見ることができて、事業をやっていく上で大切になる人と出逢う力を身につけるために、人事部で挑戦してみるのはどうか」と打診され、人事部に異動しました。
こうした会社主導の異動提案に加え、社内公募や自発的な異動希望を申請できるジョブポスティング制度も整備されており、キャリアの自律性を尊重したポジティブな異動が活発に行われています。
──自分で挙手して異動もできるし、会社側が本人の成長を見ながら勧めてくれる異動もあるのですね。
竜沢 はい、その両側面があります。私自身、当初は事業へのこだわりを持ち始めていたので、人事への異動を2度断りました。しかし、会社側が私の将来的なキャリアを見据えた上での提案であることを、対話を通じて丁寧に説明してくれたのです。単なる欠員補充ではなく、個人の成長戦略の一環としての異動であると納得できたため、最終的に決断しました。
──福利厚生面で特徴的なものがあればご紹介いただけますか。
竜沢 特に、ライフステージの変化に合わせた働き方の支援に注力しています。例えば、育児休業からの復職者を歓迎する「復職式」を毎年開催し、スムーズな職場復帰をサポートしています。育休取得率は男女ともに100%を達成しており、性別に関わらず家庭と仕事の両立を重視する文化が浸透しています。私の前の上司も3人のお子さんのパパでしたので、リモートワークや時間休を活用し、お子さんの学校行事には基本的にすべて参加していました。 当社のメインターゲットが子育て世代であるからこそ、社員自身がその当事者として働きやすい環境を整備することは、とても重要なことだと考えます。
自主勉強サポート制度で資格取得を支援
──資格取得を支援する制度はありますか。
竜沢 自主勉強サポート制度の一環で、外部研修、資格取得支援、勉強会開催などをサポートしています。当社の成長目標のひとつに「スキル向上」を掲げているので、会社として成長してもらいたいスキルと職種として伸ばしていきたいスキルの両方をより伸ばしていくための資格取得をサポートしています。
チームで勉強会を開催する際には、1回の勉強会参加において1名2,000円の補助が出されるので、費用を講師代に充てることが可能です。
また、ダイバーシティ&インクルージョンの観点から、LGBTQ+に関する研修なども実施しており、スキルセットだけでなくマインドセットのアップデートも重視しています。
──新卒のエントリーシートや履歴書に、学生時代に取得した資格が記載されていた場合、どのように判断しますか。
竜沢 資格の有無が合否に直接影響することはありません。しかし、私たちは新卒採用を未来のリーダー候補の採用と位置づけています。その観点から、資格取得というプロセスを通じて「目標を設定し、達成に向けて主体的に努力できる力」や「非連続な成長を追求する姿勢」を読み取ることはできます。資格は、ご自身の理想像に向かって努力を継続できる根拠のひとつとして、ポジティブに評価しています。
──最後にキャリアアップや資格取得をめざす読者にメッセージをお願いします。
竜沢 一部のポジションを除いて、会社として資格取得を推奨することはありませんが、自己実現のために学び、資格取得を目指す成長意欲の高さを高く評価したいと思いますし、私自身もその姿勢はとてもすばらしいと考えています。
当社が挑む「食の社会課題解決」は、決して平坦な道のりではありません。既存の枠組みでは解決できない難題に直面することも日常です。そうした困難な状況さえも成長の機会と捉え、社会やお客様のために情熱を注げる方にとって、これ以上ないほどワクワクした環境がここにはあります。その高い志と向上心を、ぜひ当社で開花させてください。私たちと共に「これからの食卓、これからの畑」を創造していく仲間をお待ちしています。
[『TACNEWS』人事担当者に聞く「今、欲しい人財」|2025年10月 ]

会社概要
社名 オイシックス・ラ・大地株式会社
設立 2000年3月31日
代表者 代表取締役社長 髙島宏平
本社所在地 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー5F
事業内容
ウェブサイトやカタログによる一般消費者への有機野菜、特別栽培農産物、無添加加工食品等、安全性に配慮した食品・食材の販売や、企業・官公庁・保育園・病院・老人保健施設等の給食などの受託運営や食材卸など
従業員数
2,021名(2025年3月31日時点)
URL