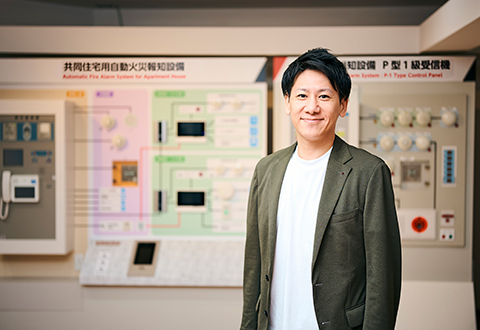人事担当者に聞く「今、欲しい人財」 第80回 MIC株式会社

一重 友理枝(ひとえ ゆりえ)氏
ひとづくり部 部長
2009年、新卒入社。入社以降カスタマーサクセス業務から社内外のインフラの整備や開発に携わる。2度の産休・育休を経て、事業部でのマネジメントや業務改善に従事。2025年よりひとづくり部の部長として、採用、教育、健康経営全般を統括。人的資本経営の実現に向けた人事戦略の立案・遂行を担う。
「ひとづくり」に関わること、
すべてに時間と情熱をかける。
丁寧なコミュニケーションと手厚い教育研修に
自信があります。
MIC株式会社のルーツは、2026年に創業80周年を迎える水上印刷株式会社だ。祖業の印刷を軸に据えながら製造×サービス、デジタル×フィジカル、ひと×テクノロジーによって、「360°フルサービス」を標榜している。「ひとづくり」に関わることに時間と情熱を注いでいるMICでは、オリジナリティ溢れる研修や福利厚生が充実している。ひとづくり部部長の一重友理枝氏に、MICの人材観や採用、教育研修、福利厚生の特徴を語っていただいた。
デジタル×フィジカルで、“企業の未来にイノベーションを起こす”
──最初にMICをご紹介いただけますか。
一重 MICは、祖業の印刷をコアに、販促にまつわるコンサルティングやマーケティング支援、販促物そのものの企画・デザイン、在庫管理、流通加工、物流など、ものづくりを含めたあらゆる周辺領域の業務を自社一貫体制で行い、新たな事業モデルを作ってきました。2022年には「デジタル×フィジカルで、”企業の未来にイノベーションを起こす”」をビジョンとして策定。デジタルとフィジカルの2つを主軸に、お客様の特徴に応じて360°フルサービスを提供する「リテール販促支援」に注力しています。
2024年12月には東証スタンダード市場に上場し、2025年8月8日時点で株価2.86倍と順調に推移してきました。
採用活動から若手メンバーが活躍
──MICの採用方針について教えていただけますか。
一重 新卒採用とキャリア採用の両軸で行い、その時々の事業バランスによって変動させています。提供サービス内容の幅が広い分、新卒社員が360°フルサービスに関わる業務をすべて習得するのには時間がかかるので、並行して、他業界経験者や必要スキルを持った人材をキャリア社員として迎えています。
──2025年4月1日入社の新卒は何名でしたか。
一重 2025年4月は25名が入社しました。すでに研修期間を終え、本配属先の各部署で早速活躍しています。
──キャリア採用は年間何名を計画していますか。
一重 事業成長に合わせて、従業員数を増やす計画で動いています。ちなみに、2025年6月末時点で正社員数は333名です。
──求める人物像とはどのような人材ですか。
一重 新卒採用、キャリア採用に共通するのは、「顧客第一主義、挑戦、改善、学習、One MIC」という私たちの5つのバリューに共感し、体現してきた経験のある方です。
──選考の中でオリジナルな取り組みがあれば教えてください。
一重 カルチャーマッチを重視した採用を行っており、とても丁寧にコミュニケーションを取っています。新卒採用に関しては、採用プロセスの中で先輩社員との交流会を複数回設けており、内定後も定期的に交流会やイベントに招待しています。
新卒社員からは「選考期間中にこれほど多くの社員と会う機会を設けている会社はない」と評価されています。言葉通り、実際に10人以上の社員に会い、働くイメージを具体化し、納得感を覚えて入社を決めた学生もいます。
また、MICは「全員採用」を掲げていて、若手メンバーにも積極的に採用へ参加してもらいます。学生にとっては、自分と年齢が近い先輩社員と直接話すことで、MICをより具体的かつ多面的に理解でき、入社後のギャップを防ぐことにもつながると考えています。
──面接にも若手メンバーに入ってもらうのですか。
一重 どちらかというとパネルディスカッション等々、コミュニケーションの場で先輩社員に入ってもらうことが多いですね。面接は部門や組織のマネージャーが主体ですが、場合によっては若手メンバーに入ってもらうこともあります。
──面接の回数も多いですか。
一重 本人の納得感を大事にしており、人によって個人差はあります。「どのような人と働くのか」ということも重視しているので、社員と会う機会を多く持つのが当社の特徴です。

ミスマッチを防ぐための丁寧なコミュニケーション
──10月1日の内定式から入社までの間、内定者フォローは行いますか。
一重 内定者フォローとして、月1回程度内定者とお会いする機会を設けています。入社前からしっかりコミュニケーションを取って、同期同士、あるいは会社との絆を深めてもらうことが大切だと考えています。ワークショップも行っており、2025年新卒の内定者は会社紹介のパンフレットづくりをゼロから行いました。自分たちでコンセプトを決め、先輩社員にインタビュー、録音・撮影をして、レイアウトも自分たちですべて行い、1冊の冊子に仕上げました。ワークショップはトレンドを採り入れるので、年によって内容は変わります。
──キャリア採用に関しては、必要に応じて必要なスキルセットを持った人材を採用するイメージですか。
一重 そうですね。やはり、事業拡大や成長のための注力分野で必要なスキルをお持ちの方、その分野の経験者を都度採用しています。新卒採用と同様、キャリア採用でも選考プロセスにおいてミスマッチがないか丁寧に会話し選考していきます。ですが、候補者の方のご希望に合わせて、スピーディに選考を進めていくこともあります。
座学からものづくりまで、幅広い新入社員研修
──2025年4月の新入社員研修はどのように実施されましたか。
一重 4月から6月までの3ヵ月間実施しました。毎年の事業状況やカリキュラムのチューンナップによって、半年や丸1年など、研修の期間に差があります。
──具体的にどのような内容ですか。
一重 私たちのフルサービスには、コンサルティング、システム開発、BPO、クリエイティブ、ものづくり(印刷・製造)、フルフィルメント、フィールドサポートがあります。最初の1ヵ月は社会人マナーやビジネススキル、各サービス分野の内容を理解してもらいます。
そのあとは、各部署の業務内容の理解を深めるための座学に入ります。並行して生産本部の印刷工場やフルフィルメントセンターで実際に生産ラインに入り、そこで働いているアルバイト社員や製造スタッフの横に並んで、ものづくりを学びます。
「スライドライティング」というユニークな研修も実施しています。PowerPointを使い、自分の仕事に関するアウトプットや顧客提案資料作成をしっかり行えるようになるための研修です。
事業部(営業職)の方には、祖業も含めた各サービスについて深く理解してもらいます。まず、カスタマーサクセス部でものづくり(印刷・製造)や、制作部門でのディレクションを経験します。社内でどのようなものを作っているのか、指示はどう出すのか。実際にディレクションを体験し、半日かけて仕事の流れを把握していきます。残り半日はお客様に提出する見積書を作成する「寺子屋道場」という研修を約2ヵ月間実施します。研修期間中で営業の基盤となるスキルと知識を、実践を交えながら身につけていきます。
──配属後も同期が一堂に会して研修を受ける機会はありますか。
一重 配属後3ヵ月間、毎週集合型の定例報告会を対面で実施します。そこでメンバーが毎週自身の業務に対して棚卸しをして、課題抽出、それに対する対応策をアウトプットする数分のプレゼンテーションを行います。参加者はその年に入社した事業サイドの新卒社員とその上長や部門の先輩たちで、参加者全員の前で新卒社員がプレゼンテーションをして、フィードバックをもらいます。
そこでは、業務理解はどれぐらいできているのか、スライドライティングなどの研修の成果は出ているのか、といったことを確認していきます。最終報告会は9月末から10月初頭で、このときは会長・社長をはじめとした経営陣も加わって各部門長のフィードバックコメントや今回の新入社員の研修結果を見届けます。それが終わると3ヵ月間やってきた研修に対しての振り返りアンケートを取り、次の研修にフィードバックするというサイクルで進めています。
このように新入社員研修には3ヵ月から半年、1年かけ、それ以降は階層別研修のカリキュラムに進みます。
──新入社員を手厚く育てていくのですね。
一重 「ヒト・モノ・カネ」のうち、「人」だけが唯一成長することができるからです。「ひとづくり」に関わることすべてに時間と情熱をかけるMICだからこその教育研修です。

学習は未来への投資
──社内の研修制度で特徴的なものがあればご紹介ください。
一重 なにしろ就業時間の10%である200時間を教育研修に充てることを目標にしているのが当社の特徴です。先ほどのスライドライティングや寺子屋道場も含め、MICオリジナルの研修をたくさん用意しています。
「寺子屋道場」は、サービスの概要や実態について座学だけでなく、現地現物で学ぶものです。印刷物と周辺の製造品、フルフィルメント、物流加工等々あらゆるサービスにおいて、お客様に提出する見積りを作るところが一番のサービス理解につながるため、営業職およびその周辺職種向けにこの研修を実施しています。
それだけでなく、業務理解を促すためのフルサービス研修を、新卒社員全員にまとめて行っています。同じ研修を四半期に一度、定期的に行っていて、キャリア採用社員が入社時に受けるのもこの研修です。
もうひとつ特徴的なのが、メンター制度です。メンター制度を設けている企業は多いと思いますが、当社では入社後必ず他部署の先輩社員がメンターとなって、業務以外の内容も含めメンター面談を実施しています。メンター制度は入社後約1年間で、新卒だけでなくキャリア入社にも設定しています。
メンター面談以外にもファーストミーティングと呼ばれる面談があります。これは新入社員なら部署配属時、既存の社員であれば人事異動が発令されて、新しい上長のレポートラインについたときに、新しい上長と部下で行う面談です。本人と上長がお互いを知るだけでなく、新しい部署に配属になった際の不安の解消を行った上で、業務上の課題などを上司が把握することを目的としている面談で、これもユニークな取り組みだと思っています。
社内外の知見の共有を目的とする「MICフォーラム」という集合型の研修も用意しています。これまで上場企業経営者などを社外から講師に招き、学びのシェアをしてきました。

健康で働きがいのある職場作りへの取り組み
──福利厚生についてはいかがですか。
一重 福利厚生面でも、健康経営を掲げ充実した制度を整えています。
時短制度では、お子さんのいる社員だけでなく、介護が必要な方など様々な社員の方が利用することが可能です。原則、残業なしの定時退社の勤務から7時間勤務、6時間勤務とバリエーションを持たせています。ママ社員の産休育休はもちろんのこと、パパ育休の取得も進んでいます。ママ社員の育休復帰率が100%なのは、そういった手厚い福利厚生が利いていると考えています。
また「360°フルサービスカンパニー」ということで、挑戦、改善、学習のために研鑽を積む機会が多い当社では、社員の健康を主軸として積極的に健康経営を推進しています。
その中から生まれた制度として、週1回のテレワーク制度、有給とは別に特別付与される年間5日間のセルフケア休暇があります。健康診断、人間ドックの一部費用負担も、社員の健康増進を後押ししています。直近では、ひとづくり部に保健師2名を配置し、全社員面談を実施していて、社員から好評です。出産後のお祝い金や復帰ママサポート手当、住宅購入お祝い金も支給しています。
社員のご家族を招待するイベントも多数実施しています。バーベキューや大型の子ども用プールでの水遊び、芋掘りや蛍鑑賞なども行っています。今年7月にはファミリーサークルという、あきる野フルフィルメントセンター「るのパレット」にヤギを連れてきて、草刈りの代わりに生い茂った草を食べてもらうというユニークなイベントを開催しました。
変わったところではSDGsの取り組みの一環として、自社拠点で養蜂をしていて、採れた蜂蜜を社員とお客様のお土産としてプレゼントしています。普段社員を支えてくださっているご家族に感謝を伝えるために、家族をご招待する任意参加のイベントは毎年1回は実施しています。
もうひとつ社員に大変好評なのが、本社1階の「Bar Five O'clock」です。定時を過ぎたらバーをフリーで使えるもので、物価上昇の折、気軽に社内のラウンジで飲めて、部門横断的にネットワークが広がっています。歓送迎会やお客様との打ち合わせ後の懇親会などにも利用できます。
社員が生き生きと明るく元気に働ける環境に対して投資は惜しまない。それが会長や社長の思いです。

No Try, No Success!
──資格取得に対する支援制度はありますか。
一重 MICのバリューのひとつに「学習」があるように、各職種で業務上必要な資格取得、外部を含む研修全般について、会社で全額費用負担しています。また、MICを支える上級管理職や拠点長などにはMBA取得を推奨しています。全額会社負担で、現在4名のMBAホルダーがMICを牽引する役員として活躍しています。
資格取得については、システム関連の情報処理系資格はもちろん、印刷系、製造部門系資格、外国籍の社員に対する日本語検定受験も支援しています。
──新卒の応募者が履歴書に学生時代に取得した資格を記載していた場合、どのように判断されますか。
一重 一定の難易度やレベル感によって、資格は目に留まります。ただし、その資格を持っていることよりも、なぜその資格を取得しようと思ったのか、どのぐらいの期間でどのように勉強して、どういった努力をしたのかを聞きながらお人柄を見たいと考えています。
──最後に資格取得やキャリアアップをめざす読者にメッセージをお願いします。
一重 「No Try, No Success!」この言葉をお伝えしたいと思います。MICが創業の水上印刷株式会社であったときから、現会長が発信し続けてきた言葉です。挑戦なくして成功なし。どんなにハードルを高く感じたとしても、そこにトライしていっていただきたいと思います。
[『TACNEWS』人事担当者に聞く「今、欲しい人財」|2025年9月 ]

▲本社
会社概要
社名 MIC株式会社
創業 1946年7月1日
代表 代表取締役会長 水上光啓
代表取締役社長 河合克也
本社所在地 東京都新宿区西新宿5-14-3
事業内容
リテール販促支援/コンサルティング、システム開発、BPO、ものづくり(印刷・製造)、フルフィルメント、フィールドサポート
正社員数
333名(2025年6月末時点)
URL