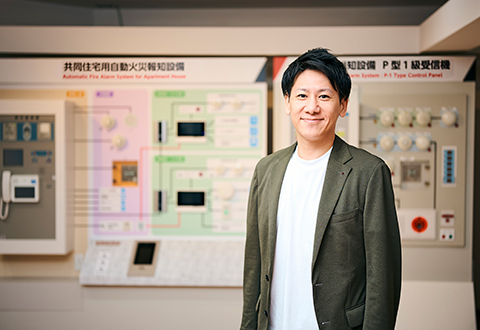日本のプロフェッショナル 日本の会計人

谷 侑治(たに ゆうじ)氏
谷侑治会計事務所 代表 公認会計士・税理士
1991年、福井県生まれ。2014年、金沢大学人間社会学域経済学類卒。卒業後、東証プライム上場企業入社。2017年同社を退社。2017年4月、EY新日本有限責任監査法人入所。2019年、公認会計士試験合格。2021年、EY新日本有限責任監査法人退社。同年、税理士法人入所。2023年2月、東京都品川区五反田に谷侑治会計事務所を開設。
成功体験が挑戦を後押しする、
公認会計士試験合格で得た揺るがぬ自信。
公認会計士・税理士として、31歳の若さで独立開業した谷侑治氏。YouTuber、インフルエンサーをはじめ、個人起業家、スタートアップ企業支援や医療機関へのコンサルティングなどをメインに奔走している。開業3年目の2025年は顧問数200件を目標に掲げ、AI活用による業務効率化を推進している。谷氏はどのような経緯で公認会計士をめざし、独立開業したのか。そして、現在抱えている課題と今後の展望についてうかがった。
将来のCEO、CFOをめざし公認会計士受験スタート
小学生のとき、中学校3年の数学の学習を修了したことで学習塾の全国紙に掲載された公認会計士・税理士の谷侑治氏。数学が好きだったことが、将来の強みになる「国家資格を取得すること」につながり、数学を活かせる資格として医師を考えた。
「ところが医学部は苦手な物理を避けて通れません。他に何か国家資格はないか。見つけたのが公認会計士(以下、会計士)と税理士でした」
金沢大学3年生の夏から1ヵ月で日商簿記3級、3ヵ月で日商簿記2級に合格。そのあと、国税専門官になれば勤続年数によって税理士資格を取得できることがわかり、半年間、公務員試験をめざした。ところがベンチャー企業で颯爽と働くエリートたちがまぶしく映り、まずは一般企業への入社を決意。専門商社に入社し、財務部の配属となった。財務部では日々の資金繰り、会計処理、連結決算、子会社決算、税務業務などに対応し、経理から会計税務まで幅広い実務を経験した。実務を覚えると「経営者とともに成長したい」「自分が経営者になりたい」という思いが強くなっていった。
「CEO、CFOになるなら会計士・税理士資格を取得したほうがステップアップできる。税理士業も可能な会計士試験にチャレンジしよう」
社会人2年目の誕生日、谷氏はTAC金沢校で会計士受験をスタートした。

監査実務と会計士受験の両輪
受験勉強を始めてから、会計監査の実務を身につけるべく4大監査法人の一角、EY新日本有限責任監査法人に転職。実務と並行して会計士受験が可能な監査トレーニー制度の第2期募集のタイミングだった。
「挑戦するならこのタイミングしかない。財務部としての4年目の目標も決まっていましたが、会計士試験に合格したいという思いが強すぎて、何も考えずに勢いで応募しました」
2017年4月、監査トレーニーとしての採用が決まり、東京で社会人受験生としての生活がスタートした。通常は週5日勤務だが、谷氏は週4日勤務で勉強時間の確保を優先した。朝5時過ぎに家を出て、始発電車でカフェや自習室に向かい、始業時間まで勉強。ランチタイムは自分で詰めた弁当を食べながら往査先の会議室で勉強した。17時半に退社し、TACやカフェで勉強してから帰宅。移動中も「この科目は移動中だけ勉強する」と決めた監査論のテキストを開き、とにかく効率重視で勉強を進めた。
2019年、谷氏は2回目の論文式試験に合格し、晴れて会計士試験を突破した。その後の修了考査も1年で突破し、2021年に目標であった会計士になった。
自分が求めている生活を得るために独立開業
監査法人では約4年間、主に東証プライム上場企業の会計監査、内部統制監査、IPO業務をメインに監査実務を学んだ。修了考査後、会計士・税理士としてさらなる成長をめざして税理士法人に転職。
「税理士法人への転職は、将来の独立を視野に入れていたためです。転職先の代表は若くして会計士・税理士として独立した方なので、どのように独立するのか、自分にとって理想のロールモデルでした」
監査法人で上位ポジションをめざす。税理士法人で自身のポジションをまっとうする。あるいは代表パートナーになる。さまざまな道を選ぶことができる。しかし、独立すれば収入と自由な時間、あらゆる意味で自分が求めている生活を手に入れられる。
2023年2月1日。谷氏は税理士法人を退所。品川区五反田で谷侑治会計事務所の看板を掲げた。
YouTuber、SNS発信者から広がったネットワーク
ゼロスタートの谷氏は、開業後、まずは士業交流会に参加。そこで知り合った社会保険労務士や司法書士などから顧問先を紹介してもらった。営業活動を行う中で、偶然にも谷氏が注目していた登録者数十万人のYouTuberが、SNSで税理士を探していると発信していた。即座にDMを送った結果、その法人の顧問税理士になった。
「彼のYouTubeへの出演やSNSでの紹介をきっかけに、お客様からの問い合わせが増え、営業活動以外でも集客ができるようになりました」
そこから登録者数が数百万人のYouTuber、インフルエンサーへの横展開が広がり、谷氏の事務所は自然とインフルエンサー、SNS発信者の税務顧問先が増えていった。

若手税理士として同年代のスタートアップ企業を支援
「税理士は平均年齢60代といわれる業界。開業税理士で私のような30代は1割程度しかいないこともあって、年齢が近い経営者、個人事業主が大勢お客様になってくれました。その方たちが事業を軌道に乗せて法人化する。こうしたスタートアップ企業や個人起業家の支援が、強みとなっていきました」
新型コロナウイルスの影響もあり、在宅勤務、副業、業務委託と働き方の自由度が増す中で、今後もニーズは増えていくと、谷氏は話す。
「例えば、業務委託者100人を抱える会社の税務顧問を受ければ、業務委託者の確定申告をまるまる依頼される可能性が予想できる。そういう仮説のもとで、個人事業主や副業者を抱える会社にアプローチしていきました」
業務委託者を多く抱える会社、あるいは個人事業主向けにサービス展開する会社を敢えて顧問先に選び、その先にいるお客様まで見越した営業アプローチをかける。こうして谷氏のひとつのスタイルが確立し、開業1年目に60件だった顧問数は、2年目の途中には100件を超えるようになった。
スタッフ増ではなく効率化で業務拡大
開業時に谷氏が掲げたビジョンは「みんなで楽しく働ける事務所」。税理士法人時代にチームで働く楽しさを経験したことがその背景にあった。
開業1年目、五反田でスタートした事務所は、ほどなく税理士をめざすパートナー(3科目合格、現在大学院在学中)を迎えてすぐに2人体制となった。1年目が終わるころには確定申告期の業務量が増え、さらにアルバイトスタッフを1人採用。2年目に4人目、3年目にもう1人を採用し、谷氏を含め6人体制となり、事務所も港区三田に移転。
パートナーが大学院を修了し、税理士資格を取得したあとは、税理士法人化も視野に入れる。さらに、今後はスタッフを増やすことより、業務の効率化に力を入れていくという。
「AI活用で業務効率化を進めていき、どこまで顧問数を増やせるか。3年目は200件が目標です」

課題は今後の展開戦略
事務所の特徴となっているYouTuberやインフルエンサーからの集客や紹介の他に、自らが発信するYouTubeチャンネルとTikTokからの問い合わせもある。といっても全体の約2割程度で、顧問先の約8割は一般事業会社が占めている。提供している業務内容は確定申告、税務顧問、補助金サポート、節税対策、コンサルティングといった税務会計のトータルサポートである点は、どちらも変わらない。
開業3年目、谷氏は思い通りに事務所を運営できてきたのだろうか。
「社会人になりたてのころ、あるいは会計士資格を取得した時点では、独立はもっと難しいだろうと思っていました。独立してみると紹介から紹介でつながり、すてきなお客様に巡り会えて、事務所が回っていき、人も雇えました。やっていくうちに徐々に成功体験が積み上がっていったので、振り返ると、大変だった、苦しかったというよりも、意外と順調だったと感じています。
逆に、ここから先どのように伸ばしていくのか。拡大路線でいくのか。安定だけを考えるのか。新たな事業を展開するのか。いろいろ選択肢が増えてきて、今のほうが難しいですね」
オンラインも含めて、顧客対応はすべて谷氏が担当している。関東圏の顧客には必要に応じて訪問し、全国の顧客とは定期的にオンラインで税務相談や打ち合わせを行なっている。
「私ひとりでかなりの数の顧客対応をしています。規模が大きくなって顧客数が増えてくると、一部の業務はスタッフに任せなければなりません。そうなれば法人化して、主査やインチャージと呼ばれるポジションの税理士もしくはスタッフを増やしていかなければ、業務が回らなくなります。今後、どのように方向転換するのか、このまま現状維持でいくのかが、一番の悩みどころですね」
3年間離職率ゼロの事務所
新たなフェーズを迎えているものの、5年先についてはまだ見通しが立っていないと、谷氏は率直に話す。
「10人、20人と採用して規模拡大していく楽しさ、仲間が増えていく楽しさもねらいにいきたい。ただ、税理士業界は『人』がもっとも重要なビジネスです。そう簡単にいい人がジョインしてくれるかはわかりません。採用難でもありますし、3年程度でやめてしまう人が多い、転職するタイミングが早い業界でもあります。
私が発信しているYouTubeやTikTokを通じて、私の人柄や事務所の雰囲気を理解してくれた方から連絡がくるのが理想です。そうした方となら意思の疎通を図れて、一緒の組織でやっていけるのではないか。そのようなイメージで少しずつ人が増えていけばいいなと考えています」
特筆すべきは、3年目を迎えたばかりにも関わらず、谷氏の事務所ではこれまで誰もやめたスタッフがいないという点だ。
「任せるべきところは任せて、あまり口うるさく言わない。そこは徹底しています」と、その秘訣を明かす。実務はスタッフに任せ、締めるところは締めて、任せるところは自由にやってもらう。役割分担をきちんとすることで、谷氏は代表としての仕事に注力できる。それによって、組織がうまく機能しているようだ。
「お客様の気持ちを理解して、うまくコミュニケーションをとれるか。お客様の悩みに気遣いができるかどうか。そこが一番大事ですね。スキルが足りなければ、私やパートナーがフォローできるので何とでもなります。まずは人柄を重視しつつ、うちの環境と価値観に合うかを見極めています」
運営上、人材面で苦労したことがない事務所はほとんどない。その意味で谷氏の事務所の最大の魅力は、離職率ゼロという働きやすい環境にあると言えるだろう。

独立するなら税務実務を経験しよう
谷氏は監査法人を経験したあと、税理士法人を挟んで独立開業している。税務実務を経験せずに、いきなり監査法人から独立するのは不安が大きいと考えたためだ。
「監査法人では仕訳を切らないし、申告書も作りません。どのような税務申告ソフトを使っているのか、給与計算の仕方も知らない状態です。なにより申告期を山場とした1年の仕事の流れがわかりません。しかも、税務手続きや届け出には期限があり、リスクと責任がともなう。そう考えたとき2年間、税務を学べたことは大きなメリットです。独立する前提であれば、期限を決めて実務を経験することをお勧めします」
会計士になってもっともよかった点を聞いてみた。
「自分の中で満足できる成功体験を味わえたことです。金沢大学に進学しましたが、実は第一志望ではなく、自分の中では小さな挫折が何個かあって。自分が満足する結果が出せていないという思いがありました」
だからこそ会計士を取得できれば自分の人生に満足できるのではないかという思いが強かったという。ところが、余裕だろうと思って始めた受験勉強は、なかなか点数は取れず、勉強量はとてつもなく多かった。
「葛藤はありましたが、新卒で入った会社には受かると宣言して辞めているので、必ず合格するという使命感に燃えていました。自分の挫折と満足しきれていない部分を払拭し、自分に自信をつける。会計士資格を取得できたから、今何をやってもこわくないと断言できます。
たとえ今すべてを失ってゼロから再スタートするとしても、すぐに今の事務所と同じレベルまで持っていける自信はあります。会計士を取得したという成功体験がベースにあるからこそ、私は何も恐れることなく挑戦できるのです」
会計士をめざす後輩には「資格を取得したら自信を持つこと」を勧める。
「仕事上一番大事なのは、どのような人と一緒に仕事をしていくかです。そこさえしっかりしていれば、結果はおのずとついてきます。会計士試験に合格した能力と努力という才能があれば、自信を持って臨んでよいと思います」
一方で、資格試験はすべてやり切る必要はないと谷氏は語る。
「もし始めてみて自分には合わないな、違うなと思ったら、やめてもいいと思います。実際、私は証券アナリストと中小企業診断士の試験は、手を出してすぐにやめました。やったから気づくこともあるので、勉強を始めたいならとりあえずやってみる。それから軌道修正してもいいんです」
最後に、社会人受験生だった自身を振り返り、受験生へのアドバイスをくれた。
「働きながらだと、満遍なくやっても受からないと考えました。できない科目、出る可能性が低い科目は全部切り捨てました。合格できたのは、働きながらのゴールを設定できたのがよかったと思います。自分なりの方法を見つけて、ゴールを設定し、しっかりと最後までやり切ってください。応援しています」
[『TACNEWS』日本のプロフェッショナル|2025年10月 ]