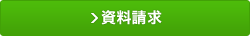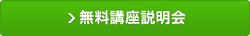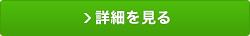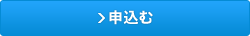よくあるご質問 - FAQ
外務省専門職試験に向けての疑問・不安の解消にお役立てください!
外務省専門職を目指すにあたり、様々な疑問を抱えていることと思います。ここでは、受験をご検討中の皆様から多く寄せられるご質問への回答をまとめております。TACは、皆様の疑問・不安にトコトンお答えいたします!疑問・不安を解消して、ぜひ気持ちよく外務省専門職試験に向けた学習をスタートしてください!
公務員 外交官〈外務専門職〉デジタルパンフレットを閲覧する
入省・勤務に関するご質問
- 外務省ってどんなところ?外交官になるためにはどうすればよいのですか?
- 一口で言えば日本の対外関係の処理を行う役所ですが、その扱う内容は幅広く、外交政策の企画立案および実施から、移住の斡旋に至るまで様々です。
霞が関にある外務省本省が日本外交の司令塔であり、世界200ヶ所以上に置かれた在外公館は外交の最前線で日々様々な交渉を行っています。
日本の平和と安全の確保と、国際社会への貢献、この二つの大きな目的のために本省と在外公館をあわせて約6,000名の人たちが働いています。
外交官(外務省の職員)になるための試験には国家総合職試験と外務省専門職試験が存在します。国家総合職は将来の幹部候補、いわゆるキャリア組で、採用後は様々な部署や国を経験します。
外務省専門職試験は合格後に言い渡される専門とする語学(研修言語)のみならず、当該言語と関連する国・地域の社会、文化、歴史等にも通じた専門家、あるいは経済、条約等の分野の専門家として活躍することが求められます。 - 外交官の魅力って何ですか?
- 外交官とは日本を代表して海外を飛びまわり、外国と様々な交渉を進めていく職業です。グローバル化が進展する現代社会において、その役割はさらに増大していくと考えられます。安全保障や経済外交がイメージしやすいかもしれませんが、在外邦人保護や日本の魅力を海外に発信する広報文化外交なども外交官が担う重要な役割の一つです。
外交官個々の人脈や能力を駆使して、日本のみならず世界中の人々のために働けるのも外交官の魅力です。たとえば、「命のビザ」で有名な杉原千畝氏も外交官であり、多くのユダヤ人の命を救いました。彼の功績は現代においてもリトアニアと日本をつなぐ架け橋となっています。
また、研修制度も非常に充実しています。入省後1年の本省勤務・研修を終えた後、通常2年間留学することになります。例外としてアラビア語などの日本人に馴染みのない言語については、3年間留学することになります。この間に語学学校に通ったり、大学院に進んだりすることで、外交官として働く上で必要なレベルの語学力を身に付けます。語学と地域のエキスパートを育てるためのこの研修制度も外交官の魅力の一つです。 - 入省後の留学・派遣国について教えてください。
- 入省後1年の勤務を終えた後(1年間は本省で仕事および研修をする)、通常2年間留学することになります。ただ例外としてアラビア語など、日本人に馴染みのない言語については、3年間留学することになります。
国費で留学させてもらうため、留学先での成績は全て本省に送られ、1ヵ月に1度は語学のテストがあるそうです。成績が芳しくない場合、その後の出世に響いてくるという噂もあります。
研修言語については、1次試験合格後、2次試験前に提出する「面接カード」の中に希望研修言語を記入する欄があり、第5希望まで記入します(なぜその言語を希望するのかという理由も書きます)。
そして本人の希望も考慮したうえで外務省が研修言語を決定し、派遣先を決定することになります。ただ、必ずしも第5希望までの言語が割り振られるとはいえず、それ以外の全く予期せぬ言語を任されることもありますが、それは運命として受け止めるしかないでしょう。 - 受験言語はそのまま研修言語になるのですか?
- 必ずしも受験言語がそのまま研修言語になるとはかぎりません。外務省が必要としている言語のスペシャリストはその年によって異なります。研修言語は受験生の希望や資質と外務省のその時々のニーズとを勘案して総合的に決定されます。
- 大学で全く履修していない言語を志望言語とすることはできますか?
- 英語で受験していても入省後の希望言語を他の言語にすることも、もちろん可能です。合格者の約8割が英語で受験をしていますが、研修言語は様々な言語に割り振られています。そのため、研修言語が初めて学ぶ言語となることは珍しくありません。大事なのは「なぜその言語を担当したいのか」という志望理由です。
- 出産・子育てについて不安を持っているのですが。
- 外務省は女性も男性も同等に活躍できる職場であることから、入省を希望する女性には出産・子育てについて不安抱く方も多いようです。実際、外務省の説明会等でもそういった質問が多くなされます。しかし、外務省では女性が安心して出産・子育てが行えるよう制度が整っており、出産・子育てにより女性が仕事上で不利に立たされることがないよう保障されています。
試験制度に関するご質問
- 本試験のスケジュールは?
- 1次試験は、1日目に専門科目(国際法、選択科目(憲法/経済学)を各科目3問中2問選択、1科目2時間)の記述試験、時事論文試験(記述式・1時間30分)、2日目に基礎能力試験(選択式・1時間50分)、外国語試験(記述式・2時間)があります。両日とも大体9時半頃~行われます。
2次試験は、グループ討議(受験生8~10人で20分程度討論)、外国語面接(2対1で15分程度)、個別面接(5~6対1で10~20分)、身体検査、性格検査があります。受験生によって試験日程が異なります。 - 競争率が高いようなので受験しようかどうか迷っているのですが。
- 外務省専門職試験は国家公務員試験の中でも難関と言われている試験であり、試験内容についての情報が少ないため、多くの受験者が同じような悩みを抱えています。しかしながら、年々倍率は低下傾向となっているため、競争率を理由に諦める必要はありません。例えば、2024年度の試験では、受験申込者数は256人でしたが、実際に1次試験を受験した人の数は174人です。そのうち、100人が2次試験に進み、61人が最終合格しました。つまり、実質的な倍率は2.9倍であり、他の公務員試験と比較してもさほど倍率が高いわけではないといえます。
受験者数は減少する一方、外務省専門職の必要性は増しつつあり、今後も採用人数は強気の傾向が続いていくと思われます。見た目の競争率に惑わされず、まずは試験についての情報を集めたり、外交について自分はどう思うかを考えてみたりすることが大切です。 - 外務省専門職試験では、性別や年齢などによって有利不利はありますか?学歴フィルターはありますか?
- 基本的に有利不利はありません。2024年度の合格者は男性24名、女性37名となっており、性別による差はみられません。
次に年齢に関してですが、受験資格を充たしていれば、20代後半であっても十分に合格可能です。実際、外務省は毎年幅広い年齢層から採用しています。また、職歴のある方は、社会人経験をアピールすることができます。仮に年齢にコンプレックスを感じるのであれば、悩むよりもまずは他の受験生以上の学力・付加価値を身に付けることが建設的だといえます。
最後に学歴に関してですが、採用の際に出身大学や学部で有利・不利に働くことはありません。確かに法・経済学部出身者は、専門科目において一通り基本事項を習得している点で、初学者よりも一歩リードしているといえます。しかし、TAC・Wセミナーの受講生の多くが、法律や経済を初めて学習される方ばかりです。カリキュラムを地道に消化することによって、十分合格レベルに達することが可能です。むしろ、面接では自身の専門分野をうまくアピールすることによって、法・経済学部出身者より高い評価を得られる可能性もあります。 - 出身大学は採用に影響するのでしょうか?
- 出身大学が合否に影響することはありません。毎年の合格者をみても、国内の国公立大学や私立大学はもちろん、海外の大学を卒業した方もいらっしゃり、学部や専攻も様々です。また、近年「面接カード」では出身大学名を記入する欄はなくなっています。
大学名よりも、「どうして自分は外交官になりたいのか」「外交官として何をしていきたいのか」という明確なビジョンをしっかりと持つことが大切です。外務省はみなさんが気にしているほど大学のブランドにはこだわっておらず、優秀で、熱意のある人物を広く求めているようです。 - 大学院生は不利ですか。
- 大学院生だから不利ということはありません。実際、毎年多くの大学院生が合格しています。1次試験に関してはあくまでも成績勝負ですから、大学院生であろうとなかろうと気にする必要はありません。2次試験においては専門知識をアピールすることで、むしろ学部生より優位に立てる可能性も十分にあります。
- 留学経験がないと不利になりますか?
- 確かに、外務省専門職試験の受験生には留学経験のある方が多いです。しかし、「留学をした」という事実よりも、「留学で何を得たのか」がはるかに重要です。ですので、留学経験の有無が合否に直接作用することはありません。実際、留学はおろか一度も海外経験のない方でも合格しています。しっかり勉強し、まずは1次試験での上位合格を目指しましょう。
- 帰国子女の方が有利になるのでは?
- そのようなことはありません。合格者の大半が国内大学出身です。外務省専門職試験は1100点満点で評価されます。1次試験の国際法、憲法/経済学、基礎能力、時事論文、外国語試験のすべてが同じ配点となっています。たしかに帰国子女の方は外国語試験で高得点を取ることができるかもしれませんが、合否を分けるのは総合力です。バランスよく全ての科目で平均以上の点数を獲得できるように勉強しなければ、いくら外国語ができても合格できません。
むしろこの試験で大切なのは、日本語の能力です。合格レベルの論文を仕上げるためには十分な訓練が必要となります。日本を代表する外交官として恥ずかしくない日本語表現力を身に付けることが大切です。 - 大学の成績が悪いのですが、大丈夫でしょうか?
- 大学の成績が合否に響くことはありません。
- 併願先は少ないと聞きましたが、どんなところがありますか?
- 併願先は少なくありません。最も人気の併願先は防衛省専門職です。その他、国家総合職政治国際人文区分(コースA)や国立大学法人、国立国会図書館、教養型やSPI型の地方上級試験なども併願先としておすすめです。まずは受験科目、試験日程について情報を集めるとよいでしょう。ホームルームや各種併願対策講座を活用することもオススメです。勉強時間に余裕があれば民間(JICAやJETROを始め各業界)にトライすることも可能です。
いずれにしても、あまり視野を絞りすぎず、かといって広げすぎず、バランスよく併願していくとよいでしょう。
受験勉強に関するご質問
- 勉強のスケジュールは?
- 人それぞれです。学生か既卒者か、仕事・アルバイトをしているか否か、専門科目の既習者か否かなどの諸条件によって本試験までの戦略は変わってきます。
ただし、基本的には論文答練期(受験年の2~4月)に照準を合わせて専門科目を完成させていく必要があるため、逆算して「基本マスター」および「論文マスター」を消化していくのが良いでしょう。また、教養科目についても同時並行で進めなければなりません。特に数的処理については、「基礎能力試験の肝」ともいえる科目ですので、早めに講義を消化し、問題演習を繰り返し行っていただく必要があります。
また、英語などの受験言語の語学スキルの向上や、TOEFL・IELTSなどの各種検定試験の受験も併せて行っていくと良いでしょう。
TAC・Wセミナーでは、本科生を対象に「担任カウンセリング」を実施しています。受験前年の8月から毎月1回、担任講師に学習計画をご相談いただけます。カウンセリングを活用して効率的に学習を進めましょう。 - 合否の基準は?
- 1次試験については、全科目を総合して学力が優秀な順に合格者が決定されます。ただし、基礎能力試験で「足切り」にあっていないことが絶対条件です。
さて、受験生を最も悩ませるのが2次試験の合否の基準です。これについては諸説入り乱れており、これといった決め手はありません。ただ一つ言えるのは、2次試験もかなり詳細に点数化されているということです。面接、外国語面接、グループ討議、身体検査のどれをとっても、2次試験には万全の態勢で挑みたいものです。 - 全くの初学者でも大丈夫ですか?
- 大丈夫です。合格者には法学部や経済学部以外の人も多いですし、文学部や外国語学部、はたまた理系学部からも多数合格しています。TAC・Wセミナーは初学者でも十分合格レベルに達することができるようカリキュラムをご用意し、好評をいただいております。初学者ということで悩む必要は全くありません。
- 専門記述の試験委員対策は必要ですか?
- 独自に試験委員対策をする必要はありません。講師が試験委員の専門分野や傾向などを研究した上で講義を行っておりますので、しっかりと講義・演習・答練に取り組むことが最上の試験委員対策となります。
- 基礎能力試験(教養試験)の対策は?
- 外務省専門職試験の受験生は、専門科目(国際法・憲法/経済学)や語学の勉強に力を入れる傾向があるため、基礎能力試験のレベルはさほど高くありません。「足切り」の基準もそこまで高くはないでしょう。しかしながら、外務省専門職試験において、基礎能力試験は専門科目1科目分と同じ配点が振られているため、最終合格を目指すには6割程度を得点できるようにならないと厳しい戦いとなるでしょう。
基礎能力試験では、2024年度試験からは「知能分野」で24問、「知識分野」で6問出題されます。外務省専門職試験の基礎能力試験は、同日に行われる国家一般職試験の問題と共通のため、過去問や模試を利用して出題パターンに慣れておくことが必要です。しっかりと戦略を立て、安定して目標点数を取れるようにしましょう。 - 時事論文の対策は?
- TAC・Wセミナーでは、時事論文対策の講義があり、重要論点を整理し、論文を実際に書く練習をしますので、その他の特別な対策は必要ありません。ただし、日々ニュースや新聞記事などで国際情勢などを追い、知識を獲得していく必要があります。
また外務省HPにある外交青書や各種大綱を読むことも有効な対策です。日本外交はどのような方向へ進んでいるのかを把握していくことが重要です。 - 外国語の対策は?
- 英文和訳と和文英訳の対策はしっかり行っておく必要があります。英語がいくらできる人でも翻訳の練習を積まなければ、本試験で高得点を獲得することは困難でしょう。TAC・Wセミナーでは「英語試験対策講義」や「ホームルーム」等で、外国語試験の対策方法ををお伝えしていきますので、ご安心ください。2次試験では外国語面接がありますが、そこまで怖れる必要はありません。基本的には1次試験後の2次試験対策の中で自主ゼミや模擬英語面接などを通じて練習することで対策ができるでしょう。過去の合格者ではオンライン英会話などを利用している方も多くいらっしゃいました。
また、時間に余裕のある試験前年頃までに、各種外国語検定試験(英語であれば英検やTOEFL、IELTSなど)のスコアや級を獲得しておくと良いでしょう。 - 参考書は使用した方がよいでしょうか?
- TAC・Wセミナーの各種テキストで十分な学力が身につきます。むしろ、多くの参考書などに手を広げると知識がまとまらなくなってしまい逆効果となるおそれもあります。したがって、TAC・Wセミナーの教材を完璧にすることが合格への近道となります。ただし、判例集や条約集などを適宜用いている合格者もいますので、講師から推奨される参考書などを使用するのも良いでしょう。まずは講師に相談してみましょう。 また、語学に関してはご自身で参考書を探し、対策を進めていく必要があります。
- 2次試験について教えてください。
- 2次試験は、人物試験(個別面接・グループ討議)、外国語面接、性格検査、身体検査で構成されます。個別面接は、1次試験合格後に外務省から送付される「面接カード」をもとに質問されます。つまり「面接カード」は2次試験の鍵となるものなので、練りに練ったものを提出する必要があります。TAC・Wセミナーでは本科生を対象に経験豊富なプロ講師による「面接カード指導」も実施しております。
個別面接の雰囲気は人それぞれで、和やかに終わる人もいれば、圧迫面接を受ける人もいます。しかし、何を質問されても毅然とした態度で堂々と応えることが重要です。わからない質問をされた場合には、「わかりません。今後勉強します。」と素直に意思表示することも大切な要素の一つです。
外国語面接では、完璧なイントネーションや発音でネイティブ並に話せることが求められているわけではありません。むしろ重要なのは、不完全ではあってもコミュニケーションしようとする姿勢です。日常的に留学生などの外国の方と会話の練習をするのもよいでしょう。
TAC・Wセミナーでは、1次試験後に他の受講生と「自主ゼミ」を組んでいただきます。この「自主ゼミ」において受験生同士切磋琢磨していくことが、最善の2次試験対策であるといえます。