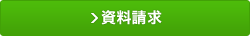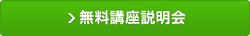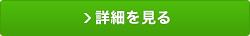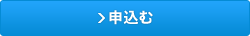vol9【現役外交官インタビュー】
国際法局 国際法課 国際裁判対策室 村本 晶子さん
2005年に外務省専門職員として入省された村本晶子さんにインタビューさせていただきました。村本さんは軍縮会議やEUの日本政府代表部での勤務もご経験されています。多国間外交の場でのご経験や様々な分野の業務を楽しむコツなどについてお聞きしました!
村本 晶子 (むらもと あきこ) さん
国際法局 国際法課 国際裁判対策室
研修言語:英語

Q. 外務省を目指されたきっかけを教えてください。
小学校の授業で第二次世界大戦について学んだ際に、日本が関与した戦争であることに強い衝撃を受け、戦争を起こさないための最後の砦は外交なのではないかと感じました。その外交に自ら関わり、戦争に突き進んでしまう流れを止める一助になりたいと感じたことが、外交官という職業を意識したきっかけです。
Q. これまでのキャリアパスを教えてください。
英語(カナダ)の研修となり、入省1年目は日米・日加の経済関係を担当する北米第2課に配属になりました。カナダのモントリオールでの2年間の在外研修を経て、オタワの在カナダ日本国大使館で勤務しました。その後本省に戻り、経済局の漁業室で捕鯨問題を含む水産外交に、軍備管理軍縮課で核兵器の軍縮に携わった後、ジュネーブにある軍縮会議日本政府代表部を経て、ブリュッセルにある欧州連合(EU)日本政府代表部で勤務しました。2年半前に本省に戻った後は、ユネスコの世界遺産関係の仕事に携わった後、現在は国際裁判対策室で勤務しています。
Q. 在外研修中はどのように過ごされていましたか。
学生時代に留学経験がなく、外務省に入ってから初めて留学をした私にとって英語は決して得意分野ではなかったのですが、カナダの温かい環境や人々、聞きやすい英語は学習環境として非常に良かったと思います。大学院では以前より関心のあった歴史学を専攻し、最終的に修士号を取得しました。
生まれて初めてカナダで生活する中で驚いたことは、「外国人でありながらこんなに生きやすい場所があるんだ」ということです。移民大国であるカナダでは、「外国人」が当たり前のように共存し、彼らを排他的に扱う空気がなく、自分自身、外国人という感覚を全くといって良いほど持つこと無く暮らせることに衝撃を受けました。
元々、自分自身の中に、海外への抵抗感はほぼ無く、海外経験を積む前から、不思議と外国の人とのコミュニケーションに対する自信のような感覚や、「国際関係に携わっていくことが自分の使命」のような直感がありました。日本と異なる文化や感覚に触れられることにはいつもワクワクしています。外務省に入り、実際に海外の人や文化に触れることで、直感が確信に変わっていったと感じています。
Q. 村本さんは、マルチ外交(多国間での外交)に長年携わっていらっしゃいますが、マルチ外交ならではのやりがいや難しさはありますか?
確かにマルチ外交は多国間での外交ですが、結局、根底はバイ(二国間)の外交と同じなのだと感じています。例えば、国際機関で日本が主導して決議を作るとなった際、他国の協力を引き出すためには、その国が求めるもの(国益)や逆に受け入れられないものを把握することが重要です。そのためには、会議という公の場ではない水面下での折衝における二国間の関係性も非常に大切になってきます。「日本が言うのなら」「あなたが言うのなら」と、他国の人の理解や合意を引き出せたときは達成感を感じました。外交は、表向きには国と国との関係ですが、現場では人と人との関係で物事は決まる、ということをマルチ外交の場で何度も実感しました。
また、マルチ外交ならではの特徴でありリスクという観点からは、現場では最後までどのような化学反応が起きるか分からないということがあります。情報収集不足で発言をすれば、思わぬ方向へ議論が展開してしまうこともあるでしょうし、他国の予想外の発言が契機となってまとまるはずのものが崩壊するといった可能性も考えられます。そういった事態をできるだけ防ぐためにも、相手の国の立場や考えを日頃からよくコミュニケーションをとって理解すること、こういう発言をしたらどの国がどのような反応をするだろうかといったことを想像しつつ、使う言葉に意識を払うことが重要だと思います。さらに、会議を円滑に進めるためにも、国際機関の事務局をはじめとした様々なアクターに丁寧に事前に根回しをしておくという外交努力も裏では行われています。
Q. 村本さんが特にご関心のある、核軍縮についてお聞かせください。
小学生の頃に先の大戦について学ぶ中で、日本への原爆投下という歴史に衝撃を受けるとともに、唯一の戦争被爆国として日本だけが発信できることがあるのではないかと感じました。
人類の歴史や、なぜ人は戦争を起こしてしまうのかということへ関心を持つなかで、核兵器は人類を力で威嚇するということの極限の形であると感じました。人類が自ら生み出した脅威に対し、日本として実際に何ができるかということを、政府の視点から取り組んでみたいと思いました。
本省の軍備管理軍縮課とジュネーブの軍縮会議日本政府代表部で勤務しましたが、非常に興味深い経験をさせていただきました。核兵器は所有国にとってみれば絶大な国力の象徴でもあり、これを単に減らそう・なくそうとしても現実世界では簡単に物事が動くわけではありません。核軍縮は、現実世界の政治とアカデミアを含む理論の世界の両面で議論が進んでいます。最終的に実務レベルでの軍縮をゴールとする中で、世界中の有識者の見識に触れながら、政府の立場から、どう現実に落とし込むのか、日本はどうあるべきかを、専門的な深い知見を持つ諸先輩方とともに、悩み考え、取り組んだ経験は非常に大きな財産になりました。
Q. さまざまな課室をご経験されていますが、新しい分野に取り組むことは大変ではありませんか?
そうですね、新しい分野に取り組む際、慣れるまでは大変です。異動してきて新しい課室の席に座ったその日から、「その分野の担当官」として扱われることになります。そのプレッシャーは少なからずありますが、元からいる同僚に助けてもらいつつ、日々多くの業務をこなしていく中で学んでいきます。そのようにしていくつかの課室を経験するうちに、共通して段々と押さえるべきポイントなどがわかるようになります。
また、外務省では少なからず緊急事態対応が必要な場面もあり、そのような時は残業を余儀なくされますが、個人的には常に無駄に残業することがないよう、できるだけ定時退庁できるよう心掛けています。本省勤務を開始した当初、職場の先輩で、業務は業務時間内に終わらせることを大事にし、自分を律して効率よく集中して働かれている方がいました。その分、日中はものすごい集中力で取り組む姿が印象的で、そうすると周りの人やカウンターパートもそうした姿勢を尊重し、結果として他の人の意識改革にも繋がっているのを見て、そういう働き方を目指したいと思いました。
Q. さまざまな分野の業務を楽しむコツを教えてください。
外務省では、2、3年に一度のペースで部署のローテーションがあり、キャリアを通じて様々な分野の仕事を担当することになります。業務対象の幅広さという意味では今日と明日では全く違う分野を担当することもよくあることで、そういう意味では「飽きっぽい人」は意外と外務省に向いているとも言えるかもしれません。これまで私が務めた部署も全く関連性のない分野ですが、私の根っこにはやはり「外交に携わりたい」という思いがあるので、どのような分野でも楽しめています。外交官は日本だけでなく、世界中が職場となるので、そこでの新しい出会いや、新たな環境での自分の変化にワクワクしながら働いています。
また、様々な部署を経験する中で見方が多角的になっていくのも面白い点です。例えば、キャリアの初期に経験した漁業関係の仕事で得た知見は、その後のEU代表部での通商業務にも活かされました。このように、一見違うことをやっているようでも、実は全てのことが積み重なっているという視点を持つことができれば、外務省での仕事はどんどん面白くなっていくと思います。
Q. 外務省を目指す方へのメッセージをお願いします。
外務省には様々なバックグラウンドの方がいます。特に近年、中途採用や任期付き職員など採用形態も多様化してきており、様々な経歴の方に幅広く門戸が開かれています。国際関係や外交に興味があるという方は、あまり難しいのではないかなどと考えすぎずに、ぜひチャレンジしていただきたいです。
Q. これから社会に出る学生にアドバイスをください!
社会人として初めて社会に出るときは「この先どの道を選ぶか」が、失敗のできない死活的な選択のように思われるかもしれません。しかし社会人になって思うのは、社会に出た後であっても、自分次第で進む道はいつでも軌道修正ややり直しがきくということです。ですから初めて社会に出る際には、その時に関心のあることに対して正直に、あまり悩みすぎずにまずはトライしてみることをオススメします。そういった柔軟な発想の方がその後の変化にも対応できると思います。これからの人生長いので、恐れずに自分の心に従い飛び込んでみてください!
取材後記
初心を忘れず、さまざまなフィールドで業務を楽しみながらお仕事をされていることが強く印象に残りました。また、マルチ外交のお話では、村本さんが「どんなに大きな場所でも結局は人対人」と仰っていたことに感銘を受け、自分も村本さんのような「人と人」を大切にする外交官になりたいと強く思いました。(小原)
ご自身の直感を信じて、未知の世界に果敢に飛び込み、新しい環境を純粋に楽しみながら働かれている姿がとても素敵だなと思いました。また、「自分を律して」、効率的に業務に取り組まれているというお話にも感銘を受けました。今回は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました!(大楠)