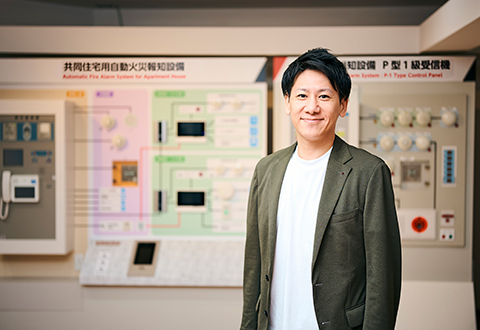人事担当者に聞く「今、欲しい人財」 第74回 株式会社オロ

藤塚 遼(ふじつか りょう)氏
コーポレート本部 人事・労務グループ
グループ長
2010年、株式会社オロに新卒で入社。クラウドソリューション事業部にて法人営業、導入支援の業務に従事したあと、管理部門で経理を担当。その後、マーケティング、広報、採用、IRと幅広い業務を経験。現在は社内研修制度、人事制度設計をメインに人事・労務を束ねる。
能力の多様性を組み合わせることで、
オロにしか出せない価値を創出していきたい。
株式会社オロは「ホワイトカラーの生産性向上」をミッションとするクラウドソリューションと、「テクノロジーとクリエイティブの力で、マーケティング効果の最大化」をめざすマーケティングコミュニケーションの2事業が柱となっている。オロの強みは、価値提供のコアであるモノづくりを支えるエンジニア職をはじめ、幅広い職種の人材がそれぞれ活躍できる点にあるといっていい。オロではどのような人材観を持って採用・育成活動をしているのか。コーポレート本部人事・労務グループ、グループ長の藤塚遼氏にお話を伺った。
クラウドERPの自社開発と企業のデジタルマーケティング戦略支援が柱
──最初に株式会社オロをご紹介いただけますか。
藤塚 オロは1999年設立のIT企業で、大きく分けて2つの事業を展開しています。ひとつがクラウドソリューション事業で、自社開発のクラウドERPの提供を通じて、企業が直面する経営課題を解決へと導き、業務の効率化や生産性の向上実現を支援しています。もうひとつがマーケティングコミュニケーション事業で、テクノロジーとクリエイティブの力でマーケティングの効果を最大化し、コミュニケーション設計によりクライアント課題を解決へと導くお手伝いをしています。
幅広い職種で「尖った人」を採用したい
──オロの新卒採用、中途採用の状況を教えてください。
藤塚 人数でいえば、新卒は毎年30~40名、中途は約30名とバランスよく採用しています。新卒は「デジタルを活用した課題解決に携わってみたい」という方に来ていただいています。中途採用は経験者から第二新卒まで幅広く採用しています。どちらにおいても、オロの経営理念と事業内容に共感いただけるかの「メンバーシップ」型のマッチングを大切にしています。
また、オロは作るところから売るところまで一気通貫で展開しているのが特徴です。そのため採用もかなり幅広い職種にまたがり展開しています。新たなシステムやサービスを開発するエンジニア職、コミュニケーションを設計し心を動かす言葉・ビジュアル・サウンドを生み出すクリエイティブ職、クライアントの課題の本質を捉えて解決策を形にしていくコンサルタント職、プロジェクトメンバーとマテリアルを取りまとめてゴールへ導くディレクター職、クライアントの課題を発掘して最適なソリューションを提案する営業職などです。新卒・中途を問わず、好きなことや得意分野に対する高い熱量を重要な要素と考え、「JOB」型のマッチングも重視しています。この「メンバーシップ」「JOB」の両方で相性のよいマッチングを図っているのが、オロの採用の大きな特徴です。
──オロの「求める人物像」とはどのような方ですか。
藤塚 能力の多様性がいろいろ組み合わさることで、結果としてより大きな価値、あるいはオロにしか出せない価値が出せると考えています。少し苦手なことがある人でも、「尖っている部分がうまく活きる組織でありたい」ので、「これが自分の強みです」というものをお持ちの方は、ぜひご応募いただきたいと思います。
新卒は入社後2~3週間の新入社員全体研修を実施
──2025年4月入社の新卒は何名予定で、内定者フォローは行っていますか。
藤塚 36名を予定しています。内定者フォローは、交流会を開いたり、Slackでの質問・相談環境を整え、不安を解消して入社を迎えられるようサポートをしています。全員参加型の研修は設けず、学生がそれぞれの学業や研究、サークル活動などに全力で取り組める時間を尊重しています。
早く就業体験をしたいという方には、早期インターンシップを実施しており、約10名が週3日程度の頻度でアルバイト入社をしています。
──2025年4月の新入社員研修はどのように実施される予定ですか。
藤塚 入社式後、新卒全体研修として、会社の経営理念や事業への理解、会社のルール理解、マインドセット、ビジネスマナー、ロジカルシンキング、ITツールの使い方といった、仕事上必要なベーシック要素をひと通り学びます。オフラインの講義とeラーニングツールを使ったオンライン学習を組み合わせて約2~3週間で実施します。
全体研修の最初の1週間は、当社の台湾拠点のオフィスで研修を実施し、その後、東京で集合研修する方向で考えています。

セールス、コンサル、技術・クリエイティブ、配属事業部でそれぞれ育成
──新入社員全体研修終了後、配属になるのですか。
藤塚 事業部への配属は4月の第3~4週目になります。オロでは事業部別職種別採用をしているので、総合職の中でも営業職なのか、コンサル職なのか、技術・クリエイティブ職なのかは、選考段階で見極めています。それをベースに大まかに職種を分け、事業部内で研修を行っていきます。
事業部内研修では、現場で必要となる業界の知見であったり、仕事の流れなどをさらに2~3週間、長いところは1~2ヵ月かけて研修を行います。部署によってはゴールデンウィーク明けから先輩に同行してお客様を訪問するなど、配属先によって異なってきます。
──入社半年後や1年後に同期が一堂に会する研修はありますか。
藤塚 事業部内でその職種に特化していきますので、全体で集まる研修はありません。ただ全社で経営理念研修を実施していますので、新卒に限らず全員が集まり、組織としてどこをめざしているのか、そのためにどのような行動がよりよいのかを考える時間を設けています。
新卒・中途ともに最終面接は社長
──中途採用に関しては年間の事業計画に沿って計画的に採用していますか。それとも人が必要となるタイミングでの採用ですか。
藤塚 事業計画に基づき、拡大が必要なポジションや過去の離職率を踏まえた補充人数を検討し、年間を通じた採用計画を策定しています。募集時期は、それぞれの組織の状況にあわせています。一方、社員の紹介を経由するリファラル採用は通年窓口を設置して行っています。
中途のオンボーディングは、人事労務手続きや会社のルール・人事制度の説明を実施したあと、直接ポジションに入ってもらうケースが多いですね。配属先のチーム長や先輩社員から、OJT形式で業務の流れや進め方を教わり、覚えていただくスタイルが一般的です。
──藤塚さんは新卒・中途両方の採用を見てらっしゃるのですか。
藤塚 採用は社長室が専属で担当しています。新卒であっても中途であっても、多くの場合、最終面接には社長が参加し、社長から見たカルチャーマッチを大事なポイントとして先行を行います。
私のいるコーポレート本部は入社後のオンボーディングから研修、人事制度を担っています。採用そのものは社長室に任せ、入社承諾後のフェーズから私たちが担います。

働き方の多様化を推進する「サンライフ」と「コアライフ」
──社内制度でオロならではものをご紹介ください。
藤塚 まず、土日の他に火・水・木から休日を選べる「サンライフ」と呼ばれる「選択的週休3日制」があります。この制度を使うと、1日の就労時間を8時間または10時間から選択できます。同じタイミングで子育て支援勤務制度の「コアライフ」も導入しました。こちらは、子育てしている社員が10~16時のコアタイムは出社して勤務する時間とし、それ以外の時間は働く場所(オフィスor自宅)と時間を柔軟に選択できるスタイルです。どちらの制度も、家庭や子育てとの両立を支援し、働き方の多様化を推進するために導入しました。
──どちらも時間を柔軟に選択できる制度ですね。週休3日を選択する方はどのぐらいいますか。
藤塚 当初は全体の10%程度でしたが、「サンライフ」実施後に課題が見えてきました。といいますのも、クライアント側は週5日勤務が通常ですので、週4日勤務ではレスポンスの遅延や連絡が来ても不在という、相手の期待値を超えにくい問題です。そこで職種を制限する制度変更を行い、現在はエンジニア職や制作職、専門職のメンバーが活用する制度となっています。
勉強会が盛んなオロのカルチャー
──教育研修での特徴を教えてください。
藤塚 オロの大きな特徴に勉強会が盛んな点があります。エンジニアはLT会(ライトニングトーク会)という勉強会を頻繁に開催しています。これは、いろいろな部署のいろいろなエンジニアが集まり、最近の技術や自身のホットトピックについて5分程度のピッチで発表していくものです。仕事上接点がなくても、同じエンジニアという括りで交流が生まれています。
他にも特定テーマを勉強するために、社内の得意分野を持つメンバーが講師を務め、勉強会を開いています。最近ではAIの活用方法についての講義が人気です。
オロには、こうした勉強会を支援する委員会もあります。勉強会は業務時間外の夜の時間帯に行われるので、参加すると委員会から軽食が提供されます。
──勉強会は業務時間外に実施されるのですね。
藤塚 研修は業務時間内ですが、自主的な勉強会は就業後、任意で集まっています。業務とは異なるので労務管理上は休憩(退勤)扱いとなります。委員会は社員の学びを促進することがミッションですので、そのためのひとつの形として食事が提供されるなどの工夫が行われています。

社内コミュニケーション活性化のためのグリーティングポイント制度「Oron(オロン)」
──福利厚生面で特徴的な制度があればご紹介ください。
藤塚 オロは健康経営優良法人の認定を取得しており、運動や食事、睡眠、いろいろなテーマで従業員のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)が上がっていくように、会社として健康経営に注力しています。
福利厚生のひとつとして、2021年から、1ヵ月の歩数が1日平均8,000歩以上を達成した従業員には「健康促進手当」というものを支給しています。1日8,000歩というのは内勤メインの社員にはなかなか厳しいハードルです。それでも意識的に1日平均1万歩以上歩いているエンジニアメンバーもいて、健康意識は上がってきたと感じています。ほかにも、非喫煙者に対する手当もあります。
──その他ユニークな制度があればご紹介ください。
藤塚 社内のコミュニケーション活性化のためのグリーティングポイント制度「Oron(オロン)」があります。これは日々の感謝やお祝いの気持ちを伝える目的で、1日1Oronを贈れる制度です。例えば、「仕事の受注おめでとう」「誕生日おめでとう」「朝のスピーチがよかった」といったメッセージを添えて贈るものです。Oronが貯まるとノベルティグッズのクッションやタンブラーなどに替えることができたり、東京の社内カフェでは5Oronで美味しいコーヒーが飲めます。全員に1日1Oronずつ更新され、誰かに贈らなければリセットされてなくなります。もらったOronは貯められて、贈るOronは使わなければなくなる仕組みですね。
こうしたさまざまな取り組みでコミュニケーションの質を高めることをめざしています。
資格取得の強い味方「資格取得一時金制度」と「教育研修奨励金制度」
──資格取得に関連する制度があれば教えてください。
藤塚 業務に関連する資格を取得すると会社からお祝金と受験料が出る「資格取得一時金制度」があります。現在30~50の対象資格がリストアップされていて、会計の基本となる「日商簿記検定試験」、コンサルティングに役立つ「中小企業診断士」といったメジャー資格から、いまのご時世の一般常識的な「ITパスポート」、エンジニアであれば「応用情報処理技術者」、「情報セキュリティマネジメント」といった国家資格系をメインに、一部ベンダー系資格も入っています。最近ではAIやディープラーニングの基礎知識を習得できる「G検定(ジェネラリスト検定)」までカバーしています。
──事業部ごとに推奨資格がリストアップされているのですね。
藤塚 そうですね。業務に必要な資格となりますので、部門によって対象が異なります。ユニークな取り組みとして、資格取得推奨の目的で委員会が2024年に企画した「資格クエスト」という、RPG的に資格を取得しようという企画があります。まず社内のツールを使って、「私はこの資格を取得します」と宣言し、がんばって勉強して取得したら報告が流れ、「おめでとうございます!」とみんなから祝福されます。こうした取り組みで、みんなで成長する機運を高めていこうと、いろいろ試行錯誤しています。
──資格取得のための講座受講の補助はありますか。
藤塚 少し違う切り口ですが、外部で何か研修を受ける場合に会社が最大20万円を支給する「教育研修奨励金制度」があります。この制度を利用して勉強し、支給日から3年間、当社で働いて勉強したものを業務で還元してくれれば、教育研修奨励金制度と利息を合わせた全額の返済を免除する貸付制度です。事業部ごとの推奨資格枠とこの教育研修奨励金制度で、受験料と合格お祝金の両方を受け取る組み合わせも可能です。
自ら学習することを後押ししたいと考えているので、手厚いサポートを心がけています。
──最後に資格取得やキャリアアップをめざしている読者に向けてメッセージをお願いします。
藤塚 今、私の隣席には社会保険労務士の資格を持って、労務の仕事をしているメンバーがいます。資格を持っていると、資格に裏打ちされた確かな実力があるので、アウトプットへの信頼は非常に高いと感じています。資格はとても有用です。特に知識を吸収しやすく定着しやすい若いうちから、資格取得にチャレンジするのは本当にすばらしいことですね!
[『TACNEWS』人事担当者に聞く「今、欲しい人財」|2025年3月 ]

東京本社の休憩スペース「Canvas」
会社概要
社名 株式会社オロ
設立 1999年1月20日
代表者 代表取締役社長執行役員 川田 篤
本社所在地 東京都目黒区目黒3-9-1 目黒須田ビル
事業内容
クラウドソリューション事業、マーケティングコミュニケーション事業
従業員数
単体314名/連結554名(2024年6月30日現在)
URL