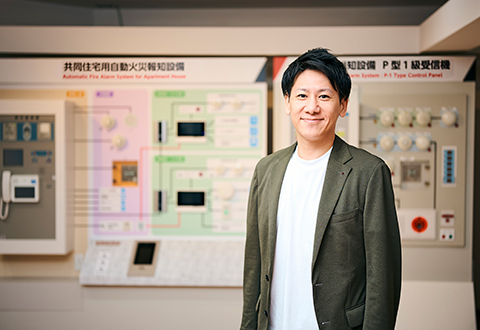日本のプロフェッショナル 日本の司法書士

洲鎌 佑輔(すがま ゆうすけ)氏
司法書士法人 洲鎌合同事務所
代表社員 司法書士
1992年、埼玉県生まれ。中央大学法学部卒業。大学3年生から司法書士受験をスタート。卒業後1年間はアルバイトをしながら受験専念。卒業2年目から司法書士事務所で補助者として勤務しながら受験。2019年、司法書士試験合格。2020年、司法書士法人洲鎌合同事務所に入所。2022年、代表社員となり2代目に就任。
ミスをしなければ成長も成功もない、ミスをおそれない組織作り。
父から受け継いだ仕事の任せ方です。
司法書士法人洲鎌合同事務所は、現在、2代目の洲鎌佑輔氏が事務所を切り盛りする。総勢20名、司法書士7名という中規模事務所を引き継ぎ、Webサイトの充実、YouTube配信など精力的に事務所のサービス改革に挑んでいる。司法書士をめざしたきっかけ、事務所の継承、継承当時のエピソードなどを交えながら、2代目としての成長を語っていただいた。
父への憧れから司法書士を受験
東京千代田区神田にある司法書士法人洲鎌合同事務所には、シーサーが置かれている。沖縄県宮古島出身の司法書士、洲鎌一彦氏が創業者だからだ。1989年開業、35年超の歴史を持つ事務所を継いで2代目となったのが、司法書士の洲鎌佑輔氏だ。
中学時代、洲鎌氏が通っていたのは名門私立中学。将来は医師や弁護士になりたいと、自身の将来を決めている同級生が大勢いた。そのような環境下、洲鎌氏は「自分は司法書士になりたい」と言っていた。
「父が司法書士だったので、間近で見ていて働き方に憧れていました。ただ、今思い返すと司法書士になりたかったというよりも、父のような自営業、社長業に憧れていたんだと思います」
父親から直接後を継ぐように言われたわけではない。それでも周囲が期待しているのは幼いころから感じていた。
「それがよかった面もあれば、イヤという気持ちもありましたね。子どもだったので、期待に応えざるを得ない感覚が少なからずありました」
その後、中央大学法学部に進学。大学3年生から司法書士をめざして受験勉強をスタートした。
「受験勉強をすればするほど、司法書士がどういう士業なのか、どのような理由でお客様が来るのかがわかってきました。同じ経営者でも司法書士は、ほかの中小企業経営者とは違う立ち位置であることがわかって、やってみたいとより一層思うようになりました」

6回の受験で合格
受験開始当初は、本人いわく「だいぶ的外れな勉強」をしたようで、1年経っても成績が上向く気配はなく、受験をやめて就職活動を始めることも考えた。
「ただ、自分の性格上、中途半端で終わるのがイヤで。負けを認めたら、就職活動にも身が入らないだろうと思ったんです。だから、卒業後の1年間、コンビニで早朝のアルバイトをしながら受験を続けました」
バイト以外の時間は勉強に充て、1年間受験に専念。それでも受からず、司法書士事務所で働きながら受験を続けることにした。勤務先は少人数の合同事務所で、不動産登記と商業登記の2本立て。洲鎌氏は不動産登記チームに配属された。
「仕事は覚えなければならない。受験もまだ終わっていない。なにしろ自分には社会人経験もない。電話対応すらできる自信がなかったので、とにかく言われたことを言われた通りにやる。したくないというより、やるしかないという気持ちでした。悔しいと思うことはあっても、しんどいと思うことはなかったですね。あまりに必死で、気づいたら本試験まで残り3ヵ月でした」
こうして働きながらの受験1年目の本試験は1問分届かず、2年目は1点足らずで不合格だった。
1問、1点で2度も落ちてしまうと、何をしてよいかわからなくなる。ただ、何かを変えなければいけないと考えた。変えたのは、実家暮らしからひとり暮らしにすること。事務所の代表が「自分のお金で生活することを知っておいたほうがいい」とアドバイスしてくれたからだ。
「それ以降は、難解な案件をあえてやらせてもらうようになりました。合格した年はかなり業務量を増やして、夜10時ごろまで働いていました」
残りの時間で受験勉強する洲鎌氏は、ある種悟りの境地に至っていた。
「普通に勉強していれば、おそらく、みんなある程度のレベルまでいける。そこから先は運の世界。さらにメンタルがかなり影響してくる。『いくら時間があっても足りない』と、足りないことばかり考えてしまいがちになる。そうなったとき、いかに時間がない中で自分をコントロールするか。そこにシフトしていきました」
朝早起きして出勤までの2時間、通勤時間の往復40分、休憩時間の一部、細切れ時間で1日3〜4時間は勉強時間を確保。定時退社の日は帰宅後にしっかり勉強した。
「できなかったらできなかったで『これだけやったし、今日はしかたない』。そうマインドセットしました。無駄なことを考えず、ただやるだけでした」
2019年、勤務3年目、受験6回目で、洲鎌氏は司法書士試験に合格。6回の受験を通しての経験は、洲鎌氏を精神的に大きく成長させた。
28歳で父の事務所へ
創業者のあとを継いで2代目となった若手有資格者は、往々にして悩むことが多い。よく聞くのは、創業者に絶大な信頼を置いている顧問先、事務所スタッフが多いということだ。入ったばかりの2代目は、さまざまな軋轢をくぐり抜けなければならない。
2020年、洲鎌氏は28歳で父親の事務所に2代目候補として入った。
「実は、父が病気になって、事務所に顔を出せないこともあったからです。合格して1年。若かった私は、受かった勢いで『自分が事務所をなんとかしなければ』と気負っていました。今思えば、28歳で引き受けるには重かった。勢いがあるあのときだからこそやれただけで、少し考える頭があったら引き受けてなかったかもしれないです(笑)。必死に食らいついてなんとかやっている状況でしたので」
入所した当時から、スタッフは19名と今と変わらない規模だった。洲鎌氏が入って有資格者は3名になったが、実働できるのは洲鎌氏ほぼ1人。洲鎌氏はプレイヤーとしてがんばってみたものの、経営面では売上が落ちた。理由は内部の陣頭指揮をとる人材がいなかったから。洲鎌氏は自身の未熟さを痛感した。
「コロナ禍とはいえ、売上が落ちた理由は自分にもありました。全体のバランスが崩れていました。かといって自分にはまだ発言権もなく、一番中途半端でした。それでも日々仕事をこなしながら『どうにかしなきゃ』と、そんなことばかり考えていました」

スタッフのがんばりで乗り越えられた
最初の1年半は、顕在化した課題を少しずつ潰していく作業から始まった。スタッフの雇い主は先代である父親。事務所内のベテランスタッフにとって、2代目の洲鎌氏は「資格を取得していても入りたての若手のひとり」でしかない。
それでも洲鎌氏は、「30年やってきたやり方がすべて正しいとは限らない。取引先の体制も変われば、社会の体制も変わる。ミスを防ぐためのチェック方法も、新たなツールが出ている。旧態依然とした方式にこだわり過ぎれば、ミスやトラブルは防げなくなる」と、強く感じていた。
想定された「起きてほしくないこと」はひと通り起きた。事務所のスタッフも半分入れ替わった。洲鎌氏は、先代である父親に相談しながらなんとかくぐり抜けてきた。
さらに、1年過ぎたころ、事務所の空気が変わってきたなと洲鎌氏は感じた。
「運よく私と同期の人間が3名入ってくれて。いろいろ相談できるようになって、やり方も変わってきて、大きなミスが減りました。
売上が下がったといっても、30年の歴史に裏付けられ、積み上げられてきた顧問先との信頼関係が、一気に落ちるわけではありません。そこからの回復は、今まで支えてくれたスタッフのがんばりがあって、乗り越えられたと思います。感謝しかないです」

2代目としてWebサイト、YouTubeに尽力
2022年、先代の意向で事務所の申請代理人が洲鎌氏に代わり、事務所の代表社員に就任し、実質的に事務所のトップになった。事務所をよくしていきたい、自分がやらなければ、という思いに突き動かされていた。
代表になった洲鎌氏は、まず、これまでなかった事務所のWebサイトを作成。さらに個人名でYouTubeの発信も始めた。
「誰もが必ず苦労するのが採用です。WebサイトもYouTubeも採用のためです。受験生にどうやって知ってもらうかを考えた結果、自分ひとりでもやれるのがYouTubeでした。YouTubeを始めて1年後、受かりたての有資格者たちが初めて面接に来るようになりました。そこから周囲の私を見る目が『申請代理人だし、もう2代目として認めていいでしょう』という空気に変わったんです。そこで、YouTubeも個人名から事務所名に変えました。
YouTubeとWebサイトを採用に活かした営業センス。認められたのは、そこが一番大きかったと思います」
Webサイト、YouTubeの配信によって、採用は現在も順調に進んでいる。トライ&エラーが、洲鎌氏を2代目として成長させたのである。
経営側の人材育成に注力
司法書士の場合、独立開業を目標とする人が多い。ただ、1年そこそこでの独立は本人にとっても事務所にとってももったいないと洲鎌氏は語る。そこで、違う経験をしてみたい、独立してみたいという社員のために社内独立制度をスタートした。
「かなり手探りでしたが、要望が多かったこと、若手育成につながること、ひいては事務所の将来のトップ育成につながるということもあって始めました」
社内独立制度を打ち出すと、手伝いを名乗り出てくれる司法書士も現れた。
2代目として代表社員を引き継いでから3年。2025年現在、総勢20名、司法書士の有資格者は7名に増えた。業務内容も、不動産登記をメインに商業登記、さらに、相続コンサルティングをプラスした。「相続はおさえておかないと絶対に成長しない」と、洲鎌氏が確信したサービスだ。
「事務所のビジョンで今言えるのは、拡大志向ではないこと。今20名、次は30名、40名、50名という志向はありません。ただ、自分がいなくても事務所が回るように、人を育てたいと思っています」
事務所が完成形になるのはまだ先のこと。しかし、ひとつの通過点として、「この人なら」と言える右腕をひとり、事務所内に置きたいと語る。
「早くて5年後。私が40歳くらいになったときに、自分とは違う観点を持った人材が新たな発想を生み出すのを見てみたい、そのような流れが生まれる組織にしていきたいです」
人を育てるには実務の教育研修もあれば、当然、有資格者としてのスキルアップもある。スタッフレベルも徐々に上げていかなければならない。
「いろいろ心を砕いてやるようにはしています。これも自分がやらせてもらえたから言えること。父はよく私に任せたなと、そこは頭が下がります」
最終的にはマネジメントする側の人間の教育に力を入れたい。そうすれば事務所は自然に大きくなるし、よい仕事もよい顧問先も生まれてくるだろうと洲鎌氏は考えている。
「自分でやらなければミスもしない。でも、成長もしないし、成功もない。だから、私も父のように極力任せようと思っています。仮にミスがあっても、日頃の仕事をまじめにやっているスタッフたちなので、大きなミスになる前にきちんと食い止められるはずです。普段は何も手を出さずに、そのときだけ私が出ていけばよいのですから」
スタッフを信頼し、事務所を任せる。その表情には、2代目の風格と覚悟が表れていた。
「洲鎌といると人に会える」と言われるように
先代は営業が得意で、顧問先の刈り取りが非常にうまかった。一方、洲鎌氏の営業活動は先代のアプローチとはだいぶ違う。
「先代は、昔ながらの取引先に足を運び顔を合わせて親しくなる方法。それもとても大事だと思いますし、その方法からの学びや気づきもありますが、私はYouTubeで対談動画を作ったりするアプローチも好きです。独立するにせよ、事務所にずっと勤務するにせよ、きちんとした成績を上げてくるスタッフが増えてきました。そうなれば裁量権とまではいかなくても、ある程度事務所を任せられる。私は人と人をつなげる仕事ができるんです」
これまではスタッフ指導のために内部にいることが多かったが、今は司法書士業界だけでなく税理士や弁護士など他士業との会合にも顔を出せるようになった。
「『洲鎌といると人に会える』と言っていただけるよう日々心がけています。例えば、草野球の練習試合で対戦したチームの方に、取引先の野球チームを紹介したり。あるいは、司法書士という立場を活かし、様々な情報の通過点として人と人、情報と情報をつなげたり。そうした行動が私にとっての営業活動なんです」

売上回復、次の種を蒔く
人を採用する際、洲鎌氏がもっとも重視するのは人間力とコミュニケーション能力だ。
「ただ、その見極めは本当に難しい。独身から結婚、子どもが産まれて家族が増える、両親の介護といったライフステージの変化によっても、人は変わります。いろいろな変化があっても、私と一緒に成長してくれる存在は大切です。人を採用するたびに、学ぶことがとても多いと実感しています」
落ち込んでいた売上も2024年3月末からは上向いてきた。
「5年前に比べたらありがたいことです。ただし、ここから先は自分ひとりではどうにもならない。周囲のスタッフのサポートでいかにうまく回していくかです。やり切ってくれるスタッフには感謝しかありません」
相続業務も順調に増えている。ただし、それが5年、10年先まであるわけではない。「次の種蒔きを模索中です」と、洲鎌氏は意欲を燃やす。
理想は「みんなが前向きに能動的に動ける」事務所
規模は追求しない洲鎌氏だが、今後の事務所のあるべき姿について、次のように話している。
「これだけの人数規模になると、給与面、待遇面でどのようにうまく折り合いをつけて着地するかもあります。そこがうまくできる事務所にしていきたいと思います。
その先は、自然にみんなが盛り上がってくれる事務所。理想は私が大きくしたいではなくて、みんなが前向きに能動的に動ける事務所。みんなが『これやりたい、あれやりたい』というのが私は好きですし、一緒に盛り上げていきたいですね」
2代目となって4年。「ありがとうと言われること」がやりがいになったと洲鎌氏は言う。
「司法書士という肩書きだけで、安心して提案を聞いてもらえる。同じことを言っても、説得力がある。そこが資格の一番の魅力です」
今勉強中の受験生にはこんなメッセージを語ってくれた。
「弁護士、公認会計士、税理士、司法書士といった国家資格は、決して楽して合格できない試験です。受験生の自分は、自分とどう向き合ったか。何をがまんしてどう勉強したか。その取捨選択した経験は必ず一生残ります。
士業が先生と呼ばれ、楽しそうでキラキラ見える裏側には、そうした経験があります。そこを思いながら受験勉強に励んでください」
[『TACNEWS』日本のプロフェッショナル|2025年7月 ]
・事務所
住所 東京都千代田区神田多町2-4第二滝ビル6階
Tel.03-6260-9670
URL:https://www.sugama-law.jp/