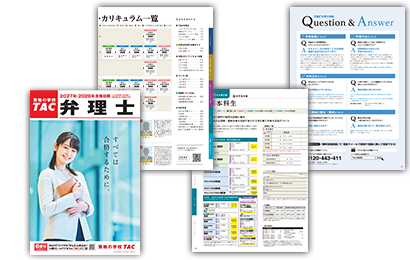弁理士試験の難易度はどれくらい?
データに基づいた合格の条件を解説

弁理士試験の最終合格率は、近年6%程度となっており、難易度は非常に高いと言えるでしょう。
本記事では弁理士試験の難易度とその推移を解説するとともに、合格者のデータを踏まえて、試験に受かるためのポイントを解説します。
弁理士講座 デジタルパンフレットを閲覧する
【無料】弁理士
「令和7年度短答本試験分析資料・解答解説集(PDF)」閲覧サービス請求フォーム
弁理士試験の短答式試験について、本試験を実施する特許庁から「解答番号」は公表されますが、「なぜそれが正解になるのか」という解説はありません。そこで、TACでは試験に精通した講師陣が毎年本試験を分析し、全60問の解答解説を作成しています。
この「短答式試験解答解説」を受験生のみなさまに無料提供いたします。以下のフォームに必要事項を入力すれば、すぐにご覧いただけます。これから弁理士を学習される方はもちろん、受験経験者の方もぜひご活用ください。
【重要】解答解説集のご利用につきましては、お送りするメールの注意事項をご確認ください。

個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。
弁理士試験の難易度はかなり高い
弁理士試験の難易度はかなり高いと言っていいでしょう。合格率はかなり低い数字になっており、合格者数も少ないからです。
弁理士試験が難しいのは、学習しなければならない範囲が広いことも要因の1つと考えられます。ここでは2024年度の最終合格率や近年の合格率の推移、さらには他の国家試験の難易度との比較などについて解説しましょう。
弁理士試験 2024年度の最終合格率は6.0%
2024年度(令和6年度)の弁理士試験の最終合格率が6.0%であることが、2024年11月18日に特許庁より発表されました。志願者数3,502人、受験者数3,160人に対して、合格者の数は191人という狭き門で、最終合格率は6.0%です。
つまり100人受けて、6人合格という難関であるため、合格するためには入念な準備と勉強時間の確保と覚悟が必要になります。
弁理士試験の合格率や合格者数の推移
下の表は弁理士試験の過去6年間の受験者数と合格者数、最終合格率を表したものです。
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|
| 2019年度(令和元年度) | 3,488人 | 284人 | 8.1% |
| 2020年度(令和2年度) | 2,947人 | 287人 | 9.7% |
| 2021年度(令和3年度) | 3,248人 | 199人 | 6.1% |
| 2022年度(令和4年度) | 3,177人 | 193人 | 6.1% |
| 2023年度(令和5年度) | 3,065人 | 188人 | 6.1% |
| 2024年度(令和6年度) | 3,160人 | 191人 | 6.0% |
参考:特許庁
ここ6年間を見ても、弁理士試験が難関であることがわかります。直近の2024年度は合格者数も少なく、最終合格率も低いため、難易度がアップしていると言えるでしょう。
他の国家試験との難易度を比較
弁理士は他の国家試験と合格率を比較した場合にも合格率は低めです。他の士業の中では、司法書士の3~4%、社会保険労務士の4~6%に次いで、3番目に難しい結果となっています。なお4位以降は土地家屋調査士・行政書士・税理士・弁護士・海事代理士です。ただしこれはあくまでも「合格率」のみを比較した場合の数字です。例えば社労士はマークシートのみの試験ですが、弁理士は短答(マークシート)・論文(必須科目・選択科目)・口述試験と3段階ある試験です。また弁護士の場合は国家試験を受ける前に予備試験もあります。その合格率が4%ほどなので、予備試験も含めると、弁護士が最も難しいと言えますが、弁理士試験もその次あたりに位置する試験といえます。
弁理士試験に合格しているのはどんな人?
2024年度の弁理士試験に合格している人の傾向を見ると、職業では会社員、理系と文系では理系が多い結果が出ています。年齢別では30代がもっとも多く、男女別では男性が多いです。
合格者で多い平均受験回数は2~4回、合格に必要な平均勉強時間の目安は約2000~3000時間とされています。これらの数字からも弁理士試験の難しさの一端がうかがえるでしょう。
それぞれ詳しく解説していきます。
職業別・理系文系別の傾向
下の表は2024年度の弁理士国家試験合格者の職業別の内訳を表したものです。
| 職業別 | 割合 |
|---|---|
| 会社員 | 46.6% |
| 特許事務所 | 33.0% |
| 無職 | 4.2% |
| 公務員 | 8.4% |
| 学生 | 3.1% |
| 法律事務所 | 1.6% |
| 自営業 | 0.5% |
| 教員 | 0.5% |
| その他 | 2.1% |
参考:特許庁
会社員が半数近く、ついで特許事務所となっており、合格者の多くは働きながら受験しています。出身校の系統別では理工系が81.7%、法文系14.1
%、その他が4.2%です。
年齢別・男女別の傾向
2024年度の合格者の年齢別内訳は、20代31.4%、30代43.5%、40代20.4%、50代3.7%、60代1.0%です。30代がもっとも多く、続いて20代と40代が並び、20代~40代合わせて90%超を占めています。
男女別の合格者は男性68.1%、女性31.9%です。弁理士は他の士業と同じように、結婚・出産などで休職した場合でも復帰しやすいため、女性が活躍しやすい資格の1つと言われています。
平均受験回数と平均勉強時間
2024年度の弁理士国家試験合格者の平均受験回数は2.4回です。前年度は2.8回であったため、受験回数は減少傾向がありますが、数年間はかかると想定したほうがいいでしょう。
合格者の平均勉強時間は約2000~3000時間とされており、働きながら受験している人が多いことから考えると、就業時間外に勉強時間を確保する必要があります。
弁理士試験の概要
弁理士試験には受験資格がないため、誰でも受験できます。試験は「短答」「論文」「口述」の3段階に分かれており、それぞれ時期が異なるのが特徴です。
「短答」の合格者が「論文」の試験を受ける資格を得られ、「論文」の合格者が「口述」の試験を受ける資格を得られます。ここでは受験資格と「短答」「論文」「口述」の試験の詳細について、解説します。
弁理士試験は誰でも受験可能
弁理士試験は学歴、年齢、国籍などによる制限は一切なく、受験資格もないため、誰でも受けることができます。例年、願書の提出期間は3月中旬~4月上旬です。
なお、短答式試験は5月中旬~下旬、論文式試験は6月下旬~7月上旬、口述試験は10月中旬~下旬がおおよその目安となっており、長丁場となるため、学習面だけでなく、体調面も含めてしっかりと準備しておく必要があります。
弁理士試験は「短答」「論文」「口述」の3段階
弁理士試験は「短答」「論文」「口述」の3段階に分かれており、「論文」はさらに必須科目と選択科目に分かれています。出題の範囲が広いことが、試験の難易度を高くしている要因でしょう。
なお、弁護士および7年以上の特許庁の審判官もしくは審査官として審判もしくは審査の事務に従事している場合は、3段階の試験が免除され、実務修習のみで弁理士資格を持つことができます。
「短答」「論文」「口述」の難易度と
攻略ポイント
「短答」「論文」「口述」の難易度と攻略ポイントを解説します。2024年度の弁理士試験合格率は、「短答」12.8%、「論文」27.5%、「口述」91.7%で、最初の関門の「短答」の難易度が高いといえます。しかしその難関である短答試験を突破した方が受験する論文試験の中からさらに1/4程度に絞られますので、弁理士試験最大のヤマは論文です。
しかし、合格しなければ次の段階に進めず、受験する段階で人数が絞られているため、合格率だけでは難易度を判断できません。それぞれの攻略ポイントを解説します。
短答は最初の関門
短答式試験は最初の関門です。特許・実用新案・意匠・商標・工業所有権に関する条約・著作権法・不正競争防止法などから、5肢択一式の問題が60問出題され、65%以上の正解が合格基準とされています。
問題は5分野に分かれており、各分野で最低40%以上正解する必要があるため、合格するにはこれらの法令を網羅して勉強することが必要です。
論文は必須3科目、選択1科目と広範囲
論文式試験は「特許・実用新案」「意匠」「商標」という必須3科目と選択1科目です。必須科目の合格基準は100点満点で平均54点ですが、47点未満の科目があると、不合格になるため、不得意科目を作らないようにする必要があります。
論文式試験は2時間と1.5時間の2種類あり、日頃から時間内で論文をまとめる練習をしておくことが大切です。
口述は合格率が高めだが油断は禁物
口述試験は合格率が90%超と高めですが、油断はできません。今までの試験形式(ペーパー試験)と違い、試験官2名と問答すること、1科目10分という制限があることなど、緊張感が高まるシチュエーションだからです。また論文試験を突破した方はきちんと口述対策も行うため、合格率が高くなっているともいえます。
「特許・実用新案」「意匠」「商標」の3科目から口頭で出題されて、答える面接方式の試験で、2科目以上の答えが不十分である場合には不合格となります。面接慣れをしておく必要があるでしょう。
難易度の高い弁理士試験に
入念な準備で挑もう
2024年度の弁理士試験合格者は191人、最終合格率は6.0%であり、他の国家資格と比較しても、かなり難易度が高いと言っていいでしょう。合格者の平均受験回数は2.4回、平均勉強時間は2000~3000時間が目安となっています。
試験は「短答」「論文」「口述」の3段階に分かれており、試験範囲はかなり幅が広いために、入念に準備し、勉強する時間を確保して、覚悟を持って挑んでください。
まとめ
弁理士試験の難易度と試験に受かるための攻略ポイントなどについて解説しました。
弁理士試験は「短答式試験」「論文式試験」「口述試験」の3つで構成されており、3つすべてをクリアしなければ最終合格を勝ち取れない試験です。試験範囲はかなり幅が広いため、入念に準備し勉強する時間を確保する必要があります。
TACでは、実務経験が豊富な講師や弁理士試験の傾向と対策を熟知している講師が、長年蓄積された講義ノウハウを元に適切な方法論と熱意をもって講義をしています。実体験に基づいた講義ですので、内容をわかりやすく伝えるだけでなく、どのように伝えたら、理解が促進されるかということも意識した講義をします。
また、定期的に学習方法などのアドバイスも発信し、安心して勉強が続けられるよう、悩みや学習サポートも全力で受講生をバックアップいたします。
仕事や家庭を両立しながら無理なく学習を進めたい方や、1年で短答式試験と論文式試験の同時合格を目指したい方など、環境やご希望に応えることのできるコースを揃えています。
弁理士のコース一覧を詳しく見る!
資格取得後、その先は…? 実務家インタビュー