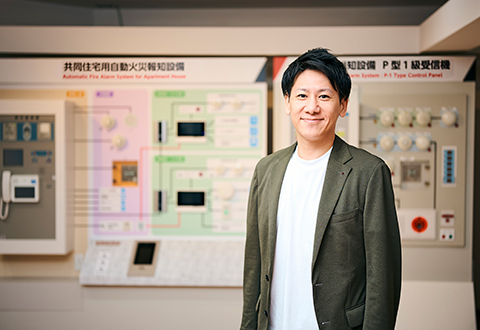日本のプロフェッショナル 日本の会計人

木田 穣(きだ ゆたか)氏
木田国際税務会計事務所 代表
公認会計士 税理士
1980年生まれ、千葉県出身。1999年、千葉県立船橋高校卒業、2004年、東京大学経済学部卒業。翌年、公認会計士第2次試験合格(当時)。 合格後、有限責任監査法人トーマツ入所。3年間勤めたあと、税理士法人レガシィに転職。2010年、東京都中央区勝どきにて開業。港区赤坂、中央区日本橋を経て現在の渋谷区西原へ移転。現在に至る。
「相続」×「国際税務」×「海外移住」の3本柱で挑む。
税理士であることが、圧倒的な信用につながります。
「相続」×「国際税務」×「海外移住」。3つの切り口を掲げる公認会計士・税理士の木田穣氏は、グローバルに活躍する富裕層をメインに高品質なサービスを提供している。木田氏はどのような経緯で公認会計士になり、独立開業して、相続から国際税務まですそ野を広げてきたのか。その経緯をうかがった。
2000年、景気低迷期に資格取得をめざす
インドネシア、ハワイ…、家族で行った海外旅行が楽しかったので「将来は世界で仕事をしたい」との思いが今につながる木田穣氏の原点のひとつだ。
木田氏が大学に進学した2000年は、「失われた20年」と呼ばれる日本経済停滞期のど真ん中。安定を求めて資格を取得する学生が増えていた。
「公認会計士(以下、会計士)をめざそうと決めたのは大学1年生のとき。景気が悪い2000年入学なので、周囲にも資格取得をめざす人が大勢いました。経済学部なので弁護士より会計士のほうがフィットすると考えて、大学2年生から受験勉強を始めていましたが、TACには大学4年生から通いました」
当時、大学の学友は合格実績を誇るTACに早い段階から通っていた。一方の木田氏は、本腰を入れてやろうと決めた大学4年生からTACに通い始めたという。
半年間留年し、2004年9月に大学を卒業。その翌年2005年に会計士第2次試験(当時)に合格した木田氏は有限責任監査法人トーマツ(以下、トーマツ)に入所して、会計士としての第一歩を踏み出した。

相続税申告に特化した税理士法人に転職
トーマツでは国内監査グループに配属され、上場会社の法定監査に従事した。その頃から木田氏は、「富裕層はどのようにして富裕層になるのか」「どういう考え方をするのか」「どういった課題があるのか」「どうやったら富裕層になれるのか」に興味を持つようになっていた。同時に興味を持ったのは相続税だった。
3年後、会計士第3次試験(当時)に合格すると、木田氏はトーマツを退所。監査法人では相続税の専門知識を身につけられないので、税理士法人レガシィ(以下、レガシィ)に転職した。
総合型の中堅・大手税理士法人は相続税だけでなく事業承継なども行っており、必ずしも相続税申告に特化した仕事ができるわけではない。それに相続税申告書を書いた経験がなければ、採用してくれない法人もある。木田氏がピンポイントで選んだのは相続税申告に特化したレガシィだった。
「これから相続税の一大ブームが来る。それなら富裕層相手にビジネスをする武器として、相続税を習得すべきだ。そう考えて、レガシィに転職しました」
相続税申告を徹底的に身につけた木田氏は、約2年半後の2010年、29歳のときに東京都中央区勝どきで独立開業した。税理士登録をしたのもこの年だった。
富裕層をターゲットにキャリアを構築
「開業した理由は『富裕層をターゲットにしてキャリアを築いていきたい』と考えたこと。さらにこれから相続税のブームが来ると考えました。税制改正により相続税の基礎控除額が大幅に下がるのではないかと見込まれていたこともあります」
開業するにあたり、木田氏は上場会社の創業者、未上場会社のオーナー、地主、医師といった資産家を対象に、通常の税務に相続対策の視点をプラスした顧問業務を展開することを軸に据えた。とはいえ、開業にあたって顧客獲得などの事前準備は一切していなかったという。
「お客様のあてがまったくないゼロからのスタート。妻も働いていたので貯蓄の数百万円を加えれば、無収入でも何とかなると楽観的でした」
そんな木田氏を救ってくれたのは、義母から紹介された親戚の歯科医師だった。そこからさらに紹介で歯科医師会の公益法人制度改革手続きを任せてもらえたのである。
とはいえ、順風満帆とはいえない船出。開業当初は相続税申告を軸にやっていこうと考えていたが、相続専門の税理士法人の躍進もあり「相続を個人で始めても、紹介ルートを切り開くのは難しいな」と悩んだ。
「開業当初は『月3万円の顧問料で記帳代行も何でもやります』というサービスをたくさんやりました」と、当時を振り返る。
この何でも受けるスタンスが意外にも功を奏し、徐々に顧問先は増えていった。加えて公益法人の仕事を社団法人4~5社ほど任せてもらえるようになると、紹介が自然に増えていったのである。
当初は、個人の歯科医師や地主のお客様からの確定申告と月次顧問報酬がメインだった木田氏は、改めて相続分野にチャレンジすることにした。
「当時は、まだ相続税申告の経験がある税理士が比較的少なかったので、ニッチな領域でした。相続税申告を始めると、いろいろな紹介先から依頼が来るようなりました。すでに顧問税理士がいても、相続への不安からセカンドオピニオンを依頼されるケースもあり、そこをフックに顧問業務に至るケースがかなり増えてきました」
通常ならインターネット集客に頼りがちだが、木田氏は紹介で地道に顧客を広げてきた。それは今も事務所の大きな特徴となっている。

2020年から海外移住案件に着手
毎年コンスタントな相続税申告業務に加えて会社オーナー、医師、地主顧問先に対する事業承継対策など、相続税顧問業務も増えている。その他にUAE、シンガポール、タイへの海外移住コンサルティングと、都内や神奈川県での歯科医師会の公益・一般社団法人への関与が7件に増えた。
海外移住の第1号案件が入ったのは2020年。特に2020年のコロナ禍直前期からは海外移住案件が増え始め、「これはニーズがある」とピンと来たという。
「海外移住が増えた背景には、2つの要因があります。1つ目は、海外へ移住した著名人がYouTubeで広く発信したことで、海外移住へのハードルが下がったこと。2つ目は、中小企業のM&Aの増加です。これも海外移住と非常に相性がよい。経営者がM&Aで企業を売却したしたあと、経済的に必ずしも日本に住み続ける必要性がなくなるため、子どもを海外のインターナショナルスクールに入れて教育したいというご家族が増えました。日本でなくてもいい。子どもの将来を考えて、海外という選択肢が増えたわけです」
それでも海外移住案件は、当初顧客ニーズがどこにあるのか手探り状態だった。海外移住には日本の税務が大きく関係している点が肝だと気づいたのは、しばらくしてからのことだ。
「海外へ移住する方が心配なのは、どちらかといえば出国時の税金や相続税です。ビザ取得より税金の悩みが多い。特に富裕層の海外移住となると、税理士への相談はマストです。そこから国際税務に非常に大きなニーズがある、今後増えるという直感がありました」
海外移住に対応できる税理士は、当時あまり多くなかった。木田氏はYouTubeへの出演、紹介によって、相続と海外移住絡みの国際税務を積極的に進めていった。その結果、個人の海外移住と国際税務、相続が仕事として多くなっていった。海外移住案件は、今後もさらに増えていくと木田氏は予想している。
一方、相続案件は関東近辺資産家から毎年一定量、安定的に依頼がある。顧問業務と相続税案件などスポット業務の比率は半々だと木田氏は話す。
「相続税に関しては、これまでいただけた案件を受けるだけで、あまり広告や紹介のルート開拓をしてきませんでした。ただ紹介していただけることは非常にありがたいこと。紹介者の顔に泥を塗らないように、きちんとおつき合いさせていただいています」
相続税を増やしていこうという意気込みを込めて、代々木上原(渋谷区西原)に事務所を移転し、オフィスを「家族の税理士事務所」という名称で営むようになった。紹介先を大切に、地道にやっていくのが木田スタイルだ。
所内は20代から30代の若手中心の事務所
現在事務所は木田氏と常勤社員4名(うち1名は2025年2月入社)とパートスタッフ2名、在宅パートスタッフ2名、合計9名で運営している。最初にスタッフを採用したのは、日本橋に事務所を構えていた開業6年目。現在のオフィスに移転してからは継続的に採用を続け、在宅スタッフは3年前から採用し始めた。
常勤社員のうち1名は会計事務所勤務経験10年以上の税理士試験3科目合格者、2025年2月入社の新入社員は会計事務所勤務5年の経験を持つ。
「社員はみな会計事務所で3年以上の勤務経験がある経験者です。採用時点で資格の有無は問いません。お客様とのコミュニケーションをうまく取れる、誠実でまじめな方であればいい。まあ理想を言えば、税理士有資格者かつ税理士業界で充分な経験があり、私と同年代くらいまでの年齢の方がさらにいればよいと思っています。また今後は海外移住案件の増加が見込まれるため、税理士業務でなく海外移住支援に興味がある未経験者の採用も考えています。」
なかなか理想の人物にお目にかかることはできないが、もう1人税理士がいれば法人化も可能になる。所内で合格者が出れば、一緒に相続案件、海外移住案件に関わり、業務の幅がさらに広がると、木田氏は考えている。

今後、常勤社員を10~20名に増員
約50件ある顧問先との面談は、基本的に4名の常勤スタッフに任せ、木田氏はオンラインで面談に同席する。任せるところはスタッフに任せ、木田氏は難解な相続案件や海外移住案件にあたる。今いる9名で業務をこなすにはキャパシティ的には十分だが、今後を考えると、これから数年で事務所の規模を常勤社員10~20名に増やしていかなければならないと考えている。
今の倍以上の規模をめざす木田氏が考える業務の柱は、相続と海外移住、そして暗号資産だ。
「この組み合わせがなかなかおもしろく、個人的にも興味があります。今のところ『暗号資産×相続』という切り口での相談はありません。でも、ご相談として会社をM&Aで売却した資産家で海外移住する人の資産に暗号資産が含まれている場合があります。中には海外に出て暗号資産を運用する方もいらっしゃる。そこから暗号資産と海外移住の組み合わせの相談も来ます」
今後は相続したら暗号資産がたくさん含まれていたというケースも増えてくるに違いない。となれば、相続税申告に相続財産として暗号資産を含めることになる。
「相続財産に暗号資産が含まれていると、相続税支払い時の現金確保にあたり大きな税金の課題があります。納税は暗号資産ではできませんので、日本円が必要になりますが、相続人が日本円に交換する際に多額の税金がかかるためです」
税理士であることが圧倒的な信用に
今後は顧客を拡大するために、紹介だけでなくYouTubeをメインに据えていくと、木田氏は話す。
「YouTubeをさらに活用していく予定です。特に会社をM&Aで譲渡したあとのことを考えている方は、自分からいろいろ調べます。そのような方を前提に、問い合わせにつながりやすいのがYouTubeです」
YouTubeの積極的な活用と並行して、海外同行も積極的に行っていく。これまでも木田氏は海外移住の相談に乗る際、移住する富裕層と一緒に現地を視察している。
「四大法人ならグローバル企業のクライアントの関係で海外出張があるかもしれません。でも、個人の開業税理士で海外出張を仕事でするケースは極めて少ないと思います。ある意味、子どもの頃にしたかった海外での仕事につながった感覚がありますね」
海外出張では現地の不動産事業者や提携会社の案内で、クライアントとともに現地の賃貸マンションやインターナショナルスクールの視察に行く。
「ご家族と一緒に、半日かけて車で物件を5~6ヵ所回ります。すると同行している間に、現地を見ながらいろいろなご相談を受けることができます。また、他のお客様が同じ国を見に行く際に、有益な情報を提供できるメリットが大きいですね」
国内には海外移住の相談に乗り、ビザ取得や留学先を斡旋してくれるエージェントが多々ある。しかし、海外に移住し、その学校に入らなければ手数料は入らないし、ビザを取得してくれなければ手数料が入らない。エージェントは海外移住が成立しないと商売にならないのだ。このような経緯から、エージェントはよいことばかりを伝えてくると、木田氏は指摘する。
「私たちは、相談料の対価としてフェアなアドバイスをします。その意味で税務に限らず、ご家族の一大決断をする際に、意見を聞く相手として信頼されます。
それは相談料を支払って公平な意見を申し上げるサービスが定着している税理士だからです。税理士であることが、圧倒的に信用につながるんです」
移住先の相談を受けた際、木田氏がおすすめするのは東南アジアだ。
「例えば、20代で起業して15年間ほど会社経営に没頭し、40歳手前でその会社をM&Aで売却したとします。M&A売却時にお子様が小学生というご家庭も多く、海外での教育を視野にご家族で海外移住というケースも多いです。世の中にはそうした富裕層が、都内だけでも毎年数十人以上生まれているように思います。
そのような方におすすめなのは、やはり時差がなく環境もよい東南アジア。一番敷居が低いでしょう」
シンガポールやマレーシアは、株や債券の配当利息に対して個人に課税するしくみがない。
「日本では配当利息や株売却益に対して必ず約20%の課税がされます。シンガポールもマレーシアも、個人については実質的に配当や株売却益への課税がないケースが多いですので、メリットは大きいですね」

資格試験の勉強は人生を変える
「資格取得後、40代のキャリアを早めに設定すること。独立するのか。どこかに勤務するのか。まずは、大きな二択があります。この選択は人生において非常に重要です。資格を取得して10年、20年経つ先輩に話を聞いてみることをおすすめします。私でよければウェブページのお問い合わせから個別にメールをいただければ受験生のキャリア相談にも乗ります」
会計士、税理士をめざして勉強中の読者に、木田氏はそうアドバイスする。
自身がTACに通学していた当時、「受験生にも講師の先生にも、活気と熱気があった」と思い返す。
「今でも一番仲のよい会計士の友人は、その当時知り合った受験仲間。大学が違っても、TACで知り合ってから彼の友人と友人になれるなど、非常に大きな影響がありました。TACに行ってよかったことは、同じ受験という苦労を共有した一生涯の友人ができたことです」
さらに「資格試験の勉強は人生を変える」と、言葉を続ける。
「TACに通った1年は、まさに勉強、まさに青春。TACの自習室で勉強した1年間は、すばらしい時間だったし、楽しかったですね」
今は苦しいと感じる受験勉強も、振り返ればすばらしい時間になる。それを、木田氏は後進に伝えたいという。
[『TACNEWS』日本のプロフェッショナル|2025年3月 ]