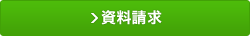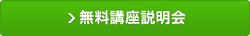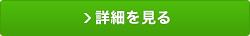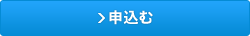消防設備士甲種1類とは?/消防設備士乙種1類とは?
仕事・メリット・試験概要・合格率などを徹底解説!
消防設備士甲種1類とは?消防設備士乙種1類とは?
消防設備士は各消防設備の設置工事・点検整備をする国家資格

消防設備士とは、ビルやデパートなどの建物に設置が義務付けられている、消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行うことができる国家資格です。
消防設備士は種類により設置工事・点検整備できるものが違います。
第1類 水系消火設備(消火栓・スプリンクラー等)
第2類 泡系消火設備(泡消火設備等)第3類 気体系消火設備(ハロゲン消火設備等)
第4類 自動火災報知設備(火災報知設備・警報設備等)
第5類 避難器具(避難はしご・救助袋等)
第6類 消火器
第7類 漏電警報装置
特類 特殊消火設備
試験は各類に分かれ、さらに類により甲種乙種に分かれます。もちろんすべて試験は異なり、合格した類でさらに甲乙で分かれている場合はその種のみの業務が可能です。もし免状不携帯で仕事をした場合、義務違反となり罰則を受けることになります。
-
甲種
消防設備の点検・整備・設置・交換工事を行います。特類~5類まであります。
-
乙種
消防設備の点検・整備を行います。1類~7類まであります。
消防設備士甲種1類、消防設備士乙種1類は水系消火設備(消火栓・スプリンクラー等)の資格

第1類消防設備士は、ビルなどの建物に設置されている水系消火設備(消火栓・スプリンクラー等)の点検や整備を行うことができる国家資格です。また、第1類消防設備士の資格は甲種・乙種に分かれています
消防設備士には多くの種類がありますが、第1類消防設備士は、甲種乙種併せて毎年約1万2千人前後が受験する人気資格です。
水系消火設備(消火栓・スプリンクラー)の設置にはルールがある
火災予防の対象となる「防火対象物」「特定防火対象物」って何?
「防火対象物」とは消防法で定められた建築物やその他の工作物、舟や車、山林などのことです。燃えやすい性質があるため、予防措置をする対象となります。その中でも「特定防火対象物」とは、不特定多数の人が出入りする施設や、病院・幼稚園など避難が難しい人のいる施設を指し、火災になった際に逃げ遅れる人が出るとも限らないため、さらに予防措置を取っておきたい施設、となります。
| 防火対象物 | 建築物その他の工作物もしくはそれに属する物、舟や車、山林など |
|---|---|
| 特定防火対象物 | 不特定多数の人が出入りする施設や、病院・幼稚園など避難が難しい人のいる施設 |
例えば屋内消火栓設備はどこに設置するの?
皆さんが利用する施設でも設置されている屋内消火栓設備。設置する場所を挙げたらキリがないほどあらゆるところに設置しますが、設置個所の一部をご紹介します。
| 延べ面積による設置対象 | 防火対象物により延べ面積が異なります。例えば映画館なら500m²以上、神社なら1,000m²以上など、細かく定められています。 |
|---|---|
| 地階・無窓階・4階以上で床面積による設置対象 | 防火対象物により床面積が異なります。例えば映画館なら100m²以上、神社なら200m²以上など、細かく定められています。 |
| 指定可燃物を貯蔵している防火対象物 | 防火対象物の種類に関わらず、一定数量以上の指定可燃物(わら、紙くずなど)を貯蔵している施設には設置が必要です。 |
まだまだたくさんありますが、ほんの一部です。屋内消火栓設備はあらゆるところで設置され、それを設置・点検する人もたくさん必要であることをご理解いただけたのではないでしょうか。
第1類消防設備士は消火栓設備やスプリンクラー設備の設置・点検が仕事

消防設備士乙種1類を取得すると消火栓設備やスプリンクラー設備の「点検」が、消防設備士甲種1類を取得すると「点検」に加え「設置工事」を行うことができます。
「消防法のルールに従って適切に設置されているか」「消火栓は正常に作動し古くなっていないか、部品に不備はないか」などを検査し、火災予防に努めるのが最大の任務です。
火災はいつどのような要因で起こるか分かりません。その際に火災を最小限に留め、建物内にいる人の安全を守る、重要な役割を担っています。
消防設備士甲種1類・乙種1類を取得するメリット
建物には欠かせない消火栓設備やスプリンクラー設備。消防設備士甲種1類・乙種1類を取得するメリットをご紹介します。
1
就職・転職に有利
特に消防設備会社、ビルメンテナンス会社では、取得必須となっている企業も多いため、転職時に取得しておくと有利になります。
2
収入UPに繋がる
企業内で資格取得奨励金などの対象となっている企業も多く、取得することで収入UPを見込めます。
3
やりがいのある仕事に就ける
人々の命を守る仕事である第1類 消防設備士の業務。消火栓・スプリンクラー等の点検や設置は第1類 消防設備士取得者だけに認められた独占業務であり、その使命はやりがいにつながります。
あわせて取得がオススメ!さらに活躍の場が広がり年収UPも狙える資格
第二種電気工事士
第二種電気工事士は、一般住宅や小規模な店舗など600V以下で受電する電気設備の工事・取扱いの際に必要な国家資格です。
消防設備の点検・整備に加えて、電気工事も担うことができれば活躍の場も広がります。第二種電気工事士にも受験資格がないのでチャレンジしやすく、さらに消防設備士の甲種の受験資格を得ることができ、さらに科目免除が受けられることも大きなメリットと言えます。
消防設備士 乙種4類・乙種6類
乙種1類と同様、受験資格がないためチャレンジしやすい資格です。
消防設備士乙種4類は火災報知設備など、乙種6類は消火器の点検・整備を行うことができる資格なので、乙種1類の消火栓やスプリンクラーなどに加えて仕事の幅が広がります。
消防設備士乙種1類からステップアップも!
-
消防設備士乙種1類を取得することで、消火栓やスプリンクラーの点検・整備を行うことができますが、さらに乙種4類や乙種6類を取得することで取扱いのできる設備が増えますし、さらに第二種電気工事士を取得すれば仕事の幅が広がり、より安定的に活躍することができ、年収UPも狙えるようになります。

デジタルパンフレットを閲覧する
資格の最新情報やTACのコースを掲載したパンフレットを、お使いのデバイスでいますぐご覧いただけます。
お申込いただいた場合、個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。
消防設備士甲種1類、消防設備士乙種1類 試験ガイド
消防設備士甲種1類の試験概要
受験資格・受験地・受験方式
-
試験方式
【筆記】マークシート(四肢択一)
【実技】記述 -
試験会場
全国47都道府県
-
試験日
都道府県により異なり月1回~3か月に1回程度
-
受験資格
あり(受験資格一覧参照)
甲種受験にあたっての受験資格一覧|消防設備士
-
資格または
実務経験(1)他の類の甲種消防設備士
(2)乙種消防設備士の免状を得た後、2年以上消防用設備の整備の経験を有する者
(3)技術士の第2次試験に合格した者
(4)電気工事士(第1種・第2種)
(5)電気主任技術者(第1種~第3種)
(6)消防用設備の工事の補助者として、5年以上の実務経験を有する者
(7)専門学校卒業程度検定試験(機械・電気・工業化学・土木または建築の部門に関するもの)の合格者
(8)管工事施工管理技士(1級・2級)
(9)高等学校の「工業」の教員職員免許を有する者
(10)無線従事者(アマチュア無線技士を除く)の免許を受けている者
(11)1級建築士または2級建築士
(12)配管技能士(1級・2級)
(13)ガス主任技術者
(14)給水装置工事主任技術者
(15)消防行政にかかる事務のうち、消防用設備等に関する事務について3年以上の実務経験を有する者
(16)消防法施工規則の一部を改正する省令の施行(昭和41年)の前において、消防用設備等の工事について3年以上の実務経験を有する者
(17)昭和41年前の東京都火災予防条例による旧制度の消防設備士 -
学歴
(1)次に掲げる学校において,機械,電気,工業化学,土木または建築に関する学科(課程)を修めて卒業した者
・大学,短大,高等専門学校(5 年制)
・高等学校または中等教育学校
・外国に所在する学校で,日本における大学,短大,高等専門学校(5 年制)または高等学校に相当するもの
・旧制大学,旧制専門学校,高等師範学校,実業学校教員養成所,旧制専門学校卒業程度検定試験合格者
(2)次に掲げる学校において,機械,電気,工業化学,土木または建築に関する関する科目を 15 単位以上修得した者(単位制ではない学校の場合は授業時間で換算)
・大学,短大,高等専門学校(5 年制),専修学校
・学校教育法第 134 条第 1 項に定める各種学校
・大学及び高等専門学校の専攻科
・防衛大学校,防衛医科大学校,水産大学校,海上保安大学校,気象大学校
・職業能力開発総合大学校,職業能力開発大学校,職業能力開発短期大学校,職業訓練大学校,職業訓練短期大学校,中央職業訓練所
(3)理学,工学,農学または薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士または博士の学位を有する者
問題数(筆記試験)
| 試験科目 | 項目 | 問題数 |
|---|---|---|
| 基礎的知識 | 機械に関する部分 | 6 |
| 基礎的知識 | 電気に関する部分 | 4 |
| 消防関係法令 | 共通部分 | 8 |
| 消防関係法令 | 第1類に関する部分 | 7 |
| 構造・機能・工事・整備 | 機械に関する部分 | 10 |
| 構造・機能・工事・整備 | 電気に関する部分 | 6 |
| 構造・機能・工事・整備 | 規格に関する部分 | 4 |
| 合計 | - | 45 |
問題数(実技試験)
| 試験科目 | 項目 |
|---|---|
| 鑑別等 | 5 |
| 製図 | 2 |
合格基準
| 筆記試験 | 各科目40%以上、全体で60%以上 |
|---|---|
| 実技試験 | 60%以上 |
試験の一部免除
他の類の消防設備士資格を持っている方は、以下の科目が免除となります。
| 持っている免状 | 免除科目 |
|---|---|
| 甲種第2・3類 |
・消防関係法令の共通部分(8問) ・基礎的知識(10問) |
| 甲種第4・5類 | ・消防関係法令の共通部分(8問) |
電気工事士・電気主任技術者・電気部門の技術士資格を持っている方は、以下の科目が免除となります。
| 持っている免状 | 免除科目 |
|---|---|
| 電気工事士 電気主任技術者 |
・基礎的知識の電気に関する部分(4問) ・構造、機能、工事、整備の電気に関する部分(6問) |
|
技術士 (機械または衛生工学部門) |
・基礎的知識(10問) ・構造、機能、工事、整備(20問) |
消防設備士 甲種1類合格コース開講中!
消防設備士乙種1類の試験概要
-
試験方式
【筆記】マークシート(四肢択一)
【実技】記述 -
試験会場
全国47都道府県
-
試験日
都道府県により異なり月1回~3か月に1回程度
-
受験資格
なし
問題数(筆記試験)
| 試験科目 | 項目 | 問題数 |
|---|---|---|
| 基礎的知識 | 機械に関する部分 | 3 |
| 基礎的知識 | 電気に関する部分 | 2 |
| 消防関係法令 | 共通部分 | 6 |
| 消防関係法令 | 第1類に関する部分 | 4 |
| 構造・機能・工事・整備 | 機械に関する部分 | 8 |
| 構造・機能・工事・整備 | 電気に関する部分 | 4 |
| 構造・機能・工事・整備 | 規格に関する部分 | 3 |
| 合計 | - | 30 |
問題数(実技試験)
| 試験科目 | 項目 |
|---|---|
| 鑑別等 | 5 |
合格基準
| 筆記試験 | 各科目40%以上、全体で60%以上 |
|---|---|
| 実技試験 | 60%以上 |
試験の一部免除
他の類の消防設備士資格を持っている方は、以下の科目が免除となります。
| 持っている免状 | 甲種1類受験時の免除科目 |
|---|---|
| 甲種第2・3類 |
・消防関係法令の共通部分(6問) ・基礎的知識(5問) |
| 甲種第4・5類 | ・消防関係法令の共通部分(6問) |
| 乙種第2・3類 | ・消防関係法令の共通部分(6問) ・基礎的知識(5問) |
| 乙種第4~7類 | ・消防関係法令の共通部分(6問) |
電気工事士・電気主任技術者・電気部門の技術士資格を持っている方は、以下の科目が免除となります。
| 持っている免状 | 乙種1類受験時の免除科目 |
|---|---|
| 電気工事士 電気主任技術者 |
・基礎的知識の電気に関する部分(4問) ・構造、機能、工事、整備の電気に関する部分(6問) |
|
技術士 (機械または衛生工学部門) |
・基礎的知識(10問) ・構造、機能、工事、整備(20問) |
消防設備士 乙種1類合格コース開講中!
消防設備士試験の申込方法
試験の申込手続は、郵便、もしくは、インターネットにて行います。
申し込み時に必要なもの、受験手数料、支払い方法、締切日などの手続きを確認しておきましょう。
正確な実施スケジュール・申込手続きは公式サイトをご参照ください。
消防設備士甲種1類、乙種1類の勉強方法
1,「基礎的知識(機械・電気)」は解ける問題から習得
基礎的知識(機械・電気)の科目はほぼ物理です。苦手な方は文字をみただけで目を覆いたくなるかもしれませんが、内容はパターン化されており、難易度も易しめなのでご安心を。 理解できる分野、解ける分野を強化することを目標としましょう。
2,「消防関係法令」「構造・設備・工事・整備」は問題を解きながらひたすら知識習得
「消防関係法令」はルールですので、ひたすら覚えていくことがカギです。テキストを見ても覚えられない方は、問題集を利用しながら覚えましょう。「構造・規格・工事・整備」は消火栓やスプリンクラーの仕組みなどについても学習します。「実技」とつながりますので併せての学習がオススメです。
3,「実技(鑑別)」は特徴を覚える
「実技(鑑別)」は画像から名称を答えるなど実物の問題が出題されます。百聞は一見に如かず。文章よりもテキストの画像を見て特徴を捉えるようにしましょう。実技を勉強することで、筆記の「構造・機能・工事・整備」の問題が解けるようにもなりますので早めの学習をオススメします。
4,「実技(製図)」はルールを覚えて練習あるのみ
「実技(製図)」は暗記が得意な方でも少々習得に時間がかかると言われています。系統図に図記号を記載する、系統図と与えられた条件から水量を計算するなど、ルールや計算方法を知らないと解答できない問題もありますので、まずは覚えることから始めましょう。筆記試験の学習知識が多く役立ちますので、後回しにせず同時に学習することをオススメします。
消防設備士甲種1類・乙種1類の合格率・難易度は?
試験実施状況|消防設備士甲種1類
消防設備士甲種1類の試験は、毎年1万人前後、消防設備士乙種1類も毎年2千人前後が受験している人気資格です。どちらも合格率も30%前後と、設備系資格の中ではやや難しめとなっています
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 12,086 | 2,914 | 24.1% |
| 2023年度 | 11,721 | 2,619 | 22.3% |
| 2022年度 | 11,482 | 2,719 | 23.7% |
| 2021年度 | 12,126 | 3,436 | 28.3% |
| 2020年度 | 9,949 | 3,104 | 31.2% |
| 2019年度 | 10,036 | 2,641 | 26.3% |
試験実施状況|消防設備士乙種1類
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 2,161 | 761 | 31.0% |
| 2023年度 | 2,137 | 602 | 28.2% |
| 2022年度 | 2,119 | 458 | 28.4% |
| 2021年度 | 2,143 | 761 | 35.5% |
| 2020年度 | 1,917 | 647 | 33.8% |
| 2019年度 | 2,169 | 571 | 26.3% |
まとめ
1
消防設備士第1類は、消火栓やスプリンクラー等の点検や設置の際に必要な国家資格
2
業務上必要で取得するケースが多く、「手に職」が身につく資格
3
試験はマークシートで特定の資格取得者は免除もある。しっかり対策すれば合格できる資格
TACの消防設備士講座
- Web通信講座ならスキマ時間でサクサク進む!
- ポイントを絞った効率的カリキュラム
- 豊富な問題演習量で合格を確実に!