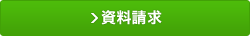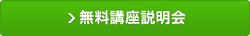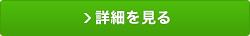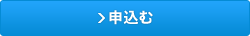電験二種2次試験 合格発表! 合格基準点・合格率・講師による試験傾向分析
令和7年度 電験二種2次試験の
合格基準・合格率
電気技術者試験センターより、令和7年度 第ニ種電気主任技術者試験の2次試験結果が発表されました。
合格基準点は100点満点換算で60.0点以上(実得点180点満点で108点以上)、かつ各科目ともに平均点以上と決定されました。
[二次試験]受験者数・合格者数・合格率
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|
| 3,692人 (昨年2,922人) |
611人 (昨年553人) |
16.5% (昨年18.9%) |
令和7年度 第ニ種電気主任技術者試験
2次試験 講師による試験分析
電力・管理科目 講評|令和7年度2次試験
計算問題は問2、問3のみで昨年に引き続き少なめでした。空欄穴埋問題が2.5問出題され、かなり難易度が高かったです。
近年の出題傾向として計算問題の比重が減少傾向にあり、より論述問題および知識問題への対策が重要となってきている印象です。
本年に関しては問1、問2、問4、問6はいずれも難易度が高く、問3および問5を選択した受験生が多かったと予想されます。この2問を確実に高得点できれば合格に大きく近づく内容であったと思われます。
また、太陽光発電をはじめとする分散型電源の増加に伴い、それに関連する出題が増えてきており、1種2種一次二次試験の過去問をどこまで深く掘り下げて理解していたかが問われる内容でした。
問1は水力発電所の劣化診断に関する空欄穴埋問題でした。
例年、水力は比較的易しめの計算問題が出題される傾向にありますが、今年は一昨年に続き知識を問う問題が出題され、難易度も高めでした。
電験の過去問での出題はほとんどなく、発電設備を扱う業務経験がある受験生以外は対応が難しかったと予想されます。
空欄穴埋形式であることから部分点も見込みにくく、選択した受験生は少なかったと思われます。
問2は対称座標法を用いた1線地絡事故時の計算に関する問題でした。
2種では令和2年度問3に対称座標法に関する問題はありますが割合としては非常に少なく、1種の平成24年問3まで学習を進めていた受験生ではじめて得点源となったと思われます。
1種平成24年の問題に比べれば計算量自体は少ないため、しっかりと理解していた受験生にとってはチャンスとなったかもしれません。
問3は百分率インピーダンスを用いた短絡容量計算の問題でした。
過去には平成29年問3、平成28年問6、平成24年問4等でも類題が出題されている頻出テーマです。 TACの講義でも扱ったことがある内容であり、受講生はぜひ完答したい問題です。
ただし計算量は多いため、計算ミスには十分注意が必要です。この問題を正答できるかは合否に大きく影響するものと思われます。
問4は太陽光発電も連系された配電線のループ切替に関する論述問題でした。
(1)の電流に関しては、令和6年問4や平成29年問4の計算問題からループ電流がどうなるかを考えると正答が想像しやすいかと思います。
(2)に関しては近年多い分散型電源連系時の挙動を論述させる内容であり、逆潮流を伴うことによる容量超過等に触れれば高得点が得られるかと考えられます。
問5は電路の絶縁に関する絶縁材料、法規および誘電正接測定試験に関する問題でした。
(1)の絶縁材料の問題は多くの受験生が正答できたと思います。
(2)の絶縁耐力試験は法規科目でも頻出、(3)の誘電正接は3種でも扱う内容であるため、多くの問題を学習していた受験生には得点しやすい問題でした。
絶縁耐力試験の空欄穴埋問題で出題された電気設備技術基準の解釈の該当箇所は必ず覚えておいて下さい。
問6は需給計画に関する空欄穴埋問題でした。
近年大きく変化している電力需給構造に関する内容で、時事的要素が強く、電験の参考書には一般に掲載されていない事項です。
常に最新の情報を収集している受験生でなければ対応が難しく、選択した受験生は少なかったと予想されます。
機械・制御科目 講評|令和7年度2次試験
同期機が4年連続で出題され、昨年まで2年連続して出題されなかった誘導機も出題されました。一方で変圧器の出題がありませんでした。
4問すべてが計算問題であり、どの問題を選択しても高得点は狙える構成であったため、計算ミスが合否を分ける要因となりそうです。
また、標準化された問題が多かったことから平均点が高くなることが予想され、平均点による足切りも考えられます。
問1は同期電動機の計算問題でした。
フェーザ図を用いて進める典型的な問題で、数値計算がないため記号を整理して解いていけば計算ミスも起こりにくい問題です。
後半の(5)の同期調相機の扱いはやや迷うかもしれませんが、それ以外は平易な内容でした。
問2はかご形誘導電動機のトルク・滑りに関する問題でした。
解法自体はよくある誘導電動機の問題なので、取り組みやすかった問題かと思います。(3)の滑りの計算が間違えやすい印象ですが、平成16年問1と酷似した問題であり、選択した受講生も多かったと予想されます。
問3は単相ダイオードブリッジ整流回路の問題でした。
例年のパワーエレクトロニクス問題と比較すると素直な出題であり、計算量も多くないため、動作原理を正しく理解していれば高得点を狙えた問題です。リアクトルやコンデンサを接続したときの挙動もTACでは扱っていたため、TAC受講生の選択率は高かったかもしれません。
問4はフィードバック制御系の伝達関数および定常偏差に関する問題でした。
自動制御の中でも出題されやすいパターンの問題であり、対策していた受験生も多かったと思われます。
ただし、伝達関数や部分分数分解、逆ラプラス変換等他の問題に比べると計算量が多く、途中計算を誤ると連鎖的に間違える可能性があるため、慎重かつ正確な計算が必要な問題でした。
Webセミナー
電験二種 2次試験対策
【電験二種】 2次試験対策 尾上講師が語る合格の秘訣
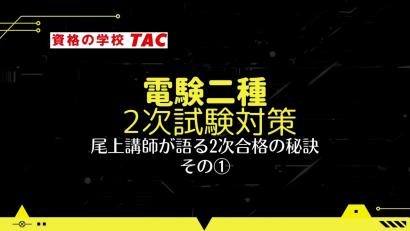
電験二種の2次試験対策についてみなさんの疑問にお答えします!
担当:尾上健夫講師<TAC電験二種講座講師>
<Part1>
0:23 2次科目の計算と論説の割合と対策方法
1:56 過去問+αの勉強が一番合格に近い?
2:12 1次の4科目の勉強は2次にどのくらい役に立つのか
3:28 1次と2次は同時に勉強したほうがよいのか
3:54 初学者の勉強期間は1年かかるのか
4:45 学習方法と学習計画の立て方
7:10 1次の理論・機械の選択問題、2次の問題選択方法
9:18 過去問への取り組み方
10:01 知識の増やし方、専門書は読むべきか
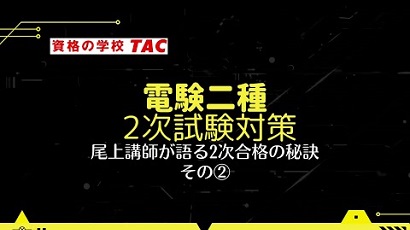
0:24 初見の問題に講師ならどう対応するか
1:24 機械制御のパワエレの勉強方法
3:08 独学でパワエレを勉強する場合の対応方法
3:51 1次は通るが2次で落ち続ける人の対処方法
6:01 計算力=数学力?
6:36 計算機の使い方が大事
7:16 数学力の上げ方
8:07 2次試験の記述答案は第三者に見てもらったほうがいいか
9:15 独学とスクールのメリット・デメリット
10:38 2次試験の総勉強時間
12:18 家庭や仕事との両立方法
14:23 完璧主義の解決方法
次こそは絶対合格!
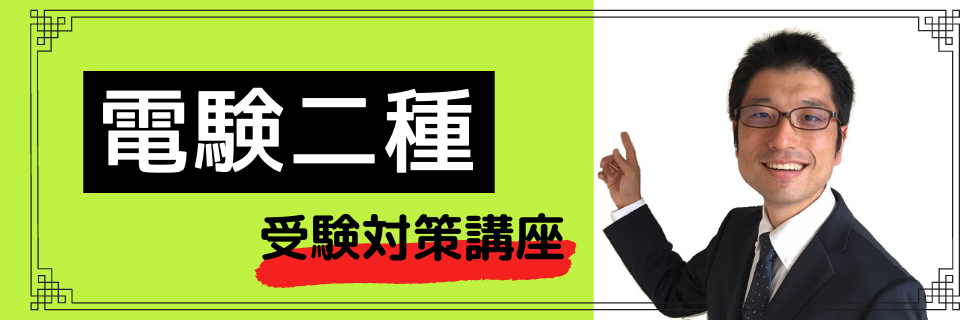
最強の電気主任技術者への道はすぐそこです。今年絶対合格!
1次試験を見事突破し、2次試験を目指す方へ。最強の「電気主任技術者」になるために、TACがお手伝いします!周りから一目置かれる存在になりましょう。
最強の電気主任技術者へ!令和8年度(2026年度)合格を目指す
電験二種 ストレート合格コース
-
コース内容
2026年(令和8年度)にむけて、1次も2次も対策するオールインワンコースです。
電験二種 1次合格コース
-
コース内容
電験二種の1次試験対策用コースです。理論や2次試験に必要な数学と各科目を学習します。
電験二種 2次合格コース
-
コース内容
電験二種の2次試験は苦戦者続出。TACでは過去問傾向を踏まえてしっかり対策します。
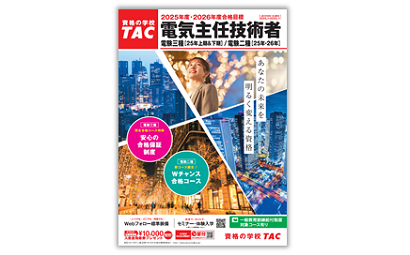
デジタルパンフレットを閲覧する
紙と同じ内容のパンフレットを、パソコンやスマートフォンから、郵送を待たずにいますぐご覧いただけます。
お申込いただいた場合、個人情報の取り扱いにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。
【参考】電験二種1次試験 受験者数/合格者数/科目合格者数
| 実施年度 | 1次受験者数(名) | 1次合格者数(名) | 科目合格者数(名) |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 7,211 | 2,524 | 3,493 |
| 令和6年度 | 7,479 | 2,159 | 3,416 |
| 令和5年度 | 6,318 | 1,545 | 3,442 |
| 令和4年度 | 6,189 | 2,178 | 3,048 |
| 令和3年度 | 5,979 | 1,539 | 2,736 |
| 令和2年度 | 6,235 | 1,695 | 3,050 |
| 令和元年度 | 6,915 | 1,633 | 3,388 |
| 平成30年度 | 6,631 | 1,600 | 3,089 |
| 平成29年度 | 6,570 | 1,737 | 3,450 |
| 平成28年度 | 6,521 | 1,456 | 3,007 |
| 平成27年度 | 6,418 | 1,557 | 3,255 |
| 平成26年度 | 6,676 | 1,595 | 3,261 |
| 平成25年度 | 6,452 | 1,550 | 3,018 |
| 平成24年度 | 7,034 | 1,748 | 3,522 |
| 平成23年度 | 6,659 | 1,047 | 3,542 |
| 平成22年度 | 6,786 | 1,549 | 3,395 |
【参考】電験二種1次試験 全科目合格率/科目合格率
| 実施年度 | 合格率 | 科目合格率 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 35.0% | 48.4% |
| 令和6年度 | 28.9% | 45.7% |
| 令和5年度 | 24.5% | 54.5% |
| 令和4年度 | 35.2% | 49.2% |
| 令和3年度 | 25.7% | 45.8% |
| 令和2年度 | 27.2% | 48.9% |
| 令和元年度 | 23.6% | 49.0% |
| 平成30年度 | 24.1% | 46.6% |
| 平成29年度 | 26.4% | 52.5% |
| 平成28年度 | 22.3% | 46.1% |
| 平成27年度 | 24.3% | 50.7% |
| 平成26年度 | 23.9% | 48.8% |
| 平成25年度 | 24.0% | 46.8% |
| 平成24年度 | 24.9% | 50.1% |
| 平成23年度 | 15.7% | 53.2% |
| 平成22年度 | 22.8% | 50.0% |
【参考】電験二種1次試験 各科目合格基準点
| 実施年度 | 理論 | 電力 | 機械 | 法規 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 令和6年度 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 令和5年度 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 令和4年度 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 令和3年度 | 54 | 51 | 54 | 54 |
| 令和2年度 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 令和元年度 | 51 | 53 | 53 | 50 |
| 平成30年度 | 49 | 52 | 52 | 52 |
| 平成29年度 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 平成28年度 | 50 | 50 | 50 | 47 |
| 平成27年度 | 42 | 51 | 50 | 51 |
詳細は試験センターHPをご確認ください。
一般社団法人電気技術者試験センター https://www.shiken.or.jp/index2.html