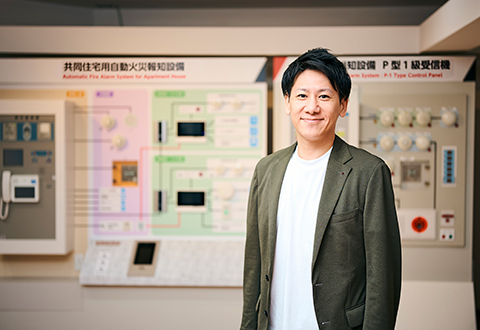日本のプロフェッショナル 日本の不動産鑑定士

雨宮 竜介(あめみや りゅうすけ)氏
アンビ株式会社 代表 不動産鑑定士 中小企業診断士
1980年、東京都生まれ。大学中退。公務員採用試験(東京都特別区)に敗れ、不動産業界に入る。不動産賃貸、売買仲介、リーシング業務、プロパティマネジメント業務、企画業務等、約10年間従事。2012年、不動産鑑定士試験合格。合格後、大手不動産鑑定会社に11年間勤務。その間に中小企業診断士資格を取得。2023年6月、アンビ株式会社を設立。同年9月、独立開業。
自分で時間を自由にコントロールできることは、
人生を豊かにします。
そのひとつの手段として不動産鑑定士という国家資格は
とても有効です。
32歳で不動産鑑定士試験に合格、2年間の実務修習を経て34歳で不動産鑑定士登録。43歳で独立開業した雨宮竜介氏は、開業1年目で1,000万円を売り上げた。開業して間もなく2年、「将来的には個人事務所で売上高3,000万円の世界に行く」と抱負を語る。「両利きの経営」を掲げる雨宮氏に、不動産鑑定士になった経緯と開業のきっかけ、中小企業診断士資格取得、今後の目標と課題についてうかがった。
公務員試験に敗れ不動産業界へ
まじめでテストの点もよい優等生だった雨宮竜介氏。ただし、それはヤンキー漫画にハマる中学2年生までのこと。
「ヤンキーは目立つしカッコいい。いつも中間・期末テストでよい点を取っている自分がダサく見えてきて…。そこから勉強が好きでなくなったんです」
学力も中程度まで落ち、その学力で入れる都立高校に進学。高校1年生でバイクの免許、18歳になると車の免許を取得し遊んでばかりいた。当然、大学への進学などまったく考えていなかった。
「浪人して予備校に通いましたが、友だちとつるんで遊んでばかり。大学受験はしましたが、受かる気はゼロでした」
それでもなんとか大学に入ったものの友人とソリが合わず、半年で中退。宅配ピザ屋のアルバイトを続けながら麻雀、パチスロ三昧の日々を送っていた。
そんな雨宮氏の人生の転機は、バイト先で彼女ができたことだ。
「バイトのままじゃいけないと奮起して、東京都特別区の公務員採用試験を受験しました。試験勉強は結構自分に合っていたようで、筆記試験は合格。でも面接は不合格でした」
このままでは一般企業にも入れない。どうしようかと悩んでいるとき、知人から「不動産業なら高卒でも入れる」と聞いたことが、不動産業界に足を踏み入れるきっかけとなった。
独立といえば不動産鑑定士
雨宮氏が不動産賃貸会社に入社したのは23歳のとき。すると、まず宅地建物取引士資格を取得するように言われた。その会社では週1回、受験者に勉強を教えるためにOBが来てくれた。
「その方が不動産鑑定士(以下、鑑定士)でした。そこで初めて鑑定士という資格を知りました。その方がいずれ独立するといっていたので、『独立といえば不動産鑑定士』という意識がすり込まれたんです」
不動産賃貸会社に3年間勤務する中で「売買もやってみたい」と思うようになった雨宮氏は、横浜の不動産会社に転職。店長として売買にも携わった。その会社に5年半勤務している間に「将来的には独立したい」「日本全国を出張して回りたい」という思いが湧いてきた。そのとき浮かんだのが鑑定士だ。
鑑定士について調べてみると「難関国家資格で、簡単な試験ではない」とある。「それでも不動産鑑定士になりたい!」と雨宮氏は強く思った。
1回目の短答式試験は仕事の傍ら独学で受験。結果は1、2点不足で不合格だったが、1年間受験に専念すれば合格できるという感触はつかめた。そこで仕事をやめて受験に専念することにした。ただし期間は1年間。1年分の貯蓄を確保して「とにかく1年間全力でやろう!」と、TACの不動産鑑定士講座1年コースへ。勉強中は短答式の全答練(全国公開模試)で1位を獲得。論文式の全答練も最後は3位まで上り詰めた。
「自分ができるというより、1年目の自分のように受験生は働きながらの社会人がほとんど。専念している自分は自信を持って試験に臨めました」
2012年、雨宮氏は不動産鑑定士試験に一発合格を果たした。

名古屋で鑑定士のDNAを授かる
雨宮氏が鑑定士試験に合格したのは32歳。当時の不動産鑑定業界は就職氷河期で「30歳を超えたら大手3社には入れない」といわれていた。TACの合同就職説明会を経て、なんとか大手の1社の面接にはこぎつけたが結果は不採用。そんな中、雨宮氏に興味を示して面接をし、説明会の場で内定を出してくれたのが株式会社三友システムアプレイザル(以下、三友)だった。こうして三友に入社し、雨宮氏は鑑定士の一歩を踏み出した。
三友は他の鑑定事務所とは異なるアプローチをしており、自社で鑑定を受け社内で鑑定評価を行うのではなく、提携する全国の鑑定士に鑑定評価自体は委託していた。上がってきた鑑定評価書をクライアントの意向を踏まえた不動産鑑定評価書に仕上げて提出するのである。さあ、鑑定評価をするぞ、と意気込んでいた雨宮氏は肩透かしをくらった。ただ、クライアントの要望をきちんと聞く経験や、営業から受付、見積、受注、発注、調整、説明、納品という不動産鑑定評価のプロセスをひとりで担当したことは、独立後に活きているという。
入社から10ヵ月後、東京本社から名古屋支店に異動。雨宮氏は妻と生まれたばかりの娘を連れて名古屋に向かった。名古屋支社は東京本社に比べ、ゆったり仕事ができる環境にあった。
「案件1件1件にしっかりと向き合えました。ときには外部鑑定士との協業もあり、実務を教えてもらえました。何より実務修習の指導鑑定士が厳しい方で、鑑定に真摯に取り組めと徹底的に叩き込まれました。鑑定士のDNAはその方から伝授されたんです。名古屋で鑑定士の基礎と鑑定実務を身につけられたのは大きな財産です」
中小企業診断士資格取得でダブルライセンスへ
名古屋では、民事再生やM&A案件でコンサルティング会社と連携する機会も多かった。ただし、鑑定士は不動産鑑定評価書を出すだけ。そのあと、案件の進捗があったとしても、呼ばれることはなかった。
「コンサルティング会社は、不動産に関して造詣が深くない印象です。不動産鑑定評価書を出して終わりじゃないのになぁ。私たちをプロジェクトに入れてくださいとも言えず、モヤモヤが募っていきました。そのころには独立を意識していたので、鑑定と経営コンサルティングが一緒にできたらおもしろいし、役に立ちそうだとひらめきました。それなら中小企業診断士(以下、診断士)とのダブルライセンスにすれば大きな武器になると考え、診断士資格取得をめざしたんです」
診断士1次試験はTACの教材で勉強したが、全答練では1度も合格点に届かなかった。しかし、見事に本試験では合格。雨宮氏は2次試験ではなく、1年間の養成課程を経て診断士資格を取得した。

追い風が増えて独立へ
名古屋支店時代、診断士資格を取得した雨宮氏はすぐに独立したいと考えていた。ところがそのタイミングで東京本社に異動。東京本社でついた上司は寛容な人で、現地視察も許可してくれたし、不動産鑑定評価書も自分で書いて学べという方針だった。
「難解な案件は委託先の鑑定士と直接会って一緒に評価をしました。ですから北海道から沖縄まで全国出張させてもらい、のびのびと仕事をしました。全国制覇を狙いましたが秋田、鳥取、島根には行けませんでした(笑)」
東京に戻って半年で独立するつもりだった雨宮氏は、その上司のためにもう少しだけと、気づいたら4年経過していた。
もうひとつ、独立を踏みとどまった理由がある。東京に戻ってから、腹膜偽粘液腫という大きな病気が発覚したことだ。大きな手術を受けることになったとき三友から最大限のサポートを受けた。恩返ししながらも独立の思いは消えなかった。治療を進めると主治医から「やりたいことをやって大丈夫。独立?いいじゃない。不動産の買いどきとか教えてね(笑)」とお墨付きをもらえるほど回復した。
予定より時間はかかったが、独立するなら多摩地区がいいと雨宮氏は考えていた。
「独立したら三友との変わらぬお付き合いも決まっていたので、適度に田園風景があって仕事ができる環境を考えました」
鑑定士は自宅開業が多い中、雨宮氏は通勤時間も欲しかった。そんなとき立川で内覧した事務所に一目惚れ、会社設立前に即決した。
「妻にはプレゼン資料を作って、独立の話をしました。機嫌がよかったのか、それとも私の本気度が伝わったのか、資料を見る前に『いいんじゃない』と言ってくれました。追い風が増えた。いろいろな環境が自然に整っていった感じでした」
2023年6月、雨宮氏は43歳でアンビ株式会社を設立、9月18日に開業した。
「両利きの経営」で開業
開業に際して雨宮氏が掲げたのは、「両利きの経営」だった。「両利きの経営」とは主力事業の絶え間ない改善(深化)と新しい領域へのチャレンジ(探索)を同時に実行することだ。
「私自身、不動産鑑定は利き腕で得意分野(深化)。診断士もうまく使えるようになって利き腕(探索→深化)になれば、両利きになる。そして、また違う何か(探索)ができるのではないかと考えたのです」
開業後、もっとも多いのは三友からの委託業務だった。安定的でコツを掴めば効率的に稼げるので、収入のベースになる。その他同業者からもかなりの依頼が来た。
「もちろん開業したからには自分で受託する仕事を増やしたいので、がんばりました。結果、2期目はかなり増えたので、今後も直受けの仕事を増やしていきたいですね」
一方、委託業務も、個人では経験できない大企業の不動産評価に出会える魅力がある。例えば、ホテルやゴルフ場の評価などは、個人事務所ではなかなか携われない。そこに携われるのは、鑑定士としてのよい経験になっている。
診断士は「伸び代」
雨宮氏は、開業してからX(旧:Twitter)で自分の売上を毎月公表している。
「自分が独立するときに、一番知りたかったのは売上です。でも、どの開業鑑定士に聞いても、売上だけは教えてくれませんでした。そこで良いときも悪いときも、包み隠さず公表したいと思っています」
雨宮氏は2024年秋、一般社団法人桃太郎オフィスを経営する不動産鑑定士YouTuberの中瀬桃太郎氏と共同代表の泰道征憲氏が展開するYouTubeチャンネル「士業の成功レシピ」に出演している。そこでも「初年度の売上は1,000万円、2期目は4ヵ月で前期を超えたので1,800万円までいきたい」と具体的に話している。同業者からは「売上公表なんて、すごいことやるね」という声が寄せられた。
「個人で成功している人が売上5,000万円超。私も将来的には3,000万円の世界に行きたい」と、将来の抱負も具体的なのが雨宮氏らしい。
仕事に加え、雨宮氏は愛知県と東京都で不動産鑑定士協会の活動をしてきた。東京では業務推進委員会を経て広報委員会に所属。当時の会長の目に留まり、2年間理事も務めた。
「協会活動は本当にボランティアなんですが、ネットワークが広がることはとても大きいと考えています」
一方、診断士資格は思うように活用できていないようだ。
「今まさに5年目の更新を迎えているのですが、診断士の実績はほぼゼロです。ただ名古屋時代の同期で東京進出したいという人が何人もいるので、事業の立ち上げや軌道に乗るまで、あるいはそれ以降も経営相談に乗る計画を、今一緒に考えています」
診断士資格を取得してよかったことはふたつ。ひとつは学習を通じて経営者マインドを学べたこと。もうひとつは養成課程で5社の中小企業に訪問し、実際に経営者に会い、現場を見て、診断士としての提案をしたことだ。
「独立後もそのときの経験が役立っています。診断士仲間から鑑定依頼を受けることもあるので、診断士の領域はよい意味で自分の伸びしろになると思っています」
目標は次世代の担い手を増やすこと
間もなく開業3年目を迎える雨宮氏は、今後の目標についても具体的に考えている。
「実は持病が再発し、2025年の年明けから治療を始めています。通院や治療の副作用があるので、当面は現状維持が目標ですね。それでも普通に仕事ができて、きちんと家族のためにお金も稼いで、社会の役に立っている。それは鑑定士資格があってこそということを、きちんと伝えたいと思います。
今できることを着実にやっていく。そして今後の生活が見えてくるまで地に足をつけて、できることをできるところまでやっていきます」
鑑定士業界の喫緊の課題である「次世代の担い手を増やすこと」にも取り組んでいる。
「特に若い受験生を増やしたいですね。2〜3年以内に実務修習の受け入れ先として私が指導鑑定士を務めて、鑑定士になるまでサポートしたいです」
将来の選択肢を考えている高校生、大学生には「ぜひ学生時代から鑑定士をめざしてほしい」と、雨宮氏は強調する。
「学生で鑑定士受験する人は決して多くないので、ライバルが少ない。合格率は低く見られがちですが、実はライバルになる分母の多くは社会人で働きながらという方なので、専念できる環境であれば合格率も見た目よりもっと高いと思います。セカンドライフをお考えの方にも、40〜50代で鑑定士を取得して定年後独立するのはおすすめです」
学生のUターン就職やリタイア後に地元に帰って仕事をしたい人にとっても、鑑定士の資格取得は大きなメリットがあるという。
「地方でも公的な地価公示、地価調査、固定資産税評価、相続税路線価評価の仕事があります。地方なら民間の案件がなくても、これだけで十分生活ができます。しかも、この4つに関しては、特別な営業もいりません。要件を満たしてきちんと書類を出せばいいのです」

伝えたいのは「独立鑑定士の魅力」
独立後、平日の休みは趣味のゴルフ、土日も急ぎの仕事がなければ家族と一緒に過ごせている。
「開業1年目は休みが取れないと言われますが、そんなことはありません。よく休んでいるし、朝ものんびりです。本当に自由な時間の使い方ができて、自分に合っています」
若い世代には、独立鑑定士の時間の自由さを伝えたいという。
「鑑定士は楽な仕事ではありません。でも稼ぐことができます。どんなに急ぎでも『今日中に納品』なんてことはありません。1ヵ月以内に自分でコントロールして終わらせればいい。時間を自分でコントロールできることは、人生を豊かにします。そのひとつの手段として、鑑定士は非常に有効です」
雨宮氏が「鑑定士を増やすこと」にこだわるのは理由がある。
「次世代の担い手がいないと、4つの公的評価を担う人がいなくなります。そうなったときに『AIでいいんじゃないか』といった議論になりかねない。4つの公的評価を担う鑑定士の絶対数が必要なんです」
鑑定士の魅力を世の中に発信し、少しでも担い手を増やしたいと雨宮氏は切に願っている。
[『TACNEWS』日本のプロフェッショナル|2025年5月 ]