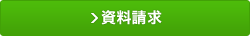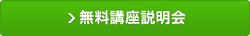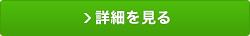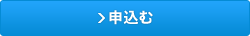一級建築士試験 合格者座談会
今年も開催しました!(2026年1月開催)
TACを使って見事合格された5名の方をお招きし、合格までのそれぞれのストーリーをお話しいただきました。【2025年実施試験 合格者】

一級建築士 合格者座談会 参加者
岩田 尚之 (いわた なおゆき)さん(総合学科本科生・設計製図本科生)【ストレート合格】
岡崎 英伴 (おかざき ひでとも)さん(総合学科本科生・設計製図本科生)【ストレート合格】
河村 明澄(かわむら あすみ)さん(総合設計製図本科生)【一発合格(1年目学科・2年目設計製図)】
本澤 梨音(ほんざわ りおん)さん(総合学科本科生・設計製図本科生)【ストレート合格】
簗瀬 未佑 (やなせ みゆ)さん(総合学科本科生 井澤Plus・設計製図本科生)【ストレート合格】
井澤 真悟(いざわ しんご)講師
清田 和歳(せいた かずとし)講師
建築士講座 デジタルパンフレットを閲覧する
1.一級建築士を目指した理由
──(井澤) 皆さん、合格おめでとうございます。今回の設計製図試験では、TAC本科生の方の45.5%※、約2人に1人が合格をされました。これは、本試験合格率35.0%より10ポイント以上高い素晴らしい数値です。まずは一級建築士を目指した経緯を教えてください。
岩田 行政機関で図面を審査する仕事をしています。今後のキャリアのために勉強しておきたいと思い目指すことにしました。
岡崎 建築業界で働く父の背中を見て育ち、工業高校、建築系の専門学校を卒業しました。その集大成として資格を取りたいと思い、一級建築士に挑戦することにしました。
河村 現在大学院の2年生です。大学の学部でも建築を学んだのですが、院卒枠で就職活動をするにあたって「建築の専門家として自信を持ちたい」と思い取得を目指しました。
本澤 一級建築士は、今後建築の分野で働くうえで欠かせない資格であり、将来にわたって建築に関わり続けるためにも、できるだけ早い段階から挑戦したいと考えていました。そのため、主体的に学ぶ姿勢を大切にし、自ら行動を起こすことを選びました。
簗瀬 設計事務所に勤務しています。上司や先輩で一級建築士を持っている方が多く、業務に直結する資格なので、若手のうちに取っておきたいと思い受験を決意しました。
※TAC本科生カリキュラム修了者とは、2025年合格目標TAC本科生コース(一級総合設計製図本科生、一級設計製図本科生)を受講され、講義出席率(講義視聴率)9割以上かつ当年度課題発表後の本課題の提出率9割以上を達成された方を指します。なお、当合格率は上述のTAC本科生カリキュラム修了者459名中、合格者209名の割合で算定しています(受験番号不明者・未受験者は「不合格」としてカウントしています)。

2.TACを選んだ理由――予習不要、ストレート合格が狙えるカリキュラムは他にない強み
──(井澤) 受験にあたって、数ある資格学校の中でTACを選んだ理由と、利用して感じたことを教えてください。
岩田 「やるからには一年で受かりたい」と思っていた時に、大学時代からの知人がTACで一級建築士にストレート合格したと耳にし、自分も続こうと思って選びました。実際に講義を受けてみても、短期間で効率的に勉強できるカリキュラムが組まれていると感じました。
河村 学科はみなさんとは違って、スクールに通わず勉強したのですが、その時からTAC建築士講師室ブログ内にある井澤先生のたくさんの記事に助けられていました。それで、設計製図からはTACで対策することにしました。
──(井澤) ブログは独学の方にも必要な情報を意識して載せているので、活用していただきうれしいです。現在は井澤式比較暗記法[法規編]も新たに執筆中です。合格後も参考になると思いますので、ぜひ引き続きお読みください。
岡崎 私も井澤先生のブログ「井澤式比較暗記法」を読んでわかりやすさに驚き、TACに通いたいと思いました。予習が不要というのも魅力的で、脳がクリーンな状態で講義を聴くことができるので理解もスムーズだと感じました。
本澤 二級建築士の受験をきっかけに、コストパフォーマンスの良さや、問い合わせ時の丁寧な対応に魅力を感じ、TACに通い始めました。実際に学習を進める中で、講義の分かりやすさと課題が明確に示されている点が自分に合っており、やるべきことに迷うことなく学習を継続することができました。その経験から、今年度の一級建築士についても、引き続きTACで挑戦することを決めました。
簗瀬 他のスクールと比べて価格が抑えられることと、先輩や知人でTACに通っている方が多く、ひとり一人にきちんと目を向けて指導してくださると話を聞いていたため、選びました。

3.学科対策について――「Webトレーニング」で通勤中に効率よくインプット、タイムパフォーマンスの高い学びが実現
──(井澤) 学科試験はどのように対策されましたか。おすすめの勉強方法や工夫した点を教えてください。
岩田 5科目の中では施工に苦戦したため、施工に力を注ぎました。スキマ時間を無駄にせず、通勤電車の中で項目別問題集のモバイル版「Webトレーニング」を解いていました。正答率も出るので、非常に効率よく学習できました。
岡崎 TACでは豊富な具体例や模型などを使って講義をしてくださるので、覚えることが苦になりませんでした。毎週の講義後の確認テストの解説もわかりやすく、間違いやすいポイントが一目瞭然。さらに私の場合は法規の新傾向問題が苦手だったのですが、GWに開催されたオプション講座(法改正出題予想講座、法規「告示」出題予想講座)を受講したことで安心して本番を迎えることができました。
本澤 TACで先生がおっしゃることを”真に受けて”勉強するようにしていました。「これくらいやらないと受からない」と言われたらその量をやる、「この問題集を一周する」と言われたらただやるのではなく、自分の中に使える知識として深掘りする一周を心がけました。
簗瀬 大学と大学院で建築を学んできたはずなのに、勉強開始当初は何もわからず「すべてが苦手科目」という状態。そこで、講義は毎回必ず出席して復習するようにしました。また、朝起きて30分、電車の中で30分、お昼休憩中の30分、帰りの電車の30分勉強すると、1日2時間確保できるので、それを毎日繰り返していました。
──(井澤) みなさんに共通していて特に印象深いのは「スキマ時間の活用」です。現在TAC一級建築士講座では通学とWebに加えて、両方のいいとこ取りともいえるオンラインライブクラスも開講しています。これから一級を目指す方に検討していただきたいです。
4.設計製図対策について――「ひとつひとつの目的が明確な、厳選された教材だった」
──(清田) 設計製図対策はいかがでしたか。取り組んでみた感想や講義中に印象に残ったことを教えてください。
岩田 私が習った先生は、エスキスをグループでディスカッションしながら進める方でした。自分の描いたものを見せることに最初は戸惑いましたが、他の受講生のエスキスも見ることで複数の視点や解き方があることがわかり、結果的に短期間で力がつけられたと感じます。教材に関しては基本の9課題に加え、応用課題に取り組むことで自分の中で「こういうやり方もあるのか!」と幅を広げることができました。
岡崎 学科も設計製図も本試験の内容に沿った講義内容なので、完全に信頼して勉強を進めることができました。私も岩田さんと同じように、応用課題まで手を広げることで「基本課題と似ているけれど、アプローチのとり方でこんなにもプランが違うんだ」と実感することができました。
河村 手を動かすことが苦手なタイプで、初めての製図(作図)には戸惑いました。最初は周囲の経験者の中でついていけない状態でしたが、講師がエスキスからしっかり指導してくださり、時間配分のコツもアドバイスくださったことで図面を描ききるスキルと体力を手に入れることができました。特に、同じ課題を2回繰り返すことで(課題のリトライ)、何を選択すれば後々どんな状態になるかを少しずつ判断できるようになったことが大きな収穫でした。
本澤 TACは当年度課題が9課題なので最初は少ない気がしましたが、内容が濃い上に毎週同じ課題を最低2回は繰り返すので「やることがない」というタイミングが発生しませんでした。それと、ありがたかったのは「クラス振替出席フォロー」です。自分の通っている校舎以外でも受講できて「どんどん質問してね」「あなたの先生はここをどう教えているの?」などと温かく声かけして迎えてくださったのがうれしかったです。
簗瀬 私の通っていた校舎では4人の先生方に教わることができました。軸が統一されているので混乱することなくいろいろな考え方を吸収できました。他のスクールに通っている同期の教材を見せてもらったことがあるのですが、課題が多すぎて消化が難しい印象を受けました。TACの課題は限られていますが、一つひとつにしっかりと目的があることがわかるので、ただ信じてやればいいと思えましたね。
──(清田) TACの「厳選した課題を繰り返し、完全に消化するTAC式学習法」が年々浸透していっているのを感じますね。また、設計製図の学習がはじめての方でも安心して本科講座を受講していただけるように、オプションの「プレ特訓講座」というのもご用意していますので、チェックしていただきたいです。

5.今後の展望
──(清田) 一級建築士を取得したことで、心境やお仕事の変化はありましたか? 今後の展望についてもお聞きしたいです。
岩田 ただ情報を出し入れするのではなく、法律や図面から背景を読み取ることが重要だと実感できるようになりました。これから、業務の要件である建築基準適合判定資格者検定に向けてまた勉強を重ねていきたいです。
岡崎 現在は内装の仕事をしているのですが、一級建築士であるという責任感を持ってこれまで以上に熱心に業務に当たりたいと思います。将来的にはさらに視野を広げ、専門性の高い一級建築士になれたら、と考えています。
河村 4月から建設会社に就職が決まっているので、まずは2年間の実務経験を着実に積んでいきたいと思います。引き続き勉強は必要ですが、一級建築士に合格したことで自信を持って社会人生活を始められそうです。
本澤 今後は、実務の中で多くの経験を積みながら、建築に対する理解を深めていきたいと考えています。一級建築士としての自覚を持ち、日々の業務に丁寧に取り組んでいきたいです。
簗瀬 合格したことで、より責任感のある仕事をしていきたいと感じます。得た知識やスキルを活用し、お客様の暮らしに寄り添う建物を作っていきたいです。
6.これから受験する方へのアドバイス
──(清田) 最後に、一級建築士合格を目指す後輩にアドバイスをお願いします。
岩田 設計製図の課題に取り組むときは、ただ単純に与えられた条件をうまく当てこむだけではなく、自分が将来一人の設計者として発注を受けたという想定で臨んでみるといいと思います。「本当の仕事なんだ、自分が建てる建物だ」と思うと真剣度が違ってきます。
岡崎 難しい試験なので、くじけそうになることもあると思います。私の場合は、講師の手厚いサポートで続けることができました。困ったらすぐにTACを頼りましょう。また講師からの「これがいいよ」というちょっとしたアドバイスも大きな助けになりますので、柔軟に取り入れるのがおすすめです。
河村 設計製図からTACに入った私ですが、想像以上に居心地がよく、楽しく通学することができました。ひとり一人の勉強スタイルやニーズに合わせて融通がきくのがTACのいいところなので、ぜひ活用して合格をつかんでほしいです。
本澤 学科も設計製図も、先生方のおっしゃることを素直に実行することで合格に近づく試験だと思います。本試験に出ないものは本当にTACではやらないので、信じてついていってください。
簗瀬 学科は間違いノートを作ってプライベートでも持ち歩き、設計製図はA4サイズの方眼ルーズリーフを横に使って電車の中でもエスキスをするなど、場所を選ばず勉強したことも結果につながったと思います。TACの教材と講師は素晴らしいの一言に尽きるので、一年間がんばってください。
──(井澤) 皆さん、貴重なお話をありがとうございました。一級建築士を目指す方は、これから、ぜひ一緒にがんばっていきましょう。

いまから始めるならこのコース!
[学科対策]令和8年向け(2026年受験)
| 冬割e受付クーポン22,000円OFF(2月末まで) 受験経験者割55,000円OFF [開講]2026年1月開講 |
年明けからはじめる方向けのベーシックコース 万全なカリキュラムで一発合格を目指す、一級学科のベーシックコースです。年明けからはじめる初学者・受験経験者の方におすすめです。 [冬割e受付クーポン受講料]¥407,000(教材費・税込) |
|---|
| 冬割e受付クーポン22,000円OFF(2月末まで) 受験経験者割55,000円OFF [開講]2026年3月開講 |
【経験者向け】インプット講義を従来の約4割に厳選!タイパ重視コース 受験経験者向けの厳選インプット重視カリキュラムを新設しました。インプットの負担を最小限にして演習時間を確保したい方、必要なテーマだけポイント学習したい方、まとまった学習時間をとりにくい多忙な方におすすめのコースです。 [冬割e受付クーポン受講料]¥264,000(教材費・税込) |
|---|
| 冬割e受付クーポン22,000円OFF(2月末まで) 受験経験者割55,000円OFF [開講]2026年4月開講 |
【経験者向け】合格まであと一歩の受験経験者向け!演習中心の実戦コース 目安として本試験で80点前後の方向けのアウトプット重視カリキュラムです。受験経験者向けに合格者と不合格者の差が付く問題を厳選し、演習と解説講義を繰り返しながら、実戦的に得点力アップを図ります。 [冬割e受付クーポン受講料]¥275,000(教材費・税込) |
|---|
| 冬割e受付クーポン22,000円OFF(2月末まで) |
【学生向け】1年分の受講料で、大学(院)卒業年まで何年でも継続受講できる 令和2年からは大学卒業後すぐに一級建築士を受けられるようになり、大学生のうちから学習を始める方が加速度的に増えています。TACなら、費用負担は最小限で、大学1~4年生、院生まで、どの学年からでも学習を始められます。どうせやるなら早くから始めていきましょう。 [冬割e受付クーポン受講料]¥440,000(教材費・税込) |
|---|
[設計製図対策]令和8年向け(2026年受験)
|
早割11,000円OFF(2月末まで) 定員になり次第、受付終了 [開講]2026年3月開講 |
課題発表前から始める方向けのコース 課題発表前にプランニングの基本や作図の方法を学び、その後「設計製図本科生」に合流するコースです。課題発表後は短期決戦となりますので、余裕のある時期に基本を身に付けておきたい方におすすめです。 [早割受講料]教室・オンラインライブ¥462,000 Web通信¥385,000(教材費・税込) |
|---|
|
学科コースとの同時申込で22,000円OFF [開講]2026年8月開講 |
学科試験後から製図対策に着手するスタンダードコース 毎年多くの合格者を輩出している設計製図コースです。余計なことはやりません。プランニングから製図完成まで、合格レベルの設計力を基本から養成します。 [通常受講料]教室・オンラインライブ¥341,000 Web通信¥264,000(教材費・税込) |
|---|