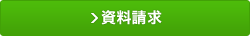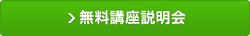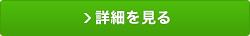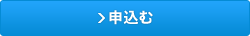合格者が語る!企業経営アドバイザーの魅力
中神 正康 さん
★資格取得者★

中神 正康 さん
研究機関勤務
企業経営アドバイザー
Web通信講座|フルパックコース受講
2025年検定試験合格
学んだ知識を活かし、経営的な視点でも経営者と対話をしながら
サポートしていきたい!
企業経営アドバイザーを受講された理由は?
私は水産業に関する研究機関に勤めており、養殖業は事業性評価により経営実態の評価が行われていることを知って、事業性評価に興味を持ちました。その後、企業経営アドバイザーの資格を取得することで事業性評価を学ぼうと考えました。
認定機関である日本金融人材育成協会のウェブサイトで紹介されていたTACの講座受講が合格への最短距離だと判断し、受講を決めました。
事業性評価の知識を身につけたかったこと、また、様々な水産関連業者の社長と打ち合わせをする機会が多いのですが、研究者である私には不足している経営上の対話ができるようになりたいと考えたことも、受験した理由です。
選択したコースと受講した感想をお聞かせください。
Web通信講座のフルパックコースを受講しました。「企業財務」と「事業性評価」を担当されていた講師は、実務の例などを盛り込んで、非常に分かりやすく、楽しい講義でした。また、苦手であった「企業法務」も講師の説明を何度も聴講することで苦手意識を軽減できました。
1回30分程度の講義は、短時間で受講しやすかったです。合格した結果から見て、テキストもトレーニングも必要事項がコンパクトにまとめられており、効率的な学習ができる内容でした。紙媒体のトレーニングとWebトレーニングを2回以上行い、間違わなくなるまでマスターすれば、試験で十分合格点を取ることができます。
知識科目4科目のテーマ数は多いですが、1単位は短時間で受講できるので、忙しい人でも少しずつ進めることができる、非常に良いカリキュラムだと思いました。事例問題については、もう少し練習問題があった方が良いと感じました。事例問題をこなしたかったので、公開されているサンプル問題を行い、TACの解説も活用しました。
また、実力テストも時間を計測して活用しました。CBT試験そのままというわけにはいきませんでしたが、実際の試験とレベル的には差はないように思いました。実力テストをこなすことができれば、本試験でも合格点は獲得できると思いました。
「事業性評価」を学習することが企業経営アドバイザー取得の目的でした。この意味で、知的資産経営、社長との対話ツールであるローカルベンチマークや経営デザインシートは、今後の業務にも活かせる内容だと思いました。実践科目の試験対策としては、財務情報の定量分析、SWOT分析が役に立ちました
「企業法務」の民法分野を理解するのが難しかったです。債務不履行や不法行為の比較、時効成立年数の違いなどは、何度も確認して試験に臨みました。「事業性評価」も馴染みがなかったので、全体像を掴むのに苦労しました。また、事例問題で何を、どう問われるのか情報が少なく、試験時まで解けるか不安でした。
1日の平均学習時間、学習の際に工夫した点がありましたら教えてください。
平日は約1~2時間、休日は約2~3時間の学習時間を取りました。3月の2科目合格に向けて、11~12月にはWebの各講義を2回受講しました。1講義30分程度なので、1日あたり3~4講義進めていました。講義動画の視聴は平日朝1時間、帰宅後1時間程度行い、各講義を受講直後にテキストの問題を解きました。
時間があればテキストを読み、分からない単語の意味を調べました。1月以降はトレーニングの問題を解き、知識科目の4科目は3回程度、事業性評価は4回解きました。間違えた箇所はメモに書き出して覚えるようにしました。
試験対策時の苦労したことは、「企業法務」がなかなか覚えられなかったことです。間違った問題はノートにメモし、机の脇に置いて何度も見返すことで覚えるようにしました。事例問題は初めて解いたときは時間がかかりましたが、繰り返し解くことで時間配分にも気を付けて解けるようになりました。
仕事との両立のため、朝5:30に起きて7:00まで勉強時間を確保するようにしました。帰宅後は疲れて効率が良くないこともあるので、できるだけ朝に学習することを心がけました。休日は午前中に時間を取り、学習に充てました。
CBT受験について、感想と受験のコツや注意点を教えてください。
CBT受験は初めてで、試験情報もあまりないように思ったので、実際に受験するときは緊張しました。操作方法、何かトラブルがあったときの対処法、計算機の使い方、解答がうまく選択されているか、両隣が気にならないかなど、色々と不安でした。
しかしながら、試験中は集中できたので、学習した内容を落ち着いて解答すれば問題ないと思います。実践科目の記述では、あまり時間がない中で、解答は読み返して日本語としてきちんと伝わるように心がけました。
分からない問題や、自信がない問題も後回しにして見直しました。見直したことにより正解になった問題もいくつかありました。また、何回か修正した問題もあったので、見直す時間は取れるような時間配分を心がけた方が良いです。
対話力向上講習について
午前中の問題解決のプロセスの考え方は、業務を行う上でも役に立つ内容でした。問題の原因を分解し、問題の本質に迫りながらロジカルに考えることで解決策に繋げることは非常に有益だと思いました。経営者と対話する場合の準備の重要さ、定性情報・定量情報として何を準備するのかという重要な点を学習することができました。
ローカルベンチマークや経営デザインシートの使い方も学ぶことができました。午後は事例企業を題材にしたロールプレイングを行いましたが、制限時間内にリスニングし、まとめるのは難しいことを実感しました。
問題発見と解決方法の考え方は、仕事でも日々直面する問題に際して活用できると思いました。ロールプレイングで使用した問題分析シートに記載されているテンプレートは、問題解決の方向性を考える上で、そのまま仕事でも使えると思いました。
これから資格をどのように活かしていこうとお考えですか?
気候変動などにより、これまで獲れていた魚が獲れないなど、水産業は大きな転換期を迎えています。環境の大変動に対して、水産業者はいかに適応していけるかという重要な時期に来ています。
このような困難な状況で、科学的な知見に加え、経営的な視点でも経営者と対話をしながらサポートしていきたいと考えています。
これから受講を検討されている方に、メッセージをお願いいたします。
技術など専門性をお持ちで、さらに経営者のサポートをしたいという人には、チャレンジするのに良い資格だと思います。
企業経営アドバイザーは知識を問う試験だけでなく、対話力向上講習があり、経営者とどのような観点で話をすれば良いのかを学ぶことができて非常に有意義です。ぜひチャレンジしてください。