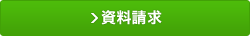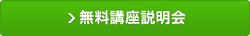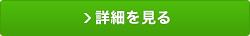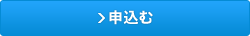「7つの習慣」プロローグ
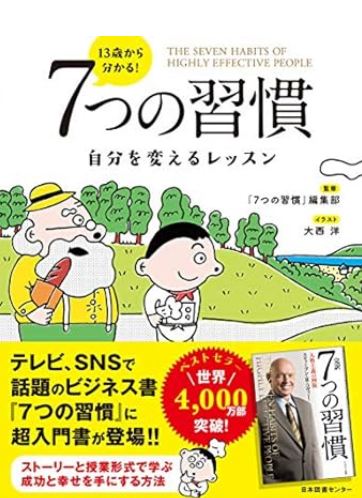
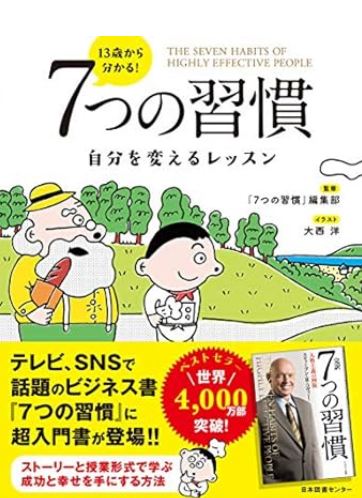
13歳から分かる!7つの習慣 自分を変えるレッスン(講座:参考書籍②)
世界4000万部のロングセラー、テレビ、SNSで話題のビジネス書「7つの習慣」に超入門が登場!原書のエッセンスをぎゅっと煮つめ、13歳でも分かるようにやさしく解説!
ストーリーと授業形式で気軽に読める!キーフレーズや重要なポイントはしっかり押さえているので、読み応えは十分!イラストや分かりやすい事例が満載!
出版社:日本図書センター


完訳 7つの習慣 (講座:参考書籍①)
世界中で読まれている、ビジネス書の代表的なロングセラー(4000万部)日本でも1996年に発売され、260万部を超えるベストセラーに
著者スティーブン・R・コヴィー博士は英国「エコノミスト誌」から世界で最も大きな影響力を持つ経営コンサルタントと評価
2012年 満79歳没
7つの習慣とは?
7つの習慣:第1の習慣から第7の習慣
『7つの習慣』は単なる成功法則ではなく、「人格」に基づいた原則を日々の行動として習慣化することによって、長期的な成果と幸福を得るための方法論です。
第1の習慣 主体的である
第3の習慣 最優先事項を優先する
第4の習慣 Win-Winを考える
第6の習慣 シナジーを創り出す
第7の習慣 刃を研ぐ
-7つの習慣の概要-
スティーブン・R・コヴィー氏著『完訳7つの習慣』(FCE/キングベアー出版)は、個人の成功とリーダーシップに関する世界的なベストセラーである。本書は、単なる「個性主義」な成功にとどまらず、「人格主義」に基づいた原則を実践することで、真の成功と永続的な幸福を得られると説く。 『7つの習慣』では、人間の成長を 「依存」→「自立」→「相互依存」 の3つの段階で捉えている。第1〜第3の習慣を通じて依存から自立へと成長し、私的成功を収める。次に、第4〜第6の習慣により、相互依存の段階へ進み、公的成功を実現する。そして、第7の習慣によって、継続的な成長を目指す。
-第1の習慣-
「主体的である」
人間には、「刺激」と「反応」の間に 選択の自由 がある。この選択の自由は、以下の4つの能力によって支えられている。
・自覚(自分の思考や感情などを客観的に認識する力)
・想像(現状を超えて可能性を描く力)
・良心(普遍的な原則に照らして、自分の考えと行動がその原則と一致しているを判断する能力)
・意志(自覚に基づき、外部の影響に関わらず、自分の価値観に沿って行動を選択する力)
反応的な人は、周囲の環境や状況に影響を受け、その場の感情や外部要因によって行動を決めてしまう。一方で、主体的な人は、この4つの能力を活用し、自分の感情や衝動などをコントロールし、価値観に基づいた選択を行うことができる。「自分自身の人生を形づくるのは自分である」ということを認識し、それを実践することが、第1の習慣の本質である。
(重要キーワード⑤ 私的成功3-1)
-第2の習慣-
「終わりを思い描くことから始める」
物事は 「始め」と「終わり」の二度つくられる という原則がある。 つまり、最初に 心の中で描かれ(知的創造)、次に 実際の行動として具現化される(物的創造) というプロセスを経る。 第2の習慣では、この知的創造を意識し、自分がどのような人生を歩みたいのかを明確にすることが重要である。この習慣の実践として、「個人のミッション・ステートメント」を作成することが推奨されている。これは、自分の価値観や目標を明文化し、人生の指針とするためのものである。 原則中心の生き方によって、以下の4つの特性が得られる
・安定(自己の存在価値・自尊心の確立)
・指針(意志決定・行動基準・規範の確立)
・知恵(人生観・バランス感覚の養成)
・力(主体的に行動する力・潜在的能力の発揮)
この習慣は、第1の習慣の 創造力 と 良心 を基盤にしている。つまり、「終わりを思い描くことから始める」を明確にすることで、日々の行動や意思決定に 一貫性と方向性 を持たせることができる。
(重要キーワード⑤ 私的成功3-2)
-第3の習慣-
最優先事項を優先する
第3の習慣は、第2の習慣で明確にした自らの価値観とビジョンに基づいて、最も重要なことに時間とエネルギーを集中させることである。これは、第2の習慣でリーダーシップを発揮して「何を」するかを決め、第3の習慣でマネジメントを行って「どのように」実行するかという流れになる。具体的には、物事を以下の4つの領域に整理する
・第Ⅰ領域(緊急かつ重要):危機対応、締め切りのある仕事、健康問題など
・第Ⅱ領域(緊急ではないが重要):自己啓発、人間関係の構築、健康維持、計画的な仕事など
・第Ⅲ領域(緊急だが重要でない):他者からの要求、会議、不要な電話やメール対応など
・第Ⅳ領域(緊急でも重要でもない):無意味な娯楽、暇つぶし、依存的な行動など
第3の習慣では、自分を律し、第Ⅰ領域(緊急かつ重要)と第Ⅱ領域(緊急ではないが重要)を優先的にバランスよく実行するマネジメントを行うことが求められる。「最優先事項を優先する」ことで、短期的な誘惑や緊急事態に振り回されることなく、自分の価値観に基づいた充実した人生を築くことができる。
(重要キーワード⑤ 私的成功3-3)
-第4の習慣-
Win-Winを考える
Win-Winとは、双方が利益を得る解決策を模索する姿勢であり、競争や対立ではなく、協力と相互利益を追求する考え方である。
【基本的なパターン】
・Win-Win:互いに尊重し、共に成功を目指す協力的な関係
・Win-Lose:自分が勝ち、相手が負ける競争的な関係
・Lose-Win:自分が譲り、相手に従う屈従的な関係
・Lose-Lose:お互いが妥協し、共に負ける関係
・Win-Win or No Deal:合意できない場合は取引しないという選択肢
Win-Winを実現するには、以下の五つの側面が重要である
1.人格:誠実さ、成熟(勇気と思いやりのバランス)、豊かさマインド
2.人間関係:信頼関係と互いの立場の理解
3.協定:相互の期待、役割、目標、資源の明確化
4.構造とシステム:Win-Winを支援する組織的な仕組み
5.プロセス:問題解決と意思決定の方法
この習慣は、第5の習慣(まず理解に徹し、そして理解される)と第6の習慣(シナジーを創り出す)と深く結びついており、これらを総合的に実践することで、より豊かで効果的な人間関係を構築することができる。
(重要キーワード⑥ 私的成功3-1)
-第5の習慣-
「まず理解に徹し、そして理解される」
効果的な人間関係を築くには、まず相手を深く理解することが、信頼と相互理解の基盤となる。人格の成熟が効果的なコミュニケーションの前提である。 【まず理解に徹する】 人は一般的に、自分の経験や価値観を基準にして相手の話を聞く。しかし、それでは本当の意味で相手を理解することはできない。そのために、共感的傾聴を実践することが重要となる。 共感的傾聴とは、単に話を聞くのではなく、相手の立場や感情を深く理解しようとする姿勢で聴くことである。
【理解に徹した後に、理解される】 まず相手を理解しようとすることで、信頼関係が生まれ、結果として自分の考えも理解されるようになる。 お互いに本当に理解し合えたとき、意見の違いは対立の原因ではなくなり、むしろ成長と発展のための土台となる。これにより、”第6の習慣(シナジーを創り出す)”につながり、相乗効果を生み出すことができる。
(重要キーワード⑥ 私的成功3-2)
-第6の習慣-
シナジーを創り出す
”シナジー(相乗効果)”とは、異なる個性や意見を統合し、単独では生み出せない新たな価値や成果を創り出すこと。単なる妥協ではなく、それぞれの強みを活かし、より高いレベルの解決策を生み出すプロセスである。
【シナジーの本質】
シナジーは第1~第5の習慣の統合によって生まれる。特に、以下の要素が重要となる。
「自覚・想像・良心・意志」の4つの能力(第1の習慣)
「Win-Win」の精神(互いの利益を考える姿勢)(第4の習慣)
「共感的傾聴」(相手を深く理解する姿勢)(第5の習慣)
【シナジーの実践】
シナジーの実践には勇気とオープンマインドが必要であるが、それによって得られる創造的な成果は、単独の努力では決して達成できないものである。異なる意見や価値観が対立する場面でシナジーを意識すれば、単なる妥協ではなく、新たな可能性を見出せる。シナジーは、個の力を超えた成果を生む最も崇高な活動であり、全体が部分の総和を超える状態を生み出す。第1~第5の習慣を統合・進化させるプロセスそのものである。
(重要キーワード⑥ 公的成功3-3)
-第7の習慣-
「刃を研ぐ」— 再新再生すること
つまり、自分自身を定期的にリフレッシュし、成長を続けること。 これは、第1〜第6の習慣を継続・向上させるための基盤となる。
4つの側面の再新再生
・肉体(Physical):運動・栄養・ストレス管理
・精神(Spiritual):価値観の明確化・学習・瞑想
・知性(Mental):読書・視覚化・計画立案・執筆
・社会・情緒(Social/Emotional):奉仕・共感・シナジー・内面の安定
これら4つの側面は相互に関連し、影響し合っている。一つの側面での成長は他の側面にも良い影響を与える。バランスよく全ての側面に取り組むことで、相乗効果が生まれる。 再新再生は「学び→決意→実行」という循環的なプロセスであり、継続的に行うことで上向きの螺旋状に成長していく。自分自身を継続的に成長させることで、私的成功(自立)と公的成功(相互依存)を維持・向上させ、より充実した人生を送ることができる。
(重要キーワード⑥ 公的成功3-3)
-7つの習慣:重要キーワード-
-①人格主義-
人格主義は、単なる「個性主義的」な成功にとどまらず、人格を磨くことで真の成功と永続的な幸福を得られるという考え方である。 スティーブン・R・コヴィー氏は、1776年のアメリカ合衆国独立宣言以降200年間にわたる成功に関する文献を調査した。その結果、過去50年間の書籍では、成功を収めるための二次的なテクニックに焦点が当てられていることが分かった。一方で、建国から最初の150年間の文献では、誠意、謙虚、誠実、勇気、正義、忍耐、勤勉、質素、節約、黄金律といった「人格」の形成に関わる内面的な特性が、真の成功の条件として重視されていた。 つまり、成功とは単なるスキルやテクニックによるものではなく、人格を基盤としたものであるべきだとされていたのである。この観点こそが、人格主義において最も重要な点である。アリストテレスが「人格は繰り返し行うことの集大成である」と述べたように、この「7つの習慣」を継続的に実践することで、「人格」は形成され、磨かれていくのである。
-②パラダイム-
パラダイム(Paradigm)とは、一般的にモデル、理論、既成概念などを指し、要するに「物事の見方」を意味する。 つまり、私たちが物事をどのように認識し、理解し、解釈するかを決定づける枠組みである。 多くの人は、自分が物事を客観的に捉えていると考えがちだが、実際にはそうではない。 私たちは、それぞれの経験や環境によって条件づけられたフィルターを通して世界を見ている。 したがって、まず自分が「あるがままの世界」を見ているのではなく、自身の価値観や信念に影響を受けた視点で 世界を捉えていることを認識することが重要である。
-③パラダイムシフト-
パラダイムシフトとは、物事の見方や認識を根本的に変化させることである。人格主義の土台となる考え方は、自然界における引力の法則と同様に、人間の本質的なあり方を支配する普遍的な原則に基づいている。これらの原則は、人間社会においても時代を超えて変わることのない普遍的な法則であり、異議の余地がない。したがって、より良い生き方を実現するためには、「物事の見方やあり方」を根本から見直し、適切なパラダイムシフトを行うことが重要である。また、どんなに困難な問題であっても、それを解決するためには、表面的な対処ではなく、より深いレベルでの思考の転換が求められる。そのためには、自分の内面を起点とする「インサイドアウト」のアプローチへとパラダイムシフトすることが不可欠である。
-④インサイドアウト-
根本的で深い問題を解決するには、表面的な対処ではなく、普遍的な原則を中心に据え、人格を土台としたパラダイムが必要である。『7つの習慣』は、このような新たなレベルの思考を促すものであり、「インサイド・アウト(内から外へ)」のアプローチを重視している。つまり、問題の本質は外部ではなく、自分自身の内面にあると捉え、自己の成長を通じて効果的な人間関係を築くことを目指すものである。また、このアプローチの前提として、例えば、まず自分自身が成熟してこそ、他者との効果的な関係を築けるという考え方がある。すなわち、公的成功を収めるためには、その基盤として私的成功を確立することが不可欠である。
-⑤私的成功-
第1の習慣(主体的である)、第2の習慣(終わりを思い描くことから始める)、第3の習慣(最優先事項を優先する)を身につけることで、自分自身を深く理解し、自己を律し、本質や価値観を意識的にコントロールできるようになる。その結果、充実感や平穏な気持ちが生まれ、依存から自立し、自らの判断で行動ができるようになる。さらに、自立を確立することで、他者の考え方を受け入れ、人間関係を大切にする姿勢が育まれる。 こうした変化が、自身の成長意欲を引き出し、自分をより良い方向へと変えていく原動力となる。そして、このプロセスを経ることで、真の自尊心を持つことができるようになり、私的成功を収めることができる。
-⑥公的成功-
私的成功によって真に自立した人間になることで、相互依存の人間関係を築くことが可能となる。これを実現するためには、第4の習慣(Win-Winを考える)、第5の習慣(まず理解に徹し、そして理解される)、第6の習慣(シナジーを創り出す)といった「公的成功につながる習慣」を身につけ、相互依存のパラダイムを理解することが不可欠である。 しかし、相互依存の関係を効果的に築くためには、その基盤となる私的成功が重要であり、第1の習慣(主体的である)、第2の習慣(終わりを思い描くことから始める)、第3の習慣(最優先事項を優先する)といった「私的成功を築くための習慣」を磨き続けることが不可欠である。 なお、私的成功と公的成功は切り離されたものではなく、人格の習慣を土台とすることで、より良い相互依存の関係を築くことができる。